 |
シルバーの城郭城跡の散歩道「目次」
|
あなたは |
終更新日付 16/02/04 16:06 |
シルバーの散歩道わき道3の城郭・城址の散歩道は国宝犬山城と小牧長久手合戦主要城址・砦址、尾張名古屋城、
金華山岐阜城、苗木城址、高山市付近の城跡、美濃大垣城と周辺の城址などをたずねてリポートします。.
| NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」の嫡男「松寿丸」が織田信長の命に反して竹中半兵衛によって、 匿(かくま)われていた「五明稲荷神社」(岐阜県垂井町)のイチョウの木が伐採されることとなったと 地元紙が伝えていました「10大垣城周辺の城郭城跡(不破郡編)」に掲載してあります。 また、竹中半兵衛陣屋跡、菩提山城址なども掲載してありますので、是非ご覧ください。 |
|
|
|
美濃地方の「腰掛石」集 |
岐阜県の伊吹山の麓「玉」地区にある「日本武尊命腰掛石」はじめ、岐阜県中加子母の大杉の「源頼朝の腰掛石」、時代は下がって不破郡関ケ原町今須の「徳川家康腰掛石」など、さしも珍しくもない腰掛石を訪ねて背景の歴史を(計画中) |
|
|
|

|
安土城址と繖山安楽寺 |
|
|

|
美濃地方にある平将門伝説の地 岐阜県美濃地方にある平将門伝説の地、将門の首を鎮めるために祀られた「御首神社」、空を飛ぶ将門の首に向かって射られた矢が飛んだ道にある大垣市矢道町の「矢劔神社」。 矢を放った神の住む「南宮大社」(不破郡垂井町)を紹介します |
|
|
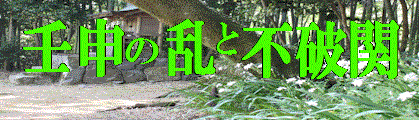
|
壬申の乱と不破関址 序章美濃洲俣(現墨俣)不破神社の化身による大海人皇子の決起から、野上に行宮を興し本営として、「和蹔邑(わざみむら)」への大友皇子軍(弘文天皇)の奇襲に反撃し、玉倉部邑への大海人皇子軍(天武天皇)の大反撃、結章の「近江瀬田の戦い」までの「壬申の乱」址の紹介(結章未作成) |
|
|
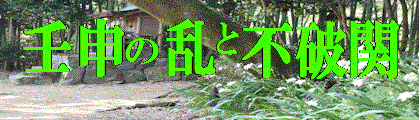
|
関ケ原合戦古戦場址(一部修正中)
徳川家康最初の陣跡(桃配山陣跡)、から開戦の地、東軍22陣址のうち11陣址と西軍石田三成笹尾山本陣はじめ9陣址、反応軍5陣址のうち2陣址、傍観軍5陣址の計28陣址の紹介と鳥頭坂の島津豊久の碑、奥平貞治の墓、決戦の地、家康最後の陣址、東軍の首塚、西軍の首塚など紹介。 |
|
|
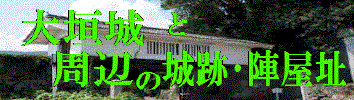
|
大垣城と周辺の城址・陣屋跡(一部修正中)
関ヶ原合戦の時、重要な役割を担った大垣城の周辺の城跡・陣屋跡を大垣市内22・羽島市9・安八郡8・本巣市23・揖斐郡池田町8・揖斐郡大野町11・揖斐郡揖斐川町10・揖斐郡旧村15・不破郡11・養老郡10・海津郡8の合計143城址陣屋址 |
|
|

|
尾張名古屋城 関が原の戦いでほぼ天下を取った家康でしたが、いまだ大阪城には豊臣秀吉の遺児秀頼が居ました。 そこで天下取りを磐石とするため、大阪方の防衛拠点とするためにこの地名古屋に慶長14年(1609)築城に着手。慶長17年(1612)に城を完成させました。 |
|
|

|
日本有数の要害・岐阜城 濃尾平野の北端、岐阜市街地の北部に屹立(きつりつ)する金華山上に築かれた山城。古くは井ノ口(いのぐち)城、稲葉城とよばれ、南と北に木曽川・長良川という天然の堀をもち、三方を急峻な断崖に守られた日本有数の要害でありました。岐阜城は斉藤道三と織田信長の国盗り物語で歴史の脚光を浴びた城 |
|
|
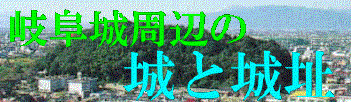
|
岐阜市周辺の城と城址 岐阜城を取り巻く岐阜市内の加納城址はじめ、各務原市、関市、美濃加茂市、羽島郡、加茂郡、本巣郡と県下の高山市の高山城址などと、郡上市、中津川市、瑞浪市、恵那郡の主要な城と城址をご案内します。 |
|
|

|
大垣城 大垣城は、牛屋川=水門川)や豊富な自噴泉を利用して、四重の水堀を擁する要害堅固な城でした。 その中心に、4層4階の白亜の天主がそびえていた。南と東に大手、北と西を搦手とし、総曲輪には七つの門、三重櫓5基、二重櫓10基、渡櫓26基を備え、外堀と中堀の間を武士屋敷が埋めつくしていた。 |
|
|
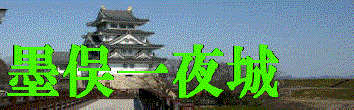
|
美濃 墨俣一夜城 永禄九年(1566)、木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)が一夜にして築いたと伝えられる墨俣一夜城は、 藤吉郎が「天下人」となる出発点として全国にその名を知られております。 |
|
|
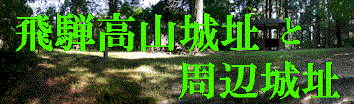
|
飛騨高山市付近城址 飛騨高山市付近にある高山城址(城山公園山頂)、 松倉城址(飛騨の里おく峠付近)、三仏寺城址(市内三仏寺町)鮎崎城址(市北部大八賀川河畔北山公園)、鍋山城址 、冬頭城址、堂洞城址、岩井城址、畑佐城址、石光山砦、 飯山城址、松亭址などの諸城址めぐりを紹介します |
|
|
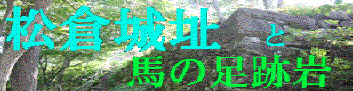
|
松倉城址と馬の足跡岩 飛騨国司姉小路中納言三木左京太夫自綱の居城松倉城址は、天正十三(1585)年、豊臣秀吉の命を受けた金森長近・可重父子に攻められ、落城し猛火の中、愛馬にまたがり一気に飛び降りた。それが、この岩上であると伝えられている。 |
|
|
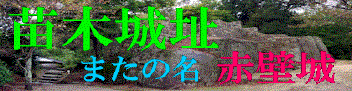
|
中津川・苗木城址
苗木城は、幾度塗り替えても竜にはぎ取られ赤壁が残るという「赤壁伝説」の史跡「赤壁城」、また城に危機が迫ると木曽川から霧が一面に立ちあがり、城を隠してしまうという伝説があり「霞城」とも言われる。 |
|
|

|
国宝 犬山城 国宝 犬山城 現存する天守で最も古いといわれ城は木曽川南岸の要害の地にあります。平山城で別名を、中国の詩人李白の詩文にちなみ「白帝城」とも呼ばれます。犬山城のはじまりは1537年(天文6年)に木ノ下城を三光寺山(犬山城の現在地)へ移し織田信康が入城し犬山城の歴史が始まりました。 |
| 小牧・長久手の主要砦城 | ||
|
|
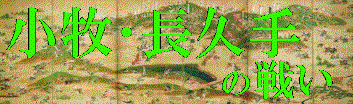
|
小牧・長久手の戦いの城砦址と遺構など 織田信雄の三家老謀殺に始まり、池田恒興離反による犬山城落城、羽黒の戦い、白山林の戦い、桧ケ根の戦い、長久手の戦い、加賀野井城の戦い、竹が鼻城の水攻め、奥城籠城、蟹江合戦など伊勢長島から西尾張、羽黒、小牧山、長久手地域に広がる広範囲の地域に両軍合わせて八万余の兵が約9ケ月にわたって戦いを展開した城址や合戦跡を巡ってみました。 |
|
|
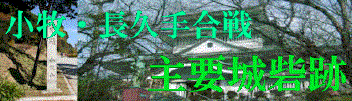
|
小牧・長久手合戦主要城砦跡 |
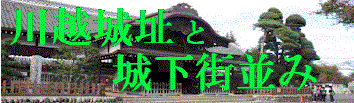
|
川越城址と城下街並み 川越城は、長禄元年に太田道真・道観父子によって築城された。後に北条氏に、また豊臣秀吉の家臣前田利家に攻められて落城。江戸時代になると、江戸の守りとして重要視され親藩・譜代の大名が藩主に任じられたが天守はなく富士見櫓が代り |
|
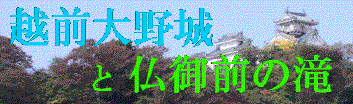
|
越前大野城と仏御前の滝巡り 織田信長に仕えていた武将、金森長近が築いた越前大野城と城下町。大野市仏原の荒島岳から流れ出る高さ100mに及ぶ三段の滝「仏御前の滝」。「瀬戸大橋」のプロトタイプとして作られた九頭竜湖に架かる吊り橋「夢の掛橋」などを巡ります。 |
|
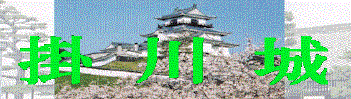
|
戦後初めて木造で復元された・掛川城 掛川城は、室町時代中期に今川氏の家臣であった朝比奈氏の城であったが武田信玄の侵攻によって、国主今川氏真は掛川城に逃げ込んだ。その後徳川氏の侵攻により落城後山内一豊が五万石で入部し天守を造り現在の姿になる。幕末地震により倒壊。維新により取り壊されたが・・・・ |
|
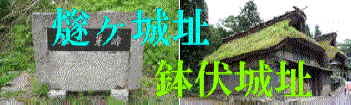
|
燧(ひうち)ヶ城跡・観音寺丸城址・ 木の芽城址・西光寺丸城址・鉢伏城址 福井県今庄町のかたくりの里・今庄宿の上にそびえた源平の古戦場で有名な燧ヶ城跡と板取宿から言奈地蔵・木の芽峠へと登り観音寺丸城址・木の芽城址・西光寺丸城址と鉢伏山山頂にある鉢伏城址の五城址を訪ねました。 |
|
|
|
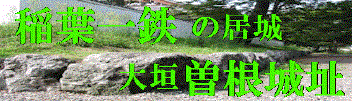
|
計画中 |
|
|
計画中 |
|
|
|
計画中 . |
GPS位置情報は目標物の測定位置が建物や遺構の中心でなく道路から辿るのに分かりやすく、
駐車場、鳥居、玄関などの場合もあります。その他の情報も2002年頃に現地で確認したものですので、
その後、道路拡幅などによる移転や行政合併特例法による市町村合併で市町村名の変更があるので
その後の情報でご確認ください。memoリンク
シルバーの城郭城跡の散歩道「目次」