|
�z��ҁF �z��N��F |
 |
���ݒn
�F �s���؎R �`�@�� �F �R�@�@�� �@�@ |
�V���o�[�̏�s��Ղ̎U�����u���؎R��v
���ǐ�������낷���؎R�ɂ��т�����͐ē����O�ƐD�c�M���̍����蕨��ŗ��j�̋r���𗁂т���ł��B
|
�z��ҁF �z��N��F |
 |
���ݒn
�F �s���؎R �`�@�� �F �R�@�@�� �@�@ |
���{�L���̗v�Q�E��
�Z������̖k�[�A�s�X�n�̖k���ɛ����i����j������؎R�i�R�Q�X���j��ɒz���ꂽ�R��B
�Â��͈�m���i���̂����j��A��t��Ƃ��A��Ɩk�ɖؑ]��E���ǐ�Ƃ����V�R�̖x�������A
�O�����}�s�Ȓf�R�Ɏ��ꂽ���{�L���̗v�Q�ł���܂����B
 |
|
�R���̊�Ƙ[�̐���~�i�����j |
��̗��j
|
��̗��j�i���̈�j ��K���s���`����V���q��� |
|
�@�@�@�@�ŏ��͊��q���{�̍� �@�@�@�@�@���́u��K���s���v�Ɣ��Z |
|
|
|
���{���F�@��K���s���� |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��K���̖��O�̗R�� �@��K�����́A������ƕ��q�����H�����̈ꑰ�ňۉ���c�Ƃ���B�������͉��B�����œ�������łڂ������A����ɍU�ߍ��Ƃ��������̑��c�����������̑s�傳�ɋ������B �@�Ȃ��ł���K���̌��z���ɃJ���`���[�V���b�N���o�����Ƃ����B �@���̌�A�����͕킵�Ċ��q�i�����ɓ�K�哰�����z�������̂ł���B �@��K�哰�͓�K���Ƃ��̂���A�H�����̈ꑰ�s�����i�����̋߂��ɏZ��œ�K�������̂���悤�ɂȂ����̂����������̎n�܂�Ƃ�����B �@�@�@�i�Q�l�F�퍑�喼�T����http://www2.harimaya.com/sengoku/html/2kaido_k.html�j |
|
�@�@�@�@�@�@�@��t�R��̖��̗R���ƕϑJ �i�Q�l�F�s�u�L�Ӂv���W�M�������A�ƃE�B�L�y�f�B�A���j |
���@�@�]���u�ē����O�́u�܂ނ��v�ƌĂ�����肩��g��������Ƃ̓y�������荑��ƂȂ���
�ƌ����悤�ȋ؏��������p���ꂽ���A�ŋ߂̌����̌��ʉ��L�̂悤�Ȑ��ڂł͂Ȃ����ƌ�����B
|
�N�@�@�@�� |
��@�@�� |
�o�@�@���@�@�� |
| �@���m�̂����i1201�`03�N�j |
��K���s�� |
�@��K���s�������Ԃ� |
| �A���̌� |
���@�� |
�@��K���s���̎q���͂����ɋ��邵�A������t���Ɖ��߈�t�R��Ƃ�����悤�ɂȂ�B |
| �B�퍑���� |
�y��E�ē� |
�@�y��E�ē����̈ꑰ���Ԃ���ɒz���鉺�����ł���B |
| �C��i�ܔN�i�P�T�Q�T�N�j�A |
����V���q��� |
�@���Z���ŁA�����������A����ē����͒Ǖ�����A ����V���q����̋���ƂȂ�B |
| �D�V����N�i1533�N�j |
�֓����O |
�@����V���q��т��v����ƁA���̎q�A����V��Y�K�G�i����֓����O�j������p���A���ƂȂ�B |
| �E�V�����N�i1539�N�j |
�֓������i���O�j |
�@����ɂȂ��Ă����֓������i���O�j���A���؎R�R���ɏ�����n�߂�B |
| �F�V���\�N�i1541�N�j�B |
���@�� |
�@�֓������i���O�j�A���y�|��Ǖ� |
| �G�V���\�Z�N�i1547�N�j |
�D�c�M�G |
�@�D�c�M�G�i�M���̕��j�A�y�|�h�̉Ɛb�ƈ�t�R�鉺�܂ōU�ߓ������s�i���[���̐킢�j�B |
| �H�V��23�N�i1554�N�j �@ |
�֓��`�� |
�@�ē������A��ƉƓ𒄎q�֓��`���ɏ���䔯�A���O�ƍ�����B |
| �I�O����N�i1556�N�j |
���@�� |
�@�ē��`���A���ǐ�̐킢�ɂ�������O�����B |
| �J�i�\4�N�i1561�N�j |
�֓����� |
�@�ē��`���̋}���ɂ��֓�������13�ʼnƓ��p���A���ƂȂ�B |
| �K���N |
���@�� |
�@�\�l���̐킢�ɏ��������D�c�M������t�R����U�߂���s�ށB |
| �L�i�\���N�i1564�N�j | �@�֓����̉Ɛb�ł������A�|���d����������A���������A�����B��t�R����U�߂�B������͏���̂āA�|���炪��N�Ԑ苒����B | |
| �M�i�\10�N�i1567�N�j |
�D�c�M�� |
�@���˂Ă�����Z�U����_���Ă����D�c�M���������Z�O�l�O�̓����ɂ���t�R�鉺�ɐi�U�B�i��t�R��̐킢�j�B�ē������́A����̂ĂĒ��ǐ���M�ł�����A�ɐ������֓��S�B |
| �N���N |
���@�� |
�@�D�c�M���́A�{���n�����q�R�����t�R�Ɉړ]���A�Ñ㒆���Ŏ������̕�������R�ɂ���ēV���肵���̂Ɉ���ŏ�ƒ��̖����u�v�Ɖ��߂��B���̍�����M���́A�u�V���z���v�̎���p����悤�ɂȂ�A�{�i�I�ɓV�������ڎw���悤�ɂȂ����B |
|
�i�Q�l�F�s�u�L�Ӂv���W�M�������A�ƃE�B�L�y�f�B�A���j |
||
��̕ϑJ�i�Â��j
|
�N�@�@�@�� |
��@�@�� |
�o�@�@���@�@�� |
| �O�V���l�N�i1576�N�j |
�D�c�M�� |
�@ �M���͒��q�D�c�M������̏��Ƃ��A�D�c�Ƃ̉ƓA�y�є��Z�A������2����������B��̐������C�͐D�c�M���i�M���̒��j�j�ɂ���čX�ɒlj��B |
| �P�V��10�N�i1582�N�j |
�D�c�M�F |
�@�D�c�M�����M���Ƌ��ɖ{�\���̕ςœ|���ƁA�Ɛb�̍֓���ꟁi�ē����O�̎q�j�����������B�������A���q���G���H�ďG�g�ɔs�����D�c�M�F�i�M���̎O�j�j�ɍ~���B |
| �Q���N�Z�� |
���@�� |
�@���F��c�ɂ���M�F���Z�E�M���̈�̔��Z����q�́A��̏��y�сA�M���̒��q�O�@�t�̌㌩�ƂȂ�B |
| �R���N12��20���A |
���@�� |
�@�H�ďG�g�A�O�H���G�A�r�c�P���̒��j�E������̕�����ɔ������ׁA�a�r�B�O�@�t�������n���B |
| �S�V��11�N�i1583�N�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 4��16�� |
�M�F�͐ؕ� |
�@�M�F�͒������̑���v�ƌĉ����ēx�����B���������Z�Ԃ��i�˃��x�̐킢�j�ɂ���Ďēc���Ƃ��s��A�Z�E�M�Y�ɂ���ċ���̊���͂����ƁA����ɍ~�������B�邩��͓��S���������~�����̐l����27�l�ł������Ƃ����B���̌�A�M�F�͐ؕ�������ꂽ�B |
| 21�@���N�A |
�r�c���� |
�@�r�c�P�������Z���ɂ�13����q����_���ƂȂ�ƁA�r�c���������ƂȂ�B |
| 22�@�V��11�N�i1584�N�j |
�r�c�P�� |
�@���q�E���v��̐킢�Œr�c�P���ƌ����������������߁A�P���̎��j�E�r�c�P���̋���ƂȂ����B |
| 23�V��19�N�i1591�N�j4�� |
�L�b�G�� |
�@�]���ɂ��A�P���ɑ������L�b�G������̏��ƂȂ�B |
| 24���\���N�i1592�N�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@9��9�� |
�D�c�G�M |
�@�L�b�G�����v����ƁA�D�c�G�M�i�c���E�O�@�t�j�����Z����13����̗L����̏��ƂȂ�B |
| 25�c���ܔN�i1600�N�j |
���@�� |
�@�D�c�G�M�́A�Γc�O���̋����Ɍĉ������R�ɂ��B�փ����킢�̑O����ŁA��ɗ��Ă����邪�A����������r�c�P����ɍU�߂��ė���B�G�M�͒�G���Ƌ��Ɏ��n���悤�Ƃ������A�P���̐����Ő����i�炦��B���������̌�͏o�Ƃ���������A����R�Ŕ��Q�A�Ǖ�����A1605�N�i�c��10�N�j�Ɏ��S�����B�G�M�͊�̍Ō�̏��ł��������A���̏�̏��͍֓����O�ȍ~�A�Z���������P���������A�S����Ƃ̎��𐋂������ƂɂȂ�@ |
| 26�c���Z�N�i1601�N�j |
�p�� |
�@����ƍN�͊���p�������߁A�����M����10����^���āA���[���z�邳����B���̍ہA��R���ɂ������V��A�E�Ȃǂ͉��[��Ɉڂ��ꂽ�Ƃ����B�邪�R��ł��邱�Ƃɉ����āA�ƍN�����ĐM�����V�����̈ӎv�����߂Ė��������u�v�Ƃ����n�������������i���쎁�ɑ���V���l�̏o�����霂�����j���炾�Ƃ������Ă���B�@ |
|
�i�Q�l�F�s�u�L�Ӂv���W�M�������A�ƃE�B�L�y�f�B�A���j |
||
 |
|
�u�L�Ӂv�i���W �M����2012.1.1���j����u�����蕨��v |
 |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̗��j�i���̈�j�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�֓����O��i���O�E�`���E�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����O�̕��́u����V���q��сv �@�ŋߔ������ꂽ��ߍ]�̑喼�E�Z�p�����i���傤�Ă��j����A���O�̑O�����͕��E����V���q��сi��������̂��傤�j�̂��Ƃł���A�㔼�������O�̎��ցi������=�����̂��ƁB�����̍��Ձj�Ƃ������Ƃ��킩��܂����B�i�܂�e�q���Ŗ����肩��A�ꍑ���̎�ɂȂ����킯�ł��B�j �@�@�@�@�@�@�@���M���ȑO�ɓ��O�����i�����͈�m�����j�W������ �@���O�͈�t�R���v�Q�����A�R�̐��[�ɋ��ق����āA�S�ȒʂƎ��Ȓʁi���݂̊s�㒃���E��������������j�ɏZ�����W�߂ď鉺��������܂����B�i���}�Q�Ɓj �u�L�Ӂv�i���W �M����2012.1.1���j��� |
|
|
|
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̍��̐D�c�M�G�i�M���̕��j�Ɛē����O �@�D�c�M�G�͑O�サ���ߌÖ���i�����É���̓�V�ۂ�����ɍ݂����j�A���ˁi���傤�j�������X�ƍU�����B�x�͂̍��쎁�Ɛ키���Ԃ�D���Ĕ��Z�ɂ��i������ȂǁA�킢�̃Z���X�͔��Q�Ōo�ϗ͂�����܂������A�x�z���Ă����͔̂����̈ꕔ�̂݁B �@����A���O�́A�����p����������A����Ƃ̉Ɛb�ƌ������ꂩ��A������E�y��Ǖ����A���Z�̎���������܂ŏ��l�߂܂Ă��܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�L�Ӂv�i���W �M����2012.1.1���j��� |
|
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@���ˏ���i�i�O�͍��ɊC�S���遁�����m������s���钬�j |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���V���\�O�N�i�P�T�S�S�j�M���̕����U�ߍ��� �@�V���\�O�N�i1544�N�j�ɐM�����̕��E�M�G���z�O�E���q�F�i�ƘA���R��������Z�ɐN�U���܂� �@��t�R����߂���킢�ł́A��̌��鉺�����Ă������A�D�c�M�G�R�̖I�{��Ȃǂ͍]����ʂɐi�o���A�y���Y�͐ȓc�i�ނ��낾�����{���s�ȓc�j������܂ŐN���������ē������i���O�j�͍єz��낵���D�c�R�����ނ��A�D�c�R�͍U���ɓ�a���܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���D�c�R��P���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�L�Ӂv�i���W �M����2012.1.1���j��� |
|
|
�s�����ɂ����u�����ˁv |
|
|
�`�D�c�ˉ����n |
|
|
�@���͂��߂��u�����ˁv�ƌĂꂢ�܂����B �@����̂��Ə���[�̕S���B�͈��l�ɗ]��펀�҂��A���E�s�����ɂ��������V�i�̂��̉~�����j�ɖ������āA�y��グ�˂����܂����B �@���܂�˂̓y���肪�����̂��������ƌ����܂������A�����Ƃ͂Ȃ����u�D�c�ˁv�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B�i���݂��s�����ɂ���܂��j �@�̂������V�i�~�����j�����݂̐_�c�����ړ]����ɔ����A�u�D�c�ˁv���ړ]�������E�~�����̋����ɉ�������A�����̋����ɔ肪����܂��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ē����O���Ԃ���E�E����ɂɕ⋭ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ē������i���O�j���y�s�y�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���D�c�M�G�͐ē������i���O�j�Ƙa�r |
 |
|
�I�����O�ƐM����������������� |
|
���m�������s�N��x�́u�������Ձv�Ɣ� |
|
|
�킴�킴�����̉\�ƈ�����M�������������u�V�_�̓n���Ձv�i��{�s������2249-1�V�_�_�Ёj�� |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ē����O�ƐD�c�M��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ē������i���O�j�͉B�����A���O�𖼏�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����O�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ē��`�����a�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����t�R��E�D�c�M���ɍU������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���M������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�L�Ӂv�i���W �M����2012.1.1���j��� |
 |
 |
|
�M�����ɓ��邵�Ă���g�p���� |
�y�s�y�����D�i���d�v�������j�~������ |
| �@�@�@��̗��j�i���̎O�j�@�D�c���O��i�M���E�M���E�G�M�j �@�i�\�\�N�i�P�T�U�V�j�A�ē������i�������j����t�R�邩��Ǖ������M���́A�R�[�̈�m�����ɏ鉺�����ĐV���Ɂu�i�������̕����i�Ԃ��j����R�i������j�ɋ����ēV��������Ȃ��Ƃ����Ƃ����Î��Ɋ�j�v�Ɩ������A�u�فi����j�v�̎��̉ԉ��ƂƂ��Ɂu�V���z���v�̈��g�p���͂��߁A�̒n�����_�Ƃ��āA�V��������߂������鉺�����ɒ��肵�܂����B �M���͈�t�R�������Ƃ��� �@��t�R�����ƌĂ�A��̐������X�I�ɍs���A�֓����̋��ق��ĐV�����ق̌��݂��n�߂܂��B �@�܂��鉺���̔ɏ���}�邽�߂ɁA�s��ł̖Ə�����i�������H���̑g���j�̓�����ے肷��u�y�s�y���v�𐄂��i�߂����ʁA�M���̓����N��ɓ��n��K�ꂽ�|���g�K���̐鋳�t���C�X�E�t���C�X�́A���̗l�q���u�l������Ȃ����ꖜ�l�A�o�r�����̍��G�v�̂悤���ƁA�{���֕��Ă��܂��B �@�V���O�N�i�P�T�V�T�j�A�M���͊�j�̐M���ɏ���A���l�N�Ɉ��y���z���āA�����Ɉڂ�܂����B �@�V������֑傫�ȑO�i�������̂ł����A���N��̓V���i�P�T�W�Q�j�A���q���G�̖d���ɂ��u�{�\���̕ρv�ŁA���j�M���ƂƂ��ɋ��s�œ������܂����B �M���̑��G�M�̂Ƃ��փ����O����ʼnΖ�ɂ����������� �@���̏\�N��́A���\���N�i�P�T�X�Q�j�A�L�b�G�g�͐M���̑��G�M�����ɕ��i�ӂ��j���܂����B �@�������A�c���ܔN�i�P�U�O�O�j�փ�������ŁA�G�M�͉Ɛb�̔������������Đ��R�ɖ����������߁A���R�ɍU�߂��Ĕ�����\�O������A�G�M�͍~�����A����R�֑����ē��n�łQ�U�Ŏ������܂����B�i����ɂ͑��֓��꒷���������Ƃ̘b������܂��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�s�j |
|
 |
 |
|
�D�c�M���摜 |
��Ō�̏��E�D�c�G�M�摜 |
|
�i��W���i�摜���j |
|
�@
|
�D�c�M�������ِ� |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����~�̊��ؖ� |
|
 |
| �@�@ |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���H�ƐΊ_�A�K�i�� |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���p�Əo�p�E���w�ΐ� |
|
 |
|
�鋳�t���C�X�E�t���C�X |
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�c�M�����ِ� �@�i�\�\�N�i�P�T�U�V�j�D�c�M���́A��t�R���E�ē������i�������j��Ǖ����āA�u����i���̂����j�v����u�v�Ƃ��̖������߁A���؎R�R���Ɋ���C�z���ēV������ւ̋��_�Ƃ����B �@���؎R���[�ɂ����邱�̕ӂ�ɂ͐l�H�I�ȓ�`�O�i�̃e���X��n�`������A�ŏ�i�����~�A���i�ȉ��̑啔�������~���Ƃ����B �@�|���g�K���̐鋳�t���C�X�E�t���C�X�����̒����̒��ős��Ȃ��̂Ƃ��ďЉ���M���̋��ق̐ՂƂ����Ă���B �@���a�T�X�N����s�Ȃ��Ă������@�����ŁA�����ɔ�̋��𗧂ĕ��ׁA����~�ւƐ܂�Ȃ���Ȃ���オ���Ă����ʘH���͂��߂Ƃ��āA���̓r������͂ɔz�u���ꂽ�y�ۏ��\�E�Ί_�E�K�i�E���H�Ȃǂ��������ꂽ�B �@��́A�M�����ߍ]�̈��y�ֈڂ�����A�c���ܔN�i�P�U�O�O�j�փ����̑O����ŗ��邷��܂ő������A�����̈�\�̑����́A���̏o�y�i�Ȃǂ���M������ɂ��̊�{�I�ȑ��삪���������ƍl������B �@����p�����́A�]�ˎ���̑������❎��i����߂āj�哙�ɂ��������邪�A���̎����ɂ͋H�ł���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�s�j |
 |
|
| �����u���{�j�v �C�G�Y�X��̃|���g�K���鋳�t�t���C�X�͐M���̐M�p�āA�ߋE�𒆐S�ɓ��{�ł̕z�����������Ă����B ���M�̍˔\�ɂ��b�܂�A�����u���{�j�v���͂��߁A�l�X�ȕ����œ����̓��{���L�q�B ��ɂ��K��Ă���A���̋q�ϓI���ڍׂȋL�q�́A�����̔��@�ɑ傫�Ȏ肪����ɂȂ��Ă��܂��B |
|
 |
|
���ݔ��@���̐��ʂƃ��C�X�E�t���C�X�̋L�q����̐����}�i�L��u���Ӂv���j |
 |
 |
| �뉀�̉\���̂���u�`�n��v����o�y���������̏ĕ� | |
 |
 |
| �����H�u�a�n��v�i�L��u���Ӂv���j | |
 |
| ����ȐΗ�u�b�n��v |
| �|���g�K���鋳�t���C�X�E�t���C�X���u�A���J���ŃC�G�Y�X��m���ȏW�v | |
 |
 |
| ��M�����@�ɂ��ĔV�L�q�͂قƂ�ǂȂ��B��|���g�K���鋳�t���C�X�E�t���C�X�́u�A���J���ŃC�G�Y�X��m���ȏW�v�ɗ��邵������܂���B�i�s���j�����ّ��j�L��u���Ӂv��� | |
�@
 |
�ł́A�R���̓V��t�֓o��܂��傤�B�o�R���[�g�͂T�ʂ肠��܂��B
|
�o�R�����[�g�} |
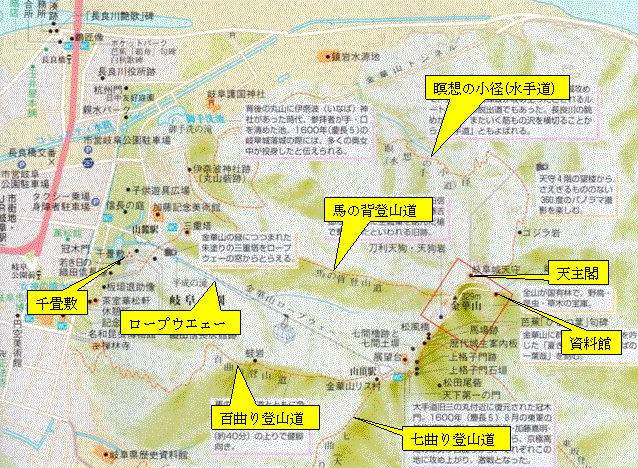 |
|
�P�D���؎R���[�v�E�F�[�i�Г�600�~�j�@�@�@�@�@�@�@�@ |
���[�v�E�F�[�œo��Ɓu�S�Ȃ�o�R���v�Ɓu���Ȃ�o�R���v�̘e�֏o�܂��B
|
�S�ȓo�R�� |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�S�ȓo�R�� �@�S�Ȃ���̖��ɂ��ނ��ʋ�\��܂�̎R���łƂ��̃��[�g�ɔ�ׂčŒZ�R�[�X��30�����炢�̃��[�g�ł��B �@�������r����13�����̓������܂����A���ǐ��s�X�n���]���ł��A���߂��ǂ����w���ȏ�̓o�R�ɓK���܂��B |
|
���Ȃ�o�R�� |
| �@�@�@�@�@�@�@���Ȃ�o�R�� �@���v���Ԃ͂S�O�����炢�A�N�_�̓h���C�u�E�F�[�[�z���u�ł��B �@���w���ł��y�X�Ɠo�R�ł��郋�[�g�ŁA�����Ă̑�蓹�Œʏ�̓o�铹�ł����B |
�R���ɂ̓��[�v�E�F�[�w����V��փ��[�g�Ɂu�V�����̖�v�u��i�q��Ձv
�u�n��Ձv�u�V���i�Z�\��j�v�Ə��ɂ��ǂ�܂��B
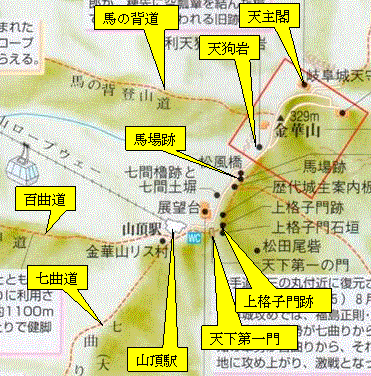 |
| �@ |
�R���֒����ƍŏ��ɖڂɓ���̂��u�V�����̖�v�ŋ��O�̊ەt�߂ɕ������ꂽ���ؖ�ł��B
|
�V�����̖� |
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�����̖� �@�i�\�\�N�㌎�����A��t�R����U�ߗ��Ƃ����D�c�M���́A�����ɔ�����������Z���ɖ{�����ڂ����B �@��t�R�̏�s���Č�����ƂƂ��ɏ鉺���̈�m�����Ɖ������A�y�s�y���̌p����F�߂�Ȃǔ��Z���̔ɉh��}�����B �@�܂��M���́u�V���z���v�̎���p���A�邪�V������֓��ݏo����ƂȂ����B �@�M���̑�u���]���Ă����Ɋ��i���ނ肫�j������āA���̈̋Ƃ�`����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�s�j |
|
��i�q��Ί_ |
|
�@�@�@�@�փ���������O����̊�U�߂̌���n |
�X�ɐi�ނƏ�i�q��Ղ֏o�܂��B
|
��i�q��� |
| �@�@�@�@�@�@�@�@��i�q��� �@�鉺�̑��傩��}��ȑ�蓹�i���ȓ��j������Ă��������Ɂu��i�q��v�������Ă����B �@���i�E��j�ɑ傫�Ȋ��A���i�E��j�ɂ͐藧������ǂ����т������A�����Ɏ��ԘE���z����Ă����v�Q�̏ꏊ�ł���B �@�փ�������̑O����ƂȂ����c���ܔN�i�P�U�O�O�j������\�O���̊�U����ł́A�U�ߓo���ė������R�̕���������̌R���Ɗ��D�c�G�M�R�̏������A���̖���߂����Č�����������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�s�j |
|
���c���Ԑ� |
 |
| �@���c���i�܂����j�Ԃ́A��i�q��i��������������j���瓌�ɉ�������������ɒz����A�킸���ȕ��R�n���R�i�ɂȂ��Ă���B �@���̍Ԃ̂ق��A�ێR�ԁE��t�R�ԁE�����i����j�R�ԁE�������i������イ���j���Ȃǂ��A���؎R�̔������l�������ł߂āA�R�[�̋��勏�قƂƂ��ɁA��̗v�lj��Ɉ�������Ă����B |
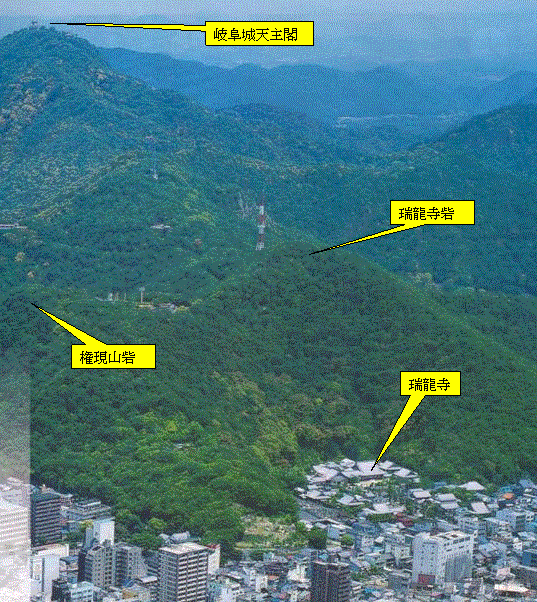 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������� |
|
�n��� |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n��� �@��̊s���ł͗B��̕��R�ȓy�n�ŏ�i�q�傩�畝�R�� �i�T�D�S���j�A�����R�O�ԁi�T�S���j�����Ă���B �@���\�N�ԂƐ��肳����G�}�́u�n��Ձv�Ɉʒu���Ă���B �@��ɋl�߂Ă����������n���q���ł����ꏊ�Ƃ��A��n�̌P�����������Ƃ������Ă���B �@����ɂ͔n��ł͂Ȃ����ł���Ƃ������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�s�j |
�u�n��Ձv���߂���Ƃ��悢��V��t�����n�߂܂��B
 |
|
���w�ٔ��s�u������䂭�E��v�̊�n�}���� |
|
腖��� |
|
���ڒ� |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�˂̗R�� �@��͐ē����O�ȗ��A�D�c�M���E�r�c�����E�D�c�G�M�ȂNJ����p�Y�̋��S�̒n�Ƃ��đ����̐�v�҂��o���Ă���̂ł���܂��B �@�����̗���Ԃ߂邽�߂��̂��납�炩�����̐M�҂ɂ���āA�얳���@�@�،o�̂���ڔ肪���Ă�ꂽ�̂ł���܂��B �@�i��ɂ͌����N��͏����Ă���܂���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�s�j |
|
|
�V��t���ŏ��̐�i�|�C���g�͂��̂�����ł� |
 |
|
�ē����O�摜 |
|
�{�ۍ� |
|
��̊ۋ� |
���؎R�R���̊�ɂ͏�̓쐼�ɌR�p��˂��l���邻���ł��B
���̈�����̖{�ۈ�˂ł��B���̈�˂̒J�̕��ɂ������˂�����܂��B
|
��̈�� |
 |
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�یR�p��� |
|
|
�{�ۓ� |
��̎l�̌R�p��˂̂�����̖{�ۈ�˂Ƃ��̒J���̈�˂̑��ɁA���̋��������O�ڂ̈�˂ł��B
|
�R�p��� |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̈�ˁi�������j �@�N���͈�H���������؎R�ł͉J���Ɗ�̊Ԃ���͂��ɂ��݂ł鐅�𗭂߂��˂����Ɍ@�킵�Ă���B �@��̊ۂ�����Ő����ɂR�����A�����ɂP�����̈�˂�����B �@���̈�˂́A��̊ۂ̐��Ɉʒu����R�p��˂Łu�������v�Ɩ��t�����Ă���B �@�i�s�j |
|
��������˂���V��������r���ɔn�̔w���̉����������B
|
�n�̔w���@����� |
| �@�����Ă͋}���̎��ɗ��p����Ă������ŁA�R�O���ʼn��܂ʼn�����邪�}���z�Ō��r�p�ł��� |
�V��̑O���߂���Ԗk�ɂ��鉺�蓹�ʼnƑ������̓��ł��邪�A���͈����߂��z�̓��Ƃ͎v���܂���B
|
�ґz�̓��@����� |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�߂��z�̏��a�i���݂��j�i�Ƒ������j �i�K�̍����牺��܂��j�@ �@�������牺��̂�̂́A���̎蓹�Ƃ����܂����B �@�r���Ɉꕔ�ɓ�͂���܂����A���ǐ�̐�����]�ނ��Ƃ��ł��钭�]�̗ǂ��o�R���ŁA�R�E�S�O���Ŋ����O�d���t�߂։������̂ł߂��z�̏��a�Ƃ��ēo�R�҂ɐe���܂�Ă��܂��B �@�c���ܔN�i�P�U�O�O�j�����փ�������̑O����̎��A���R�̐�N�E�r�c�P���R���U�߂̓o���Ă����̂����̐��̎蓹�Ƃ����Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�s�E�X�ъǗ����j |
|
|
�r�c�P���̝|�� |
| �V���\��N�i�P�T�W�S�j���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���[���@�r�c�P���|���i���D�����v���J�j �@�@�@�|�@�@�@�@�@���[ ��A�c�s��z���V�y�A�������Ҕς��� �@�@�@�ւ��炷�A�䒬���������Ƌ� �@�@�@�����ނ鎖 ��A�y�s�y���V��A���������ւ��� ��A���������E�T�S�E���܁E���_�E���s�ԔV�g�s�� �@�@�@���A�t�w��E���E��~�̎� �@�E���X�A���ߒ�~���A��L��� �@���ҁA���|�ȎҖ�A���@�� �@�@�@�@�@�V���E�� �@�@�@�@�@�@�@�@�����@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���q��сi�r�c�P���j�ԉ� �@�V���\�N�i�P�T�W�Q�j�Z������A�D�c�M���͖��q���G�̖d���ɂ�苞�s�̖{�\���œ������A���D�c�M���i�M�����j�j�������ɂ����Č��G�R�ɍU�߂��ē������܂����B |
 |
|
�@�@�@�@�@�吳���N�̏�猩���� |
 |
|
|
���a�R�O�N�i�P�X�T�T�j�n�����w���̏W�c�o�R�̎��̐Ί_ |
�����̐Ί_ |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V��̐Ί_ �@�݂邩��ɑf�p�Ȏ��R�ł���B �@�������ɕ������ꂽ��̓g�^���������������A�Ί_�͐M������̈ӎu�����̂܂g���ς݂Ȃ����ꂽ�B �@���̋M�d�ȐΊ_��ۑ����邽�߁A���a�̍Č����ɂ́A�S�R���N���[�g��̏d�ʂ͊�Ղ����ׂĈ��������A�Ί_�ɂ͂����������S��������Ȃ��悤�ɍH�v����Ă���B |
|
|
��̗���� |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̗��j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���q����͍Ԃ��� ���m���N�i1201�N�j ��K���s���i�ɂ����ǂ��䂫�܂��j�����؎R�̏������z�����̂��n�܂�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������i���Ƃ��Ƃ��݂@��K���s���̏����j�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɉ���@�i�����݂ނ� ���������̎q)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��t�����i���Ȃ݂����@�ɉ���@�̒�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��t���[�i���Ȃ݂ӂ��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��K���s���i�ɂ����ǂ��䂫�ӂ��@�s���̑��̎q�j�̌�A�p��ƂȂ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y���R���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�]�ˎ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������� �@�������A���̖͋[����I��Q�N�O�ɕ��Q�҂̎��ɂ��Ď��������A��ǂ��v�킵���Ȃ����퐶�����ꂵ���Ȃ�A�s���͖�A�R���������グ����x�ł����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a���� |
�V���ڂ̑O�ɂ��čX�ɓV��߂Â��܂��B
| �@�@�@�@�@�M���̓V���z���ւ̊K�i �����Ԃ�����Z�� �@��t�R�鐪���̂X�N�O�A�I�{�ꏬ�Z�i�����j��Ɉē����������̓��̈Ɋ�R�ɓo�����M���́A�R�����牓�߁i���������j�̍����R�߂āu�A�������q�R��A��t�R��v�Ə�@���������Ƃ����B�@�M���Q�T�̂Ƃ��ł���B �@���ꂩ��T�N��ɂ͏��q�R�ɐV���z�����B �@�M���̂���Ȃ閲�́A��t�R�i���؎R�j�Ɍ������čL�������B �@�����ĉi�\�\�N�i�P�T�U�V�j�A���Ɉ�t�R��𗎂����B �@�R�S�ɂ��Ă悤�₭�O��̔��Z���蒆�ɂ����߂��̂��B ��m��������u�v�� �@�M���͒����ɐV�������z���A�����ɊƂ����V��������^���A�V�����s�s�����݂��悤�Ƃ����B �@�y�s�y���̐��D���������A���R�ŕ����ȏ��H������ۏ����B �@�����āA���̐V�����o�ϐ���ɕ��s���āA�M���̂���܂Łu�فv�̉ԉ��ɑウ�āA�u�V���z���v�̈�͂��g���悤�ɂȂ�B �@���̂S�����ɂ́A���ƂȂ����M���ɂƂ��āA����ɖ��m�ɂȂ��Ă������������O���\������Ă���B �@����͋����̗̓y�x�z�Ȃǂł͂Ȃ��A���Ƃ��Ίy�s�y�������S�Ɏ����������E�A�V���������ɂ���ē��ꂳ�ꂽ���E���A��Ђ炱���Ƃ�����̂������B �@���̂��߂́u�V���z���v�ł������B �u�V����v�����̐� �@�M���́A�݂�����̗��z���ے�����A���́u�V���v�Ƃ������t���D�B �@���̍D�݂���肢�ꂽ�̂��u�V����v�����̐��������B �@�ł��D�ꂽ�Z�\�҂Ɣ��肵���E�l�Ɂu�V����v�̏̍���^���āA�Z�\�̔��B�����サ���̂ł���B �@�V����̊����A�V����̏���A�V����̋���蓙�X���y�o�����B �@�������߁u�l�ԍ���v�̐��Ƃ����ׂ����̂ŁA���V�̋C�ɂ��ӂꂽ�鉺�̟u���i����j�Ԃ肪���̂��A�씲�ȕ�������ł������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���w�فu������s�����邩��j�@ |
�Ō�ɓV���ւ̊K�i���オ��܂��B
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�鋳�t�t���C�X�̊s�� �@�i�\�\��N�i�P�T�U�X�j�A�C�G�Y�X��̎i�ՁA�|���g�K���̐鋳�t���C�X�E�t���C�X��s�́A���K�˂��B �@���̂Ƃ��t���C�X�������̂́A�l�X���Z�����ɍs�������̏鉺�ŁA���̓��킢�́u�o�r�����̍��G�v���v�킹���Ƃ����B �@�o�r�����́A�����Đ��E�����̒��S�Ƃ��ĉh�������\�|�^�~�A�̌Ñ�s�s�ł���B �@���؎R�[�̐M�����قɓ����ꂽ�t���C�X�́A����ȐΊ_��u����̂��Ƃ���Ȃ�Ɖ��v �ɋ������A�u�N���^�̖��{�v�̂悤�ȕ��G�ȍ\���ƁA����ȍ��~�Ɏ^�Q�B �@�X�ɊՐÂȒ������Ɋ�������A�S�w�̓W�]�䂩�璬��]�������B �@���N�A�������̐M���ɉy�����Ēm���Ă����t���C�X�́A���炽�߂Ď��R�ȕz���̕ۏ���B �@�����āA�M��������ē�����Ƃ����̂ŁA�؍݂��Q����������B �@�������J�̒��A�钆�Ńt���C�X�ƂQ�`�R���Ԓk�b�𑱂����M���́A��p�����ɐ��E�̍��X�̓�����K���ɂ��Ď��₵�A��قǖ��������̂��A�݂�����H�V���^��ł��ĂȂ����B �@�V�������Ղ��t���C�X�ɁA�M���́u�`�����ڂ��ʂ悤�A�^�������Ɏ��悤�Ɂv�ƒ��������Ƃ����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���w�فu������s�����邩��j�@ |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̗R�� �@���q����̌��m���N�i�P�Q�O�P�j�A���{�̎����E��K���R���s�����R���ړI�̂��߂ɂ����ɏ��߂čԂ�z�����Ɠ`�����Ă��邪�A��t�R��Ƃ��ē��{�j�ɑ傫���o�ꂵ�Ă���̂͐ē����O�ȍ~�̂��Ƃł��B �@�ē����O�͓V���i�Ă�Ԃ�j���N�i�P�T�R�X�j�Ɉ�t�R����C�z���ē��邵�A�����Ďq�̋`���A���̗��������ɂȂ�܂����B �@�i�\�\�N�i�P�T�U�V�j�D�c�M���͐ē������Ɛ���Ĉ�t�R��𗎂��A�㌎�V���Ƃ��ē��ꂵ�܂����B �@�M���͈�t�R�����Ɖ��߁A�y�s�y����ی삵�A�u�V���z���v�̎���p����ȂǓV������̖{���n�Ƃ��܂����B �@�i�\�\��N��鋳�t���C�X�E�t���C�X�����K��A���̑s�킳�ɋ��������Ƃ����ȂɋL���Ė{���|���g�K���֑���A���m�ɂ܂Ŋ�̂��Ƃ��m����悤�ɂȂ�܂����B �@���̌�A�D�c�M���E�_�ːM�F�E�r�c�����E�r�c�P���E�L�b�G�������ƂȂ�܂������A�c���ܔN�i�P�U�O�O�j������\�O�����E�D�c�M�G�i�M���̑��j�͐��R�̖L�b���ɖ������ē��R�̓�����Ɛ킢�A���������E�r�c�P���ɍU�߂��ĊJ�邵�܂����B �@�c���Z�N�A��͔p��ƂȂ�V��t�E�E�Ȃǂ͎���ĉ��[��Ɉڒz����]�ˎ���ɂ͋��؎R���ɓV�傪���Ă��邱�Ƃ͂���܂���ł����B �@����S�R�N�i�P�X�P�O�j���Nj��̔p�ނ𗘗p���y�،��z�g�����A�ؑ��̖͋[�邪���Ă��܂������A���a�P�W�N�i�P�X�S�R�j���Q�҂̎��ɂ��Ď����܂����B �@���̌�A�ό��̃V���{���Ƃ��āA�܂����y���R����̉ؗ�ȏ�s���Č��������Ƃ����s���̔M�ӂƏ���ɂ�菺�a�R�P�N�Ɍ��݂̎O�w�l�K�̓V��t���Č����܂����B �@������N����C�H�����s���A�D�c�M���̍��̑s��ȓV��t�̎p���Č����܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�s�j |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̗���� �P�A��K���s���i���v�N�s�ځj �@���q����O���̊��q���{�����B�@��K�����̑c�B �@���͓�����Ɨ��̍s���B��͔M�c�_�{�i�G�̖͂��Ƃ����B �@�s���͌������ɑ�������d���A���q���{�̕����Ƃ��Ė����ɎQ�悷��B �@�������������i�������ɐ������܂�ǂ���j���J�݂���ƁA�s���͌�������l�ƂȂ�A���Ő����߂ƂȂ�B �@�ȍ~ ��K�����͑�X���������Ƃ��Ė��{�̍������������ǂ��邱�ƂɂȂ�B �@�������`�o�E�t��̉�����Ȃ��߂邽�߉i�����̌����肷��ƁA���v�i���イ�j��N�i�P�P�X�P�j�s���͂��̑��c��s�ɔC������B �@�܂��A�s���́A���m��N�i�P�Q�O�P�j�Ɉ�t�R�ɍԂ�z���A���s�ւ̉������Ƃ���B �@�s���̈��́A�֓�������Z�̂ق������E�o�H�E�x�́E�ɐ��ɋy�сA����E���|�E�ɗ\�E�F���Ȃǂɂ������Ƃ��Ĕɉh�����B �Q�A���������i�Ƃ��݂j�i���v�s�ځj |
|
 |
|
|
���������ɕ������ꂽ��@�@�i���W���摜����j |
|
|
�V��t���̓W���i |
|
| �V��t�S�w����̒��] | |
|
�@��V��t��蒷�ǐ��]�� |
 |
 |
|
���j�I�ɂ͂U������� |
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�闎�镨�� �J��O��̔��Z ��֔��� ��֍U�� |
�@�@�@�@�@�@���������]�R�ɑ������킯 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�키�O���������� |
|
�������Ԃ̐퓬�i���݂̐������̗��R�j �@��\�O���ߑO�Z�����A���K���A��������A��ɒ����R�͍U�����J�n���܂����B �@�ԑ��̕���������B������U�߂����K���R���ܐ��B �@����̖��A�ߑO�\���ɂ͍Ԃ͗����킢�͏I���܂����B
���Ȍ��̐퓬�i���݂̊�����������j �@�������A�����A�א�A�����̓��R���͈͂��|�I�ɑ����A�u�S�Ȍ��v�u��i�q��v�u��̊ۖ�v�Ǝ��X�Ɣj���A�Ō�ɖ{�ۂ܂Œǂ��߂��Ă��܂��܂����B |
|
�{�ۂ̕�����P���o�� �����ďG�M�������̊O�֎P���o���č~���̋��߂܂����B�i�����͎P���o�����Ƃɂ���āu�~���v�Ƃ��������ł��j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����R�Əx�͒� |
|
�D�c�G�M�A�㊥�\��ŏo�� ���̌�u�G�M�v�͍���R�œ�\�Z�܂ʼn߂������Q���������ł��B �ؑ]���˔j�i�n�́j����A����������̐킢������ |
�@
 |
|
| �@�@�@�@�@�@�u���E���A�a�f�[�v�Ńu���[�̃��C�g�A�b�v �@2008�N11��14���̍��A����߂��u���E���A�a�v�̃e�[�}�J���[�ɍ��킹����u���[�Ƀ��C�g�A�b�v���ꂽ�B �@300mm�̖]�������Y�Ŏ���������Ԃ̂��߃u�����傫���B��Ȃ����������V���̎ʐ^���ؗp���܂����B |
|
|
�鎑���� |
|
�����Ă̊�̉Ζ�ɂ������Ƃ����Ă��܂��B |
����́u�߂��z�̓��v���i�F���悭�����ǂ��̂ł������߂ł��B
|
�ґz�̓��Ɣn�̔w���̏o���� |
| �����߂��܂ʼn����Ă����n�_�Ō��r�����́u�n�̔w���v�ƍ������܂��B | |
���̍����_�Ɉɓޔg�_�АՁi�ێR�ԐՁj�ƉG�X�q�₪����܂��B
|
�ɓޔg�_�А� |
| �@�@
�ɓޔg�_�Ћ��ցE�G�X�q�� �@�ɓޔg�_�Ђ̎�_�́A�i�s�V���̌Z�E�\���~���F���i���ɂ�������Ђ��݂̂��Ɓj�ŁA���E�ɂ�����A��a�O�g�̐_��̊Ǘ������Ă������A���̐E���ق����i�݂��Ɓj�ɏ���A�ӔN��t�R�[�i���؎R�j�̊ێR�ɋ��Z���ꂽ�Ƃ����A���̈Г����Âт��̒n���J���Ă������A�V�����N�i�P�T�R�X�j�ē����O����t�R������Ƃ���ɂ�����A����_�Ђ����ɂ����Ă͂ƈɓޔg�_�Ђ��ێR���ɓޔg�ʂ̍��̒n�Ɉڂ����B �����r �@�ێR�̖k�ʂ̐^���ɐ_�ЂɌw�ł鎞�Ɏ�������Ƃ����r������A�����r�Ƃ����B �@�c���ܔN�̊闎��̍ہA�����������̒r�ɐg�𓊂����Ɠ`�����Ă���B �G�X�q��̂����v �@�_�АՂɂ���G�X�q�̌`��������́A���ǐ�̐��ɁA�_�l�̉G�X�q�����Ԃ����₪����ł��邢���l������A�_�l�̊�����̂܂܂ɂ��Ă����̂͂��������Ȃ��ƁA��ɓ���|���āA�ێR�Ɉ����グ���B �@����ƁA�₪����ł��ƐG��������l�́A���̎������ύK���ɕ�炵���Ƃ��������`����������܂��B �i�s�j |
�ێR����[�ցu�߂��z�̓��v������Ɛ���~�̎�O�ɎO�d��������܂��B
|
�O�d�� |
|
�������i���㒷�Nj��j�̌ÍނŌ��Ă�ꂽ�O�d�� |
|
�����͂Q�S�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�吳�V�c���ʋL�O |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ݒn�̑I��̗R���Ɛ썇�ʓ��� |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�҂͓�����勳�� �@�v�����̂́A�����鍑�勳���̈ɓ��������i�P�W�U�V�`�P�X�T�S�j�ŁA�����_�{�i���s�s�j��z�n�{�莛�i�����s������j���肪���A������a�l�ܒ��ł͂Ȃ����{�ŗL�̗l���̔��W��ڎw���Ă����B �@�W�҂́u�����͖@�����̒��̗l���̓M���V���_�a�ɗR������Ɠ˂��~�߂��l�ō������z�w���w�Ԋw�������_���������ߊɗ��邭�炢���v�Ɛ������Ă��邻���ł��B�i�����V���E�ߍx�ł��j |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�������i���㒷�Nj��j�̌Íނ𗘗p���O�d�� �@���̌��ނɂ��P�i�������������ƒ����Ȃ����z���i�j�̐Ղ��c���Ă��蒷�Nj��̌Íނ̏ł�����܂��B �@�����̒��Nj��͖������N�i�P�W�V�S�j�ɑ���ꂽ����̖؋��Łu�������v�ƌĂ�Ă��܂����B�@ �@�u�������v�ȑO�͖ؑ��œ�݂���r���܂ł������͖����A�r������k�݂܂ł͑D��12�z�Ȃ�����ɖؔ�n�����D���Ŗ��Ԃ̌��݂ŗL���������������ł��B �@���́u�������v�����ڂɉ˂��ւ����鎞�̌Íނ𗘗p�����Ɠ`�����Ă��܂��B�i�����V���E�ߍx�ł��j |
�܂������ɂ͖��a���������ق�����܂��B
 |
 |
�܂��Ă̊��Ԃ͒��ǐ�ʼnL���������Ȃ��Ă��܂��B
 |
|
�@ |
���łŁu����ӂ̏隬�v�Ƃ��Ċs�i���[�隬�E���K�隬�E���X�隬�E��R�隬�E����隬�E
�㈩���隬�E���隬�E�����隬�̂W�隬�j�e�����s�i�ɖ؎R�隬�E�L���隬�̂Q�隬�j�A�֎s�i�֏隬�̂P�隬�j�A
���Z���Ύs�i�����隬�̂P�隬�j�A�H���S�i�����隬�E���q�隬�̂Q�隬�A���ΌS�i����c�隬�E
����i����݁j�隬�̂Q�隬�j�ȂǂP�U�隬�Ɗ����͍��R�s�i���R�隬�E��R�隬�E���q�隬�j�A
�S��s�i�S�㔪����j�A���Ð�s�i�c�؏隬�j�A���Q�s�i�߃P�隬�E�����隬�j�A�b�ߌS�i�⑺�隬�E���q�隬�j�A
�{���S�i�k���隬�j�̂P��E�X�隬�����ē����܂��i���ݐ��쒆�j
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̗p��R����
����i�Ђ炶��j�F�@���n�ɒz���ꂽ��s�B�@�����Ƃ̊W���d������A�z��ɂ������ẮA�鉺���v�����@�@�@�@�@�@���܂�ł���B�@�R���E�����E�o�ς̋��_�Ƃ��āA�z�`�Ȃǂ����Ȃ����B |
�f�o�r�ʒu���͖ڕW���̑���ʒu���������\�̒��S�łȂ����H����H��̂ɕ�����₷���A
���ԏ�A�����A���ւȂǂ̏ꍇ������܂��B���̑��̏���2002�N���Ɍ��n�Ŋm�F�������̂ł��̂ŁA
���̌�A���H�g���Ȃǂɂ��ړ]��s����������@�ɂ��s���������Ŏs�������̕ύX������̂�
���̌�̏��ł��m�F���������B
�V���o�[�̏�s��Ղ̎U�����u����ӂ̏�Ə隬�v