|
|
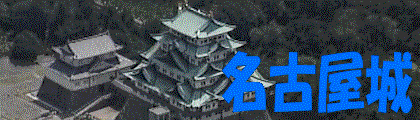 |
�z��� �F ����ƍN�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �z��N�� �F �c���P�T�N�@�@�@�@�@�@�@�@ ���ݒn �F ���É��s����{�ۂP�|�P |
�V���o�[�̏�s��Ղ̎U�����u�������É���v
|
|
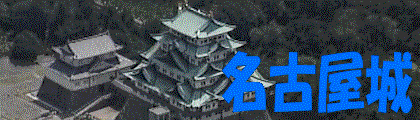 |
�z��� �F ����ƍN�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �z��N�� �F �c���P�T�N�@�@�@�@�@�@�@�@ ���ݒn �F ���É��s����{�ۂP�|�P |
���̃V���`�z�R�ŗL���Ȗ��É���͑�2�����E���̋�P�ŏĎ����܂�����
���̌�A�吨�̎s���Q���ɂ��Č�����܂���
���݂͖�R�N�A�H����v�͉��ׂT�T�W���l
�ւ����̐킢�łقړV����������ƍN�ł������A���܂�����ɂ͖L�b�G�g�̈⎙�G�������܂����B
�����œV������Ƃ��邽�߁A�����̖h�q���_�Ƃ��邽�߂ɂ��̒n���É���
�P�U�O�X�N�i�c���P�S�N�j�z��ɒ���B�P�U�P�Q�N�i�c���P�V�N�j�ɏ�����������܂����B
����

���y�Y�V���b�v
��P�ŏĎ������E�C�[�����ɂ��o�W���ꂽ���͎c�[�ō��ꂽ���̒���
���W������Ă��܂��B

|
�s�u�摜���� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�ȏ�̉f���͂s�u�ŕ��f���ꂽ���̂���f�ڂ��܂����B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@
|
������ |
|
�Z�\�ꖜ�@�����˂̋��� |
��V��ɂ͋����͂�����܂���

�@
|
���@�� |
���Ẳ|����i���̂�������j�ՁA�����ɂȂ��ċ��]�ˏ�̘@�r����ڂ��A
���É�������̐���Ƃ�������ЂŏĎ��B
1959�N�ɍČ����ꂽ�����P�Q���A2�K���Ă̓S�R���N���[�g��
����ɂ͖���̓����v������܂�
�@
|
����̖� |
|
�����\�Z���[�g���A�����蔪���[�g���z��ȑO���玩��������Z�S�N�ȏ�ƌ����Ă��܂��B ����ˎ哿��`�������֏o�w�̂Ƃ��A���̎���V�ɐ���A |
����̓W�]�K�ȊO�͂̓J�����֎~�ł��̂ŁA�p���t���b�g�̉摜�ŏ���̖͗l���Љ�
�@
|
��P��Ƃ�ꂽ |
|
�P�U�P�T�N�i���a��N�j�Ɋ��������{�ی�a���P�X�S�T�N�̋�P�ŏĎ��������ꕔ�̉���˂͑a�J���Ă��薳���ł����B |
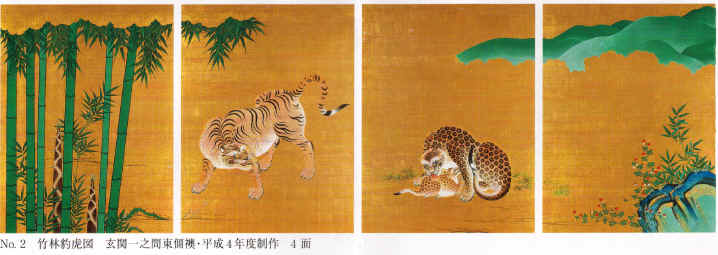

 |
|
 |
 |
| �@ | |
�@
|
�V��t |
|
��V��͂T�w�i�V�K�n���P�K�j |
| �V�K�̍ŏ�K�����͎B�e��������Ă��܂��B | |
| ��V��̊e�K�͗��j�~���[�W�A�� ���܂��܂Ȏ����╜���͌^���W������Ă��܂��B �n�K�F���V���`�̌����͌^�A��������˖͌^ �R�K�F�u�鉺���̂ɂ��킢�v�u����ł̐����v �S�E�T�K�F�u���É���̗��j�v�Ȃǂ��Љ��Ă��܂��B |
|
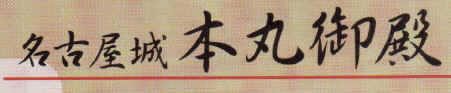

�@
|
�{�ی�a�� |
|
�����v�� |


| �@ | �@ |
 |
 |
|
�Ď��O�̖{�ی�a���� |
�Ď��O�̏㗌�a |


�@
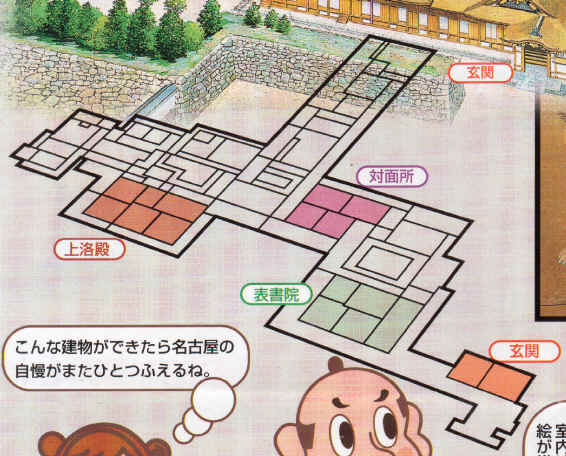
 |
 |
|
���� |
�㗌�a |
 |
|
| �㗌�a�i�䐬���@�j�@�@��i�V�� | |
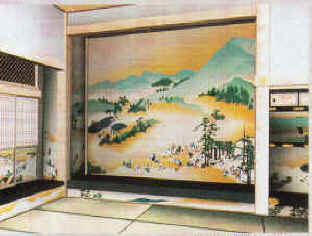 |
 |
| �Ζʏ��@��i�V�� | �\���@�@��i�V�� |
�j�V�ی�a�Ɣ\�������P�ŏĎ�
�@
|
�����ˎ�̐܂��ݒ��� |
|
�ˎ�E����c���i�悵���j |
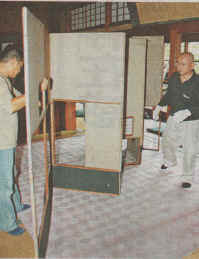 |
 |
| �����`���R�ȁ@ �����Ɍc�������点���Ƃ����������܂��ݎ������u��ț����v���A�������� ���É��s����ߌÖ��̌c�h���ł��̂قǑg�ݗ��Ă�ꂽ�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �y���Ɏ������a������̛������J���ƁA�݂�I�⏰�̊ԂȂǂ̒�����p�̂��炦���U�����ӓI�ɂ���o���A��ԏo���G�{�Ȃ�ʔ�яo�������������ł��B |
|
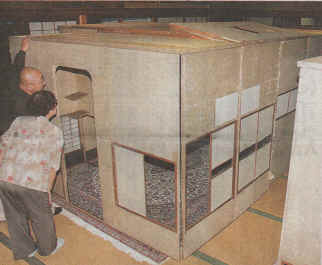 |
�@
|
�\��V�� |
|
�]�ˎ���@�d�� |
| �@ | �@ |
 |
 |
| �@ | �@ |
�@
| �@ | �@ |
�@
|
������E |
|
�]�ˎ���@�d�� |
|
|
�@
|
�����̐Ήg�� |
|
���̏�ɒt�����ׂ͂点�A�C�����ە�������������B |
�@
|
�ˌP��`�̔� |
|
���̔�̈ʒu�͓�V�ی�a�Ղł���B |
| �@ | |
�@
|
���t�����V��� |
|
�c���l�N�i�P�W�U�W�N�j������\���A��V�ی�a�����~�̒�O�Ŕ�������Ƃ̎O�d�b���a��A |
| �����t�����̔ߌ� �P�W�U�W�N�i�c���l�N�j�A���H�����̐킢����A�����̔����ˎ哿��c���̂��Ƃ� �Ď@�̋g�c�m�s�����É����ԋ{�O�L����̖��������Q���܂����B ����ɂ��A�c���h�}篔����֖߂�A�����h�̏d�b�ȂǂP�S�l���a���B |
|
�@
�@
|
���@�@�� |

�@
|
�ߌÖ��� |
|
��V�ے뉀�̓�[�ɂ���܂��B |
�@
�@
|
��V�ۓ�� |
|
��V�ے뉀�͓ߌÖ��Ô�̖k���ɂ���܂��B |
| �c�N����̐D�c�M������������ �ߑ㖼�É���͐퍑���̓ߌÖ�邪�x�[�X�ɂȂ��Ă��܂��B �����Ă��̓ߌÖ��́A�M���̕��M�G�̏�ƂȂ�O�A���쎁�̏�ł܂���܂����B |
|
|
������ |
|
�z��`���ɂ͔������������ŁA�]�ˏ�ɂ͎����̔�����������܂����B |
| �x��̓y�������S�̕�͂V�Γ�l�}�� ��傪����Ă��p�ӂ���E�o�̌x��ɓ������������ŁA���̑��݂͉B����Ă��܂����B �����Q�N�̑吭��҂̂����l�̓��S���~����E�т̉��Ă�����ƂɕԔ[����܂������A �Ȃ�����ȉ��Ă��������m�̉��~�ɂ������̂��A���ɒm��l�����Ȃ����������ł��B |
|
 |
 |
| �x�̉����������ēy�����i�ǂ�����������ԁj���S���~�� ���݂͖��߂��Ă��܂��������`�̘g�g�i�Ԃ����j�̓������ʘH�ƂȂ��Ă��āA ��������x�̉��ɉ���邱�Ƃ��o���������ł��B |
|
�@
|
��������S�C���� |
| ��������i�ΊD�E�ԓy�E�����������āA������ ������H�@�j�Ōł߂�ꂽ���łȗ������A��̊� �k�[�̐Ί_�̏�Ɏc���Ă��܂��B �~�`�̓S�C���Ԃ��J���Ă��܂��B |
 |
�@
|
���k���E |
|
�����@�]�ˎ���@�d�v������ |
 |
| ���F��̌Íނ��p�����Ă���Ƃ����Ă��܂��B |
�@
�@
|
�Ί_�̍��� |
 |
|
�g���u������ |
|
�@
|
����V�ۓ���V�� |
|
�����@�]�ˎ���@�d�v������ |
| ���m���̈�ٌ��݂Ŏז��ɂȂ�ڒz ���̖�́A���S��Ƃ����A���͓�̊ۂ̓���̊ہi�O��j�Ƃ��Č����Ă������A ��̊ۂɈ��m�̈�ق����݂���ɂ������̈ڒz���ꂽ�B �`���͍����Ŗ{�������A�����́A����h��U�߂Œ��E���E���Ȃǂ͑ѓS��ł��t���Ă��܂��B |
|
 |
 |
|
���ɂ͂T��ނ̋��������t���ēG����������Ă��܂��B |
|
|
������ |
| �`�������� ���j�V���������Ɩڂ̑O�ɂ������ȐΑg�݂��ڂɓ���܂��B �u�����v�Ƃ����A�z��ɓ������Ė{�ۂ����������ِ������^�Γ`�����Ă��܂��B �\�ʂ��猩���傫���͏c�Q���]��A���U���قǁA���s�����s���Ȃ̂ŏd�ʂ͕s���ł���B |
|
�@
|
����V��� |

 |
|
��V��Ə��V����e�V��̒n�K���u���x�v����Ō��A�����V��`���ł��B |
| �@ | |
�x���ɂ͑哹�|�̔�I������܂��B
| �@ | |
�@
|
������E |
 |
| �����@�]�ˎ���@�d�v������ �u�C���i���݁j�E�v�Ƃ������A�O�ς͂Q�w�A�����͂R�w�B ���ꉮ����A�{�������ŁA�Q�K�Ɂu�Η��Ƃ��v������܂��B �S���͒z�铖���̂��̂Ƃ����u����v������܂��B |
|
�@
|
���ցE�Ԋ�E��L�� |
�@
|
�\��V��� |
| �\��V��� �{�ےǎ�i���j�e�`�i�l�����Ń}�X�̂悤�Ɉ͂�����G�ɍU�ߍ��܂�Ă� �l������U���ł���悤�Ȍ`�̖h��`���j�̎��ł���B |
|

|
���n�o�� |
| ���n�o�� ���n�o�Ɛ��V�ۂƂ̊Ԃ̖x�̐Ղ̎��ō��͓y��̋��ƂȂ��Ă���B |
|

�����̔p��߂ɂ����̈Зe���c�������É���ł�����
��Q�����E���̋�P�ő�V��E���V��E�{�ی�a�ȂǑ�����
�M�d�Ȍ����������܂����B
���݂͖x���܂߂��悻�Q�S���u���s���̌e���̏�Ƃ��ē�����Ă��܂�
|
���É���O�V�ۂ��� ���É��s����ۂ̓��@���Ƌ{ |
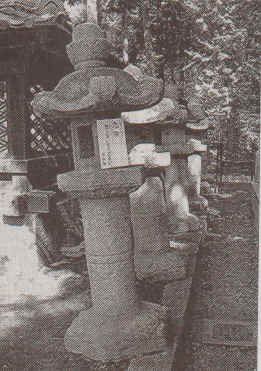 |
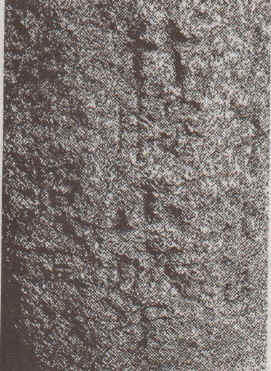 |
| �d�b��[�Q�X��Ђ�������@ ���Ƌ{�����ɂ���t�����U�ƌĂ��Q�X��̓��U�͖����̏��߁A���É��� ����ڒz����A���̌��Ђɂ��������݂Ђ�����Ƃ�������ł��܂��B�@�@�@�@�@�@ ���̓��U�̑����́u���a�܌Ȗ��N ��� ���Ƒ匠�� ���O �l���\�����v�Ȃǂ� ���܂�Ă��܂��B�@���݂̓��Ƌ{�͓���ƍN�̖v��O�N�A���̗���J�邽�ߖ��É���O�V�ۂɑn������A���̎������˂̏d�b��������[������Q�ƌ����� �@���̖��V�|���́A�t�ƘV�߂��|���Ɓi�O���j�̏���i���M�j�ŏd�b�i���o�[�Q�B�@�M���̐����Ɓi�O���ܐ�A���R���j���j�u���������q��v�̖�������B�@�����̓��U�Q�̈ꕔ�͌X���댯�ȏ�Ԃł��� (�����V�����j |
|
�@
| �@�@�@�@�@�@�@�@��̗p��R�����i�E�̎�ށj
�����E�i�͂Ȃ݂₮��j�F�@������s�Ƃ́A�퓬���ړI�̍\�z���ł���B�@���������̐w���I���A���@�@�@�@�@�a�Ȏ���ɓ���ƁA��͐퓬�ʂ������ς��d��悤�ɕω������B�@�����ŕ�����ړI�Ƃ���@�@�@�@�@�ȗցi�����j�⌚�����o�Ă���悤�ɂȂ����B |
�f�o�r�ʒu���͖ڕW���̑���ʒu���������\�̒��S�łȂ����H����H��̂ɕ�����₷���A
���ԏ�A�����A���ւȂǂ̏ꍇ������܂��B���̑��̏���2002�N���Ɍ��n�Ŋm�F�������̂ł��̂ŁA
���̌�A���H�g���Ȃǂɂ��ړ]��s����������@�ɂ��s�����������s�������̕ύX������̂�
���̌�̏��ł��m�F���������B
�V���o�[�̏�s��Ղ̎U�����u�������É���v