
|
�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_����ӂ̏隬�P�O�v�i�s�j�S�j�̏隬�����^���܂����B

|
�@
|
�ŋ߂̒n���j���[�X����lj��b�� |
���̃y�[�W�ŏЉ��隬�̈ꗗ�\
|
�s�j�S(���䒬��փP����) �s�����P�P�ӏ��̏隬���Љ�܂��B |
|
�s�j�S |
115.�I������i���䒬�I���j�A115-1.���]�䕔���e�w���i���䒬�I���j�A 115-2.���������w���i���䒬�I���j�A115-3.�I���Õ��i���䒬�I���j�A 116.������i���䒬�����j�A 116-1.�������b���w���i���䒬�{���j�A116-2.�ї��G���w���i���䒬�{��j�A 117.���������~���i���䒬���j118.�{�������i�i���䒬�{���j�A 119.���e���������i�i���䒬���j�A119-1.���_���i���䒬���j�A 119-2.��̂悤�Ȍ䉮�~�i���䒬���j�A120.���R�����i�i���䒬���j�A 121.�|�������q�w���i���䒬���j�A121-1.�ܖ���א_���i���䒬���j�A 121-2.�|�������q�̕�̂����P��i���䒬���j�A 122.�ʏ����i���܂��傤���փ������ʁj�A122-1.�ʉΖ�ɐ��i�փ������ʁj 123.�R�������i�փ��� ���R���j�A 123-1.����䥎R����Ղւ̂�����̓o����i�փ��� ���j 124.���{�����i�փ��������{�����j�A125.�����R�����i�փ��������{���a���j�B |
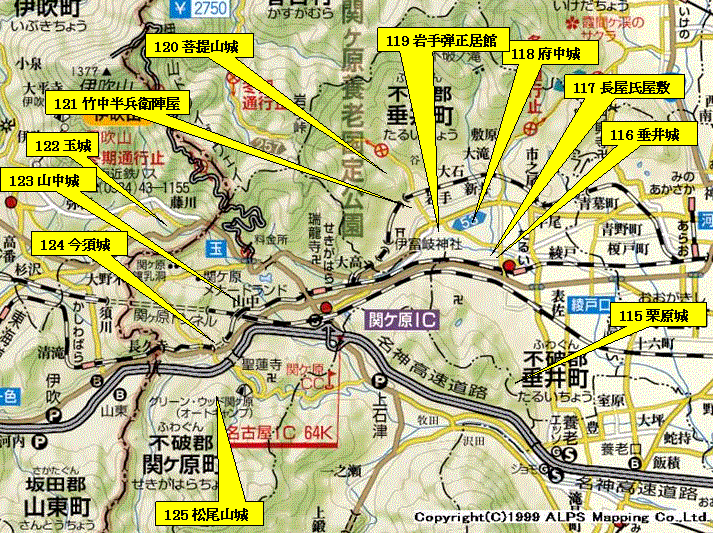 |
|
�@
|
115.�I���隬 ���s�j�S���䒬�I�� |
|
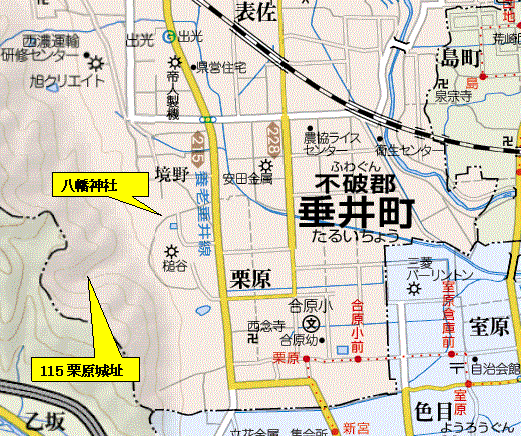 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I���隬 �@�����Q�P�����̋{��M���������Q�P�T�����ɓ����R������A����̔����_�ЂɁu��\��V�E�A���̃T�J�L�v�̈ē�������܂��@�����ŎԂ̕��͓k���ʼnE��ׂ̍��⓹���R�O�O���قǓo��܂��B �@�����Œ��]�䕔���e�w�̐����̂Ƃ���Ɏ���܂��B��������A���̃T�J�L�E��\��V�̈ē��ɏ]���o��܂��B�P�T���قǂŋ�\��V�ՂɎ���A��������T���ŘA���̃T�J�L�Ɏ���܂��B |
|
�ڈ� |
|
���]�䕔���e�w��(�R��)��|�������q���̒n(�I���隬)(�R�O��)� |
|
�y�����ԂȂ����܂����A���ł̒��ԏꂪ�S�z�ł��B |
|
����������(�ē�������S��) |
|
�r���v���v���Ɉē�������܂��B |
|
�I����\��V�� |
|
|
|
��\��V�Ղ���X�ɏ�֓o��܂��B |
|
�S���قǓo��ƉE��Ɂu�I���A���̃T�J�L�v�������Ă��܂��B |
|
�I���A���̃T�J�L |
|
�|�������q��(�B����)�� |
�@
|
115-1.���]�䕔���e�w�� �s�j�S���䒬����I�� |
|
|
���]�䕔���e�w�� |
�@
|
115-2.�������Ɛw�� �s�j�S���䒬����I�� |
|
|
�I���隬��T���Ă��Ė������L��̎R���ɂ��ꂢ�ȍ�����������܂����B |
|
|
���̍L��ɒ����Ɛ��w�Ղ�����܂����B |
|
|
�L��̋��ɂ͋������_�Ђ�����܂����B |
|
|
|
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
���� �@���� �����i�Ȃ� �܂������^�Ȃ��� �܂������j�́A���y���R����̊����E�喼�ł���A�L�b�����̌ܕ�s�̈�l�ł��� �@���ߒO�H���G�Ɏd�������A�V��13�N�i1585�j�ɖL�b�G�g�̕���O�ɔ��F����A�O�H�����匸����������ƖL�b�����Q�̉Ɛb�ɂȂ����B �@�����Z�p�\�͂��č��������ɒS���A�L�b���̑����n�̊Ǘ��⑾�}���n�̎��{�ɓ��������B �@��B�̖��E���c���̖��E���\�E�c���̖��̍ۂɂ́A���ƕ�s�Ƃ��ĕ��Ƃ̗A���Ɋ����B �@���\4�N�i1595�j�ɋߍ]����5����q�̂��i�̂����������12���j�A�ܕ�s�̖��Ȃɖ���A�˂�B �@�c��5�N�i1600�j�ɎO����ƂƂ��ɖї��P����i�����ċ�������B �@��͋��s�O�����ŎN����A���Y�͒r�c���g�ɒD��ꂽ�Ƃ��� |
|
�@
|
115-3.�I���Õ� �s�j�S���䒬����I�� |
|
|
���䒬�w��j�� |
|
���̌Õ����u�I���隬�v��T���Ė������I���n��̂ǂ����ł� |
�@
|
116.����隬 �s�j�S���䒬����@�� |
|
| �@ |
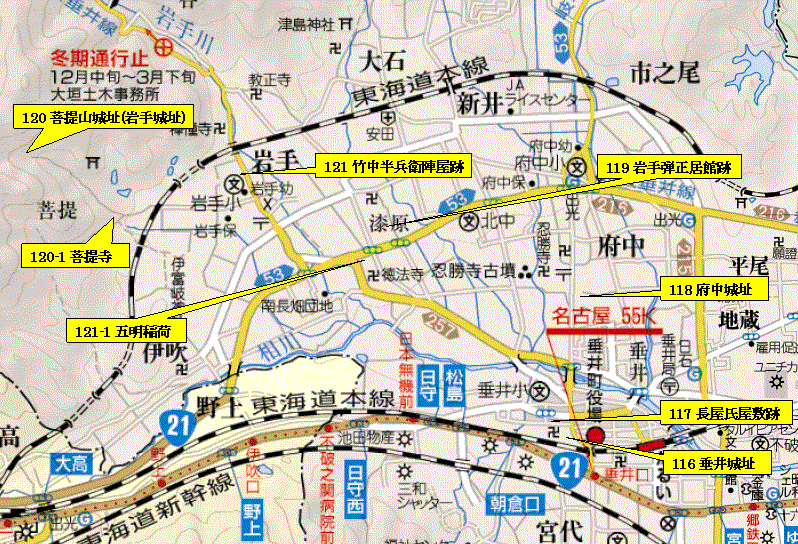 |
|
����隬 |
 |
 |
|
�u�����v�̂������ꐸ�� |
|
�ꐸ���R���̒��ԏ�Ɂu�����Ք�v������܂��B |
|
�@
 |
|
���ˈL�Ɛ����Ր���n |
�u�������b���w�Ձv�Ɓu�ї��G���w�Ձv�͐��䒬�{��̓�{�_�Ђ̌�_�̂̓�{�R�̘[�ƎR���ɂ���܂��B
|
116-1.�������b���w�� �s�j�S���䒬����{�� |
|
|
��{�R�o�R ��{�_�Ђɂ��Ắu |
|
|
�փ�������̎����������b���w�Ղ��֗��r�̉�������܂��B
|
�������b���w�� |
|
�������b�� |
�������b���w�Ղ̂����߂��Ɏs�n���i���������܁j��_���K������܂��B
|
�s�n����_ |
| �s�n���i���������܁j��_ �fᵖ��ƓV�Ƒ�_���A�V���͂Ő�����������ɉ��������_�l�ŁA���ɍւ����_�ł��B �Ȃ��������J���Ă��邩�͕�����܂���B |
�s�n����_���߂����ӂ肩��R���ƂȂ�܂��B
�Q�O���قǓo��ƓW�]��֓������܂��B
|
116-2.�ї��G���w�� �s�j�S���䒬����{�� |
|
|
|
|
�W�]��ɂ͖]����������i�����j���É��w�O�̃r���Q�� |
 |
|
�ї��G���w�� |
|
�@�@�@�@�@�@���̐w�`�}������Ɠ���ƍN�͏�����E�g��Ȃǂ̗��肪�Ȃ������犮�S�ɑ܂̃l�Y�~������ |
�@
|
117.���������~�� �s�j�S���䒬���� |
|
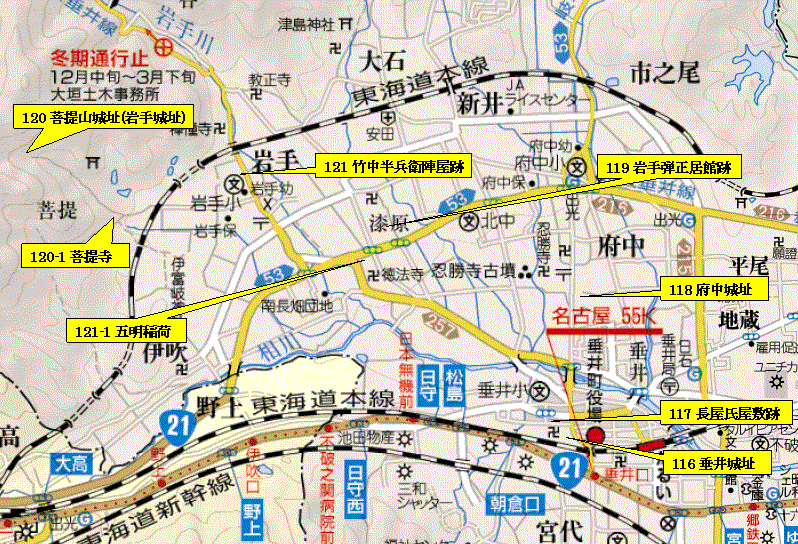 |
|
���������~�� |
|
�Ԃ������p�̕��� |
 |
 |
|
���䏊�ƂȂ������~�� |
 |
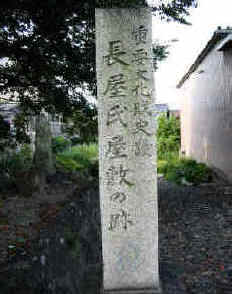 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����L�䂩��̒n |
|
�@
|
118.�{���隬 �s�j�S���䒬�{�� |
|
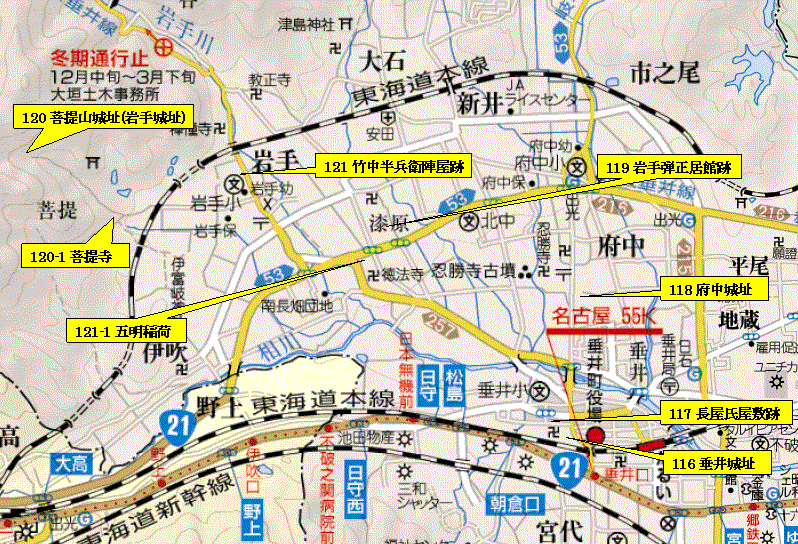 |
|
�u�{���隬�v(������) |
 |
|
�{���邪�������Ƃ��������� |
|
���Z���{�K�Ղ̔肪���̊p�Ɍ����Ă��܂��B |
|
|
|
���{�鐄�� |
�@
|
119.���e�������� �s�j�S���䒬��� |
|
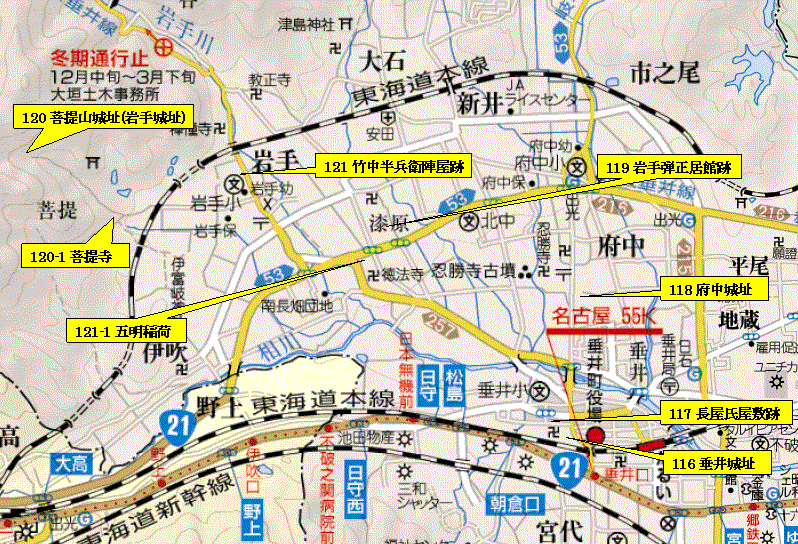 |
| �@ |
 |
|
�����ӂ�Ɍ����鉓���̖����̂���ꏊ�ł��B |
|
�ِՂɂ͏����ȎЂ������܂��B |
|
�Ԃŗ������́u�����W��v�ɒ��Ԃ����Ă��������ēk���Ŋٚ��܂ōs����邱�Ƃ������߂��܂��B |
|
�ȑO�܂ł����������������ʂĂ��P�{�����c���ė����Ă��܂��B |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����_�Ќ䉏�N �@���̌�A���e�����l�Y�����o�Ċ��e�����l�Y���q���̎���ɂ́A���n��̖k�ɘZ���N�̍Ό����₵�Č��ݒn�ɒ�������u���_�Ёv���ڒz���c����܂����B(��ɏЉ�܂�) |
|
|
�V��15�N(1544)�܂��͉i�\���N(1559)�i�\�Q�N���ɒ|���d�������R�ɍԂ��\������e����ǂ��A���R���z�����Ƃ����Ă���B
�@
|
119-1.���_�� �s�j�S���䒬����� |
|
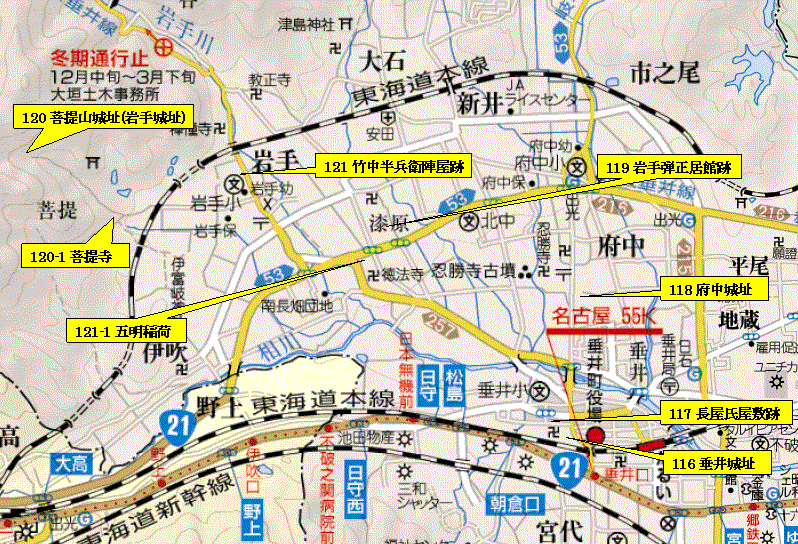 |
|
|
|
���_�� |
�@
|
119-2.���̂悤���䉮�~ �s�j�S���䒬����� |
|
|
�\������h�ł�������������� |
�@
|
120.���R�隬 �s�j�S���䒬����� |
|
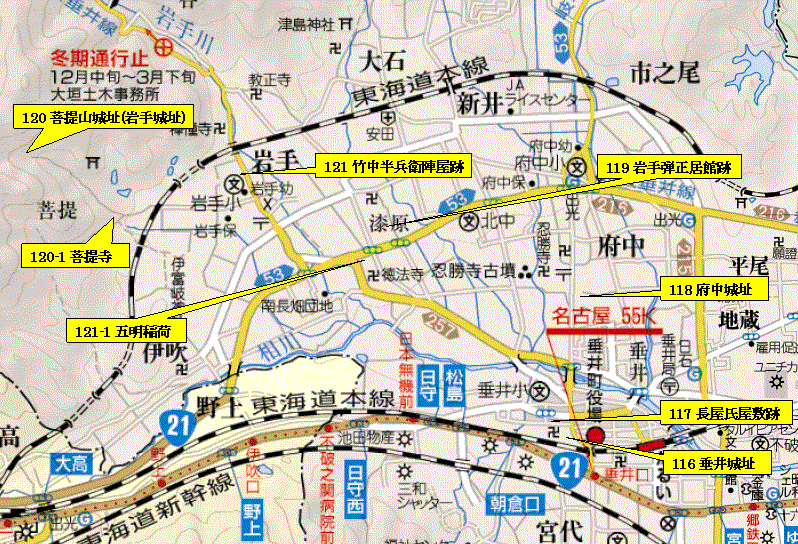 |
|
���R�� |
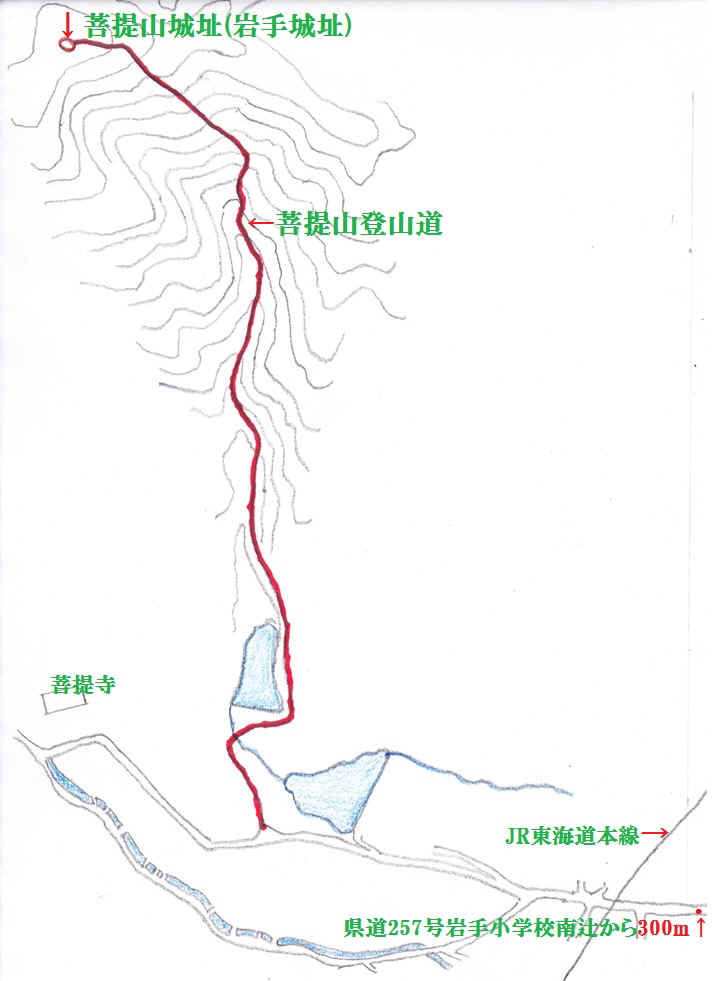 |
|
���ԃX�y�[�X�̋߂����u���R�隬�n�C�L���O�R�[�X�v�o�R���K�i������܂��B |
|
 |
 |
|
�ŋ߂͌F�ɒ��� |
|
|
|
|
| �@���R��̓꒣��́A�R�����Ɏ�s��u���A��Ɍ����ē�̋ȗցE�O�̋ȗցA�쑤�ɏo�ۂ�z�u���Ă���B�@ �@��s�Ռ������ɂ͎O�����x�Ɠy�ۂ��n�o�A�����Ğe�`�Ռ����`�����A�X�Ɉ�i�����������ɂ���䏊�ȗւƂ��A�g�������G�ȓ꒣��ƂȂ��Ă���B �@��x���u�Ăē쑤�ɂ���o�ۂ́A��[�ɓy�ۂ�z���A�X�ɐ؊݉��ɂ͒G�x�Ɩx��g�ݍ��킹���h�����ł߂Ă���A��x�� |
|
| �@���R��́A�i�\�Q�N�ɒ|���d���ɂ���Ēz���ꂽ�B�@�|�����͗K��S��䓰���ō֓����Ɏd���Ă������A�i�\���N�Ɋ�莽���̊��e����łڂ��Ċ��ɋ����ڂ��Ă��B�@ �@�i�\�R�N�ɏd�����v���A���̎q�d�������ƂȂ�B�@���̏d�����H�ďG�g�̌R�t�Ƃ��ėL���ɂȂ����B�@�d���́A�V���V�N���d���O�؏��U�߂̐w���ɂĕa�v�����B |
�@
|
120-1.��� �s�j�S���䒬��莚��� |
|
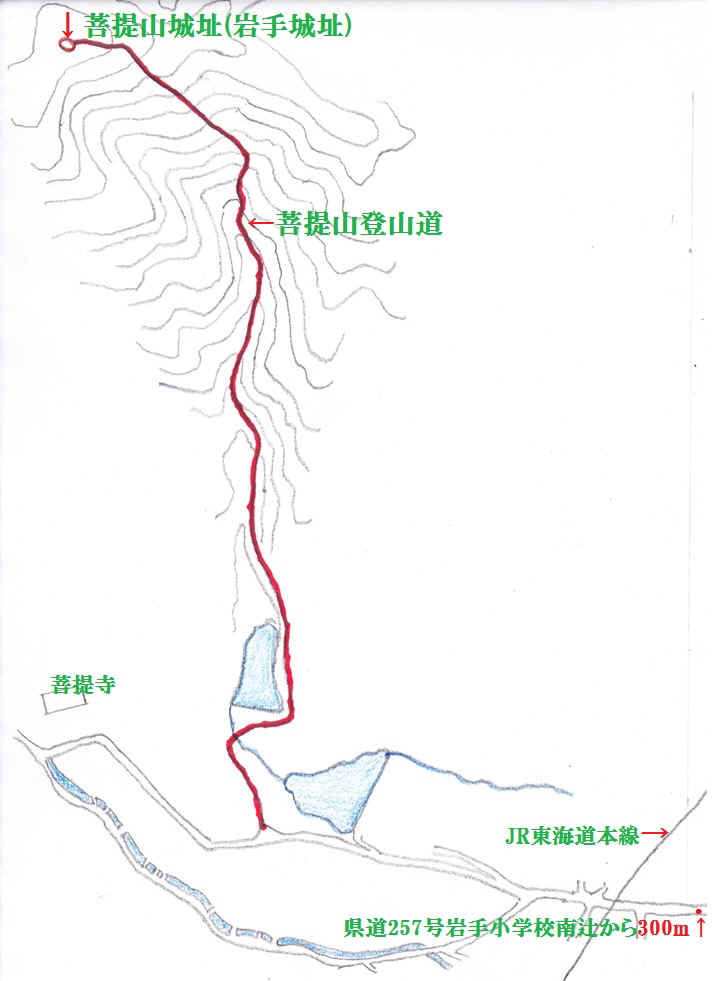 |
|
�ԂłQ��قlj�������ǂꂪ�u��v��������Ȃ������B |
�@
|
121.�|�����w���� �s�j�S���䒬��莚�쌴�i�����j |
|
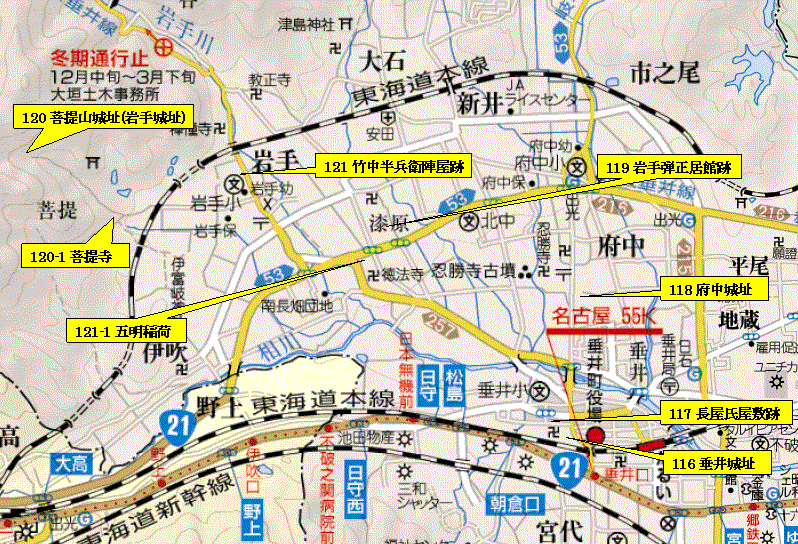 |
|
|
|
�|�������q�w���� |
|
�|�����w�����y�јE�� |
|
�|�������q�d�� |
|
|
|
�����q���̒m���A�\����� |
|
���̍��V����_���Ă����D�c�M�����A���̕�����Z���̔�����^��������ŁA���̏�̏��n��\�����ꂽ���A |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�g�Ɣ����q�� �@�G�g�͗ՏI�ɗՂ݂��̎���Ƃ��u�E�����������ɂ��ƂȂ炸�v�ƒQ���߂��ƌ����Ă��܂��B �@�u�|�������q�d��v�v��A���j�u�d��v�i���Ⴍ�Ȃ�A�������ǁj�͊փ����̖��ɂ� |
�@
|
121-1.�ܖ���� �s�j�S���䒬��� |
|
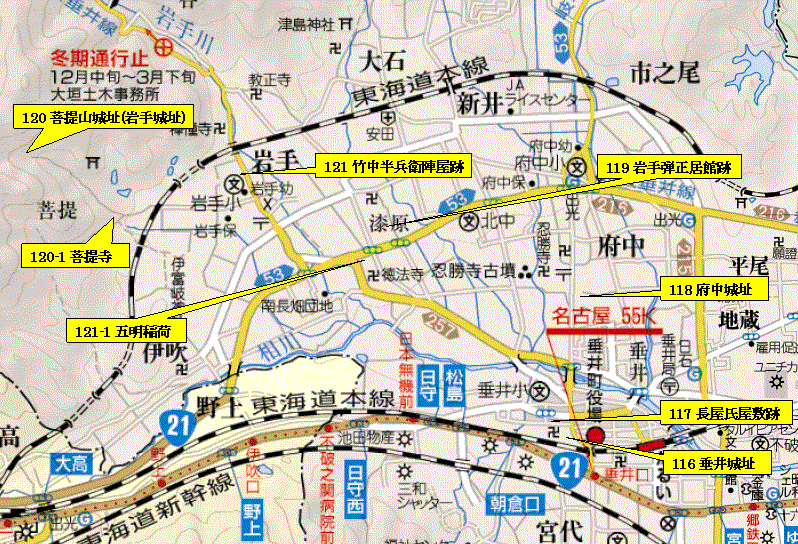 |
|
�ܖ���א_�� �@�@�V���Z�N(�P�T�V�W)�����|�������q�����O�؏�U�����A�ے×L�����r�ؑ��d�͐D�c�M���ɔ�����|�����B �@�܂��A�|�������q�w���ՁA���R�隬�Ȃǂ��f�ڂ��Ă���܂��̂ŁA�������������B |
 |
|
�D�c�M���ƍ��c�����q�ƒ|�������q�� |
|
�ܖ���� |
�@
|
121-2.�|�������q�̕�̂��� �s�j�S���䒬����� |
|
 |
|
�|�������q�̕�̂����P� |
 |
| �@�@�@�@�@�d�B�i���Ɍ��j�O�ɂ������|�������q�̕���ڂ� �@���̎��́A�����O�N�i1494�j�F�����i���������j����̐������ׁi�������傤�����j�a�����J�n���܂����B �@�V�����N�i�P�T�V�X�j�d�B�i���Ɍ��j�O�̐w�ŕa�����܂������A�����̕�́A�O�ɂ�������j�d������ڑ��������̂ł��B |
 |
 |
| �@���݂̖{���́A�����q�̑��A�d����������O�N�i�P�U�U�R�j�Ɍ����������̂ŁA���w��G��u�|�������q���v������܂��B | |
 |
 |
 |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�������q�d���̕� |
|
|
������̓o��� |
�@
|
122.��(����)�隬 ���s�j�S�փ������� |
|
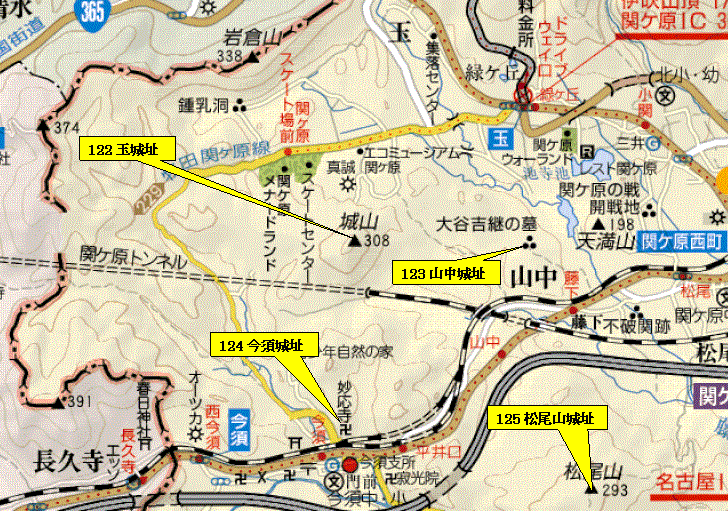
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��R���ʏ隬 |
 |
|
�ʏ隬 |
|
�����R�U�T�����́u���v�M���Ō����Q�Q�X�����ɓ���܂��B |
|
�q���g |
|
�R�̕����P�O�O���قǓ���ƉE���Ɂu��R�R���U�O�O���v�̕W��������܂��B |
|
|
|
���͓o��₷������܂ł��Q�O���͊y�ɏオ��܂��B |
|
��R�i�ʏ隬�j |
�@
|
122-1.�ʂ̉Ζ�ɐ� ���s�j�S�փ������� |
|
|
�펞���͒N�����m���Ă�R�̒��閧�ꏊ�ł����B |
|
�ʂ̉Ζ�ɐ� |
|
|
|
���R���Y |
�@
|
123.�R���隬 ���s�j�S�փ������R�� |
|
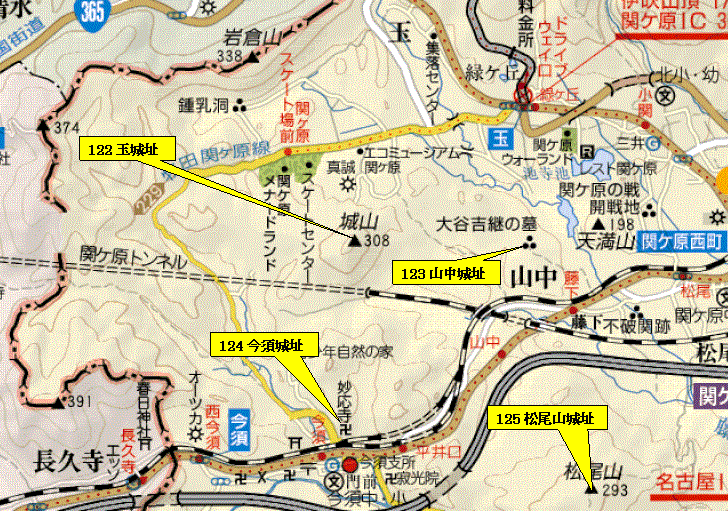 |
|
�R���隬
|
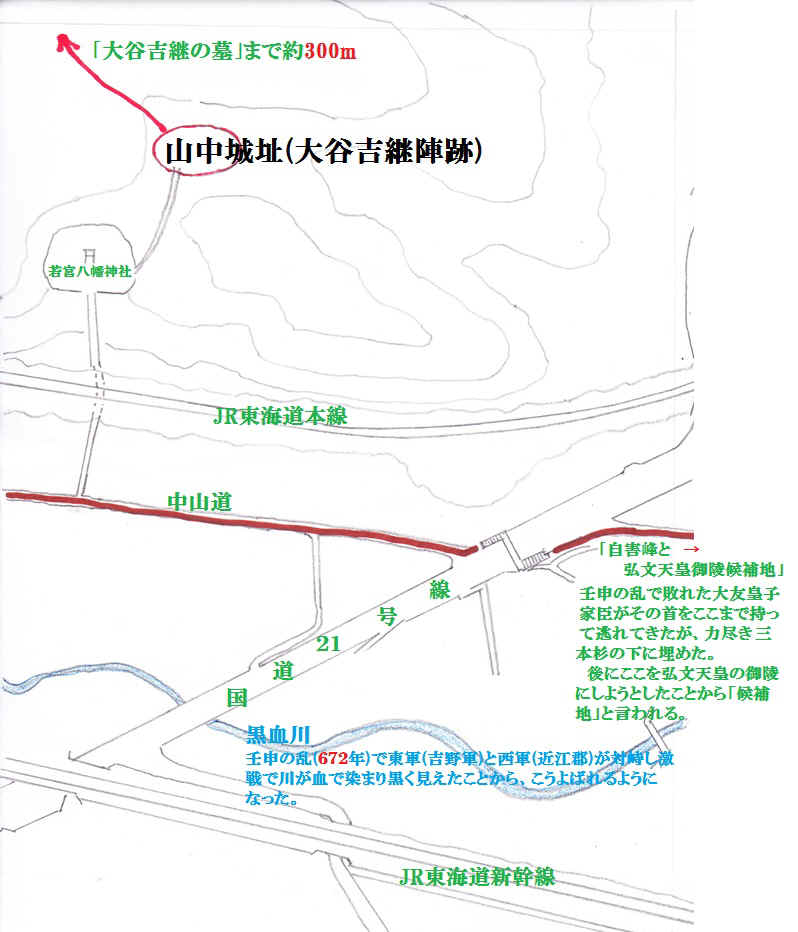 |
|
�ߋ��ƌ���Z���̒n�u�R���隬�v |
 |
 |
|
�@�@�@�@���R���������낷�v�Q�̒n�A�R���� |
|
���̕��͐�قǂ̒��R���̎�{�����{����̕����߂��Ċy�ł��B
������̓o����͎Ԃ̕��������̊W�Ŋy�ł��B
|
123-1.������̓o�������� �s�j�S�փ����� |
|
|
�����(��J�g�p�̕�o���) |
���̈ē�����R��(����)����܂�
|
�ē��̂Ƃ�����S�T�O��10���Łu��J�g�p�̕�v�֒����܂��B |
|
���j��
��J�g�p(�g��)�� |
|
����Ō����Ă����u���������̕�v�͉��̊ԊW������̂��傤�H �@�փ����̍���ɂ����āA���R������G�H�̗�����@�m���Ă�����J�g�p�͂��炩���ߏ�����R���z�w���Ă��������R�Ɍ����ĕ���z�����Ă���A�����삪����Ɣz�����Ă��������ŏ�����R�������Ԃ����Ƃɐ������܂����A ����Łu������̕�v�̗��R���G���́u�����Ɓv��������Ă����R��������܂����B |
���͑�J�g�p�w�Ղ������܂��B(�R�O�O��4��)
��J�g�p�w���֗��܂����B
��J�g�p�w�Ղ̉��ɐV���Ɂu�����R���]�n�v���ł��܂����B
|
�u�����R���]�n�v�̂������ɒ��R��������̓o����ɂ���u��{�����{�v�������܂��B �u�����R���]�n�v |
|
�D�c�M�����ŏ��ɏ��z���������R |
�@
|
124.���{�隬 �s�j�S�փ��������{������ |
|
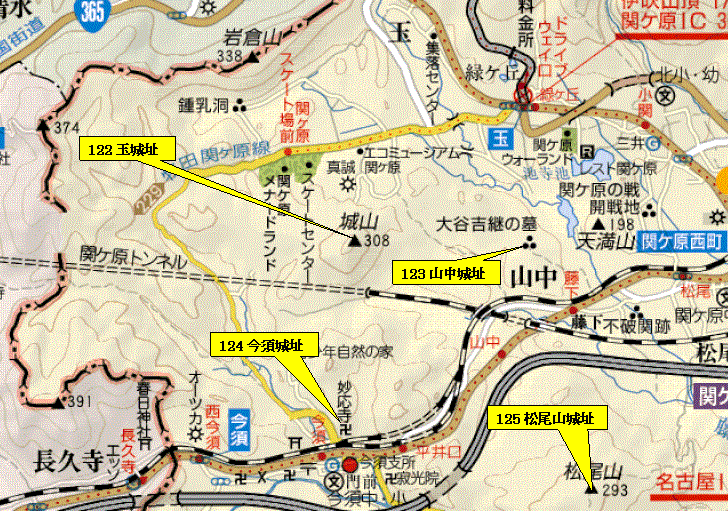 |
|
���{��̓`�� |
 |
|
���{�隬(���䎛) |
 |
 |
|
�u�������v�ւ͂i�q���C���{���̉���ʂ�܂��B |
|
| �R���ɂ͋��a���h�сi���̂ƂƂ�j�N�i1801�N�j�̕���������܂��B | |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�_�_�@�t�̑呫�Ձv |
 |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�������v |
|
 |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���݂鋾�r |
|
| �ŋߋ����̍u�������Ă��܂����B���ւł��傤���H |
���{��Ղ̓�́u�����R�v�R���Ɂu�����R�隬�v�͂���܂��B
�o�����
|
125.�����R�隬 �s�j�S�փ��������{���a�� |
|
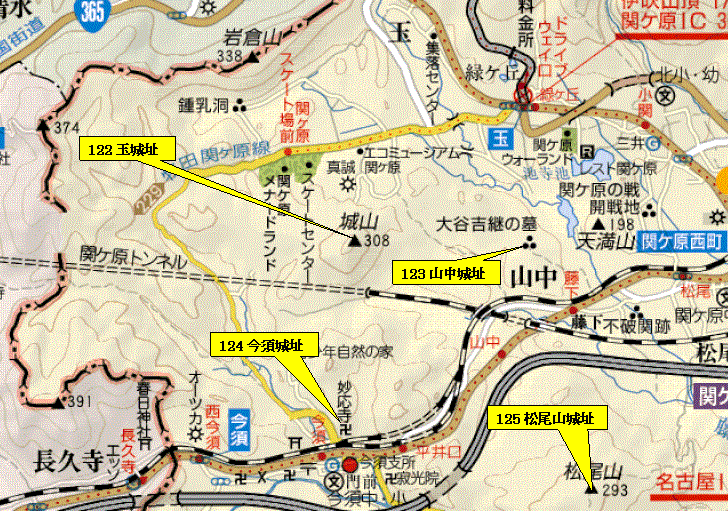 |
|
���{�����������u���䓹�v�ŕ���������P�����قǂ� |
 |
|
�r�������R�R���̓��W������܂� |
���H���R�̘[�܂ōs���P�D�U�����i��S�O���j�ŎR���� |
�R���܂ł�1.5km�i��40���j�R������̌i�F�͐�i�ł��B
|
�R���ɂ͏����R�隬������������Ă��܂��B |
| �@ |  |
|
�����R�隬 �@�����R��́A���Z�E�ߍ]�̗�������]�ł��A�ቺ�ɓ��R���ƈɐ��X���E�k���X�����ʂ���T�^�I�ȋ��ڂ̏�ł��B |
|
�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_����ӂ̏隬�P�O�v�i�s�j�S�j