|
築城者: 築城年代: |
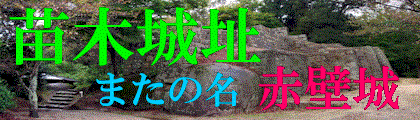 |
所在地 : 岐阜県中津川市苗木 形 式 : 山 城 |
シルバーの城郭城跡の散歩道「苗木城址またの名、赤壁城」
|
築城者: 築城年代: |
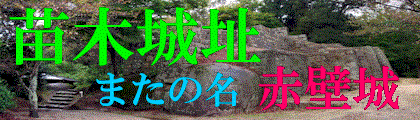 |
所在地 : 岐阜県中津川市苗木 形 式 : 山 城 |
苗木城は、幾度塗り替えても竜にはぎ取られ赤壁が残るという「赤壁伝説」の史跡「赤壁城」、
また、城に危機が迫ると木曽川から霧が一面に立ちあがり、城を隠してしまうという伝説があり「霞城」とも言われる。
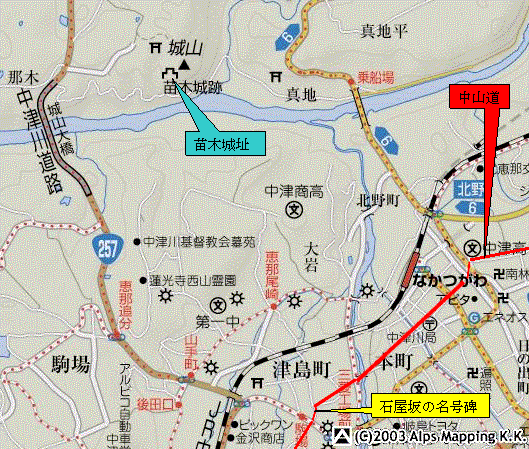 |
|
苗木城跡へは中山道の石屋坂の名号碑の交差点を国道257号線に |
建武年間(1334~38)に、遠山景村が築いたとされています。
本能寺の変後、秀吉派の森長可により落城しましたが、慶長5年(1600)には旧領復活が叶い、
以後12代270年にわたって遠山氏が支配し、一万石ながら明治の廃城まで続きました。
| 国道257号線の有料「城山大橋」料金所を通ります | ゲートを過ぎると「赤壁城(苗木城)の伝説」説明板があります |
| 赤壁城(苗木城)の伝説 苗木城は木曽川のぜんぺきに建てられた立派な城で合った。 白壁が夕日に輝いて綺麗な城であった。 ところがある日耳をつんざくような雷鳴が轟き、激しい雨が降り、昼間であったが夜のように暗くなり木曽川は怒涛さかまき白い牙をむくように荒れ狂った。 まる一日吹き荒れた嵐も治まり城を見ると、驚いた!真っ白であった城の壁が何かで引っかいたような爪のあとで赤くはげてしまっていた。 大勢の左官が集められ修理されたが白い壁になると嵐が来て、また赤くなってしまう。 何度塗り替えても駄目でした。 殿様も城下の人々も白壁に塗ると木曽川から白い色を嫌う竜が来て、かきむしってしまうのだと信じ、それ以降は赤壁に塗り城の東に竜神様を祀り竜神を鎮めました。 それ以来「赤壁城」というようになった。現在も城址東の岩屋に竜神様が祀ってある。 (国道257号線沿いの説明板より) |
|
木曽川に架かる「城山大橋」を渡る途中の上流側に苗木城址がある城山が見えます。 |
|
|
「城址入り口」と「四十八曲り上り口入り口」とは違います |
|
|
| 「四十八曲り上り口入り口」 | ||
| 城山大橋を渡り300mほどに何の目印のない三叉路に看板と木杭があります | ||
三叉路を東へ入り1,300mほど進むと山裾に「四十八曲り道」の標識があります。
|
城坂四十八曲り道 |
|
この道はかなりきついので登るのを止めて、正面の道へ回ることにしました。
| 城址入り口 | |
|
国道257号線を更に北へ150mほど進むと |
城址への途中に「青邨記念館」があります |
|
城への上り口は公園として整備されています |
その奥横には歴代の城主の墓地があります |
| 中津川市指定文化財
史跡 苗木藩士安田太左衛門殉死の跡 苗木領主第5代遠山友由の側近として仕えた安田太左衛門は、29歳の若さで死去した友由の墓前の地にある巨岩上で殉死した。 殉死は幕府によって禁じられていたが、太左衛門の忠誠心と責任感の強さによるものとして問題にならなかった。 (中津川教育委員会) |
|
苗木城跡には建造物は何一つ残っていないが、城跡の規模は1万石に過ぎたるもので、
巨岩と石垣との壮大な組み合わせなどが往時のまま残り、国の史跡に指定されている。
| 更に坂道を登ると城の入り口に差しかかります | |
| 全部で十八の門で固める 苗木城には沢山の「門跡」が残っていて、城下町がある麓から本丸まで、全部で「18の門」がありました。 【①上ノ町門、②風呂屋門、③竹門、④風吹門、⑤北門、⑥駈門、⑦大門、⑧台所門、⑨不明門、⑩清水口門、⑪仕切門、⑫綿蔵門、⑬坂下門、⑭菱櫓門、⑮本丸口門、⑯玄関口門、⑰竹門、⑱大手門】 |
|
史料館裏手の緩やかな登城道を少し行くと、最初に目に入るのが枡形の石垣が残る「風呂屋門跡」です。
| ②風呂屋門跡 | |
| 苗木城の歴史 1-築城年代 苗木城は、天文年間に遠山直廉によって築かれた。 直廉は、岩村城主遠山景友の次男で織田信長の妹を正室としていた。 直廉の娘が後に信長の養女となり武田勝頼に嫁ぎ、勝頼の嫡男信勝を生んでいる。 |
|
風呂屋門跡を固めるように足軽長屋跡、隣接して遠山氏の祈祷所であった龍王院跡がある。
| 足軽長屋跡 石垣に寄って造成された30mほどの広場には、足軽宿泊施設の外、「小頭(ことう)部屋」・「稽古場」等、数棟の建ち並んでいた。 足軽が出仕する場合、最初にこの長屋に立ち寄ることになっていた。(現地説明板より) |
|
| 苗木城の歴史 2-遠山三人衆 元亀3年、直廉が病没すると継嗣なく、信長の命により一族飯羽間城主遠山友勝が城主となった。 苗木遠山氏は、岩村本家と明知城主遠山氏と共に遠山三人衆と呼ばれていた。 武田氏の東美濃侵攻により岩村城が武田氏の拠点となると、苗木城が織田方の苗木城が最前線となった。 |
|
|
龍王院跡 |
|
| 苗木城の歴史 3-本能寺の変後 天正11年、本能寺の変後、金山城主森長可に攻められ落城、遠山友忠・友政父子は徳川家康を頼って落ち延びた。 苗木城は、森氏の領する地となり、その後慶長4年には河尻直次の所領となる。 |
|
 |
風呂屋門跡から三の丸跡へ
風呂屋門跡から竹門跡を経て登城道を行くと三の丸跡に至るが、途中から三の丸跡直下に通じる土塁と空堀が良く残り、土塁の上を歩くこともできる。 |
三の丸跡への入口が風吹門跡。
| ④風吹門跡 | |
|
④風吹門(大手門)跡 |
|
三の丸跡で目を惹くのが大矢倉跡の石垣。
| 大矢倉跡 | |
 |
|
|
大矢倉の土台は天然の巨石と見事に融合された切り込みはぎの石垣が見る者を圧倒する。 |
|
 |
| 大矢倉跡 大矢倉は、外観から二層に見えるが、実際は三階建であった。 一階は三方を石垣で囲われ、倉庫として使われていた。 苗木城最大の櫓建築で、二階、三階の壁には矢狭間(やはざま)が設けられるなど、大手門である風吹門や北側からの防御のために17世紀の中頃に作られた。 (現地説明板より) |
|
大矢倉跡北側に北門跡がある
|
⑤北門跡 |
| 。北門は城の外郭にあった土塀付きの門で、東側に下ると木曽川、北側の道は家臣の屋敷跡に通じている。 |
北門跡脇にある小池は雨水が頼りの貯水池で、馬の飲み水に利用されていた。
三の丸跡東側の駆門(かかりもん)跡には虎口の石垣が残り、眼下の谷とあいまって風情のある佇まいを見せている。
| ⑥駈門(かかりもん) | |
|
駆門は木曽川畔の大手門から三の丸への通用口にあたり、今でも門跡から山麓東側の大手門跡へは「四十八曲り道」と呼ばれる急峻な登城道が続いている。 |
|
三の丸跡から本丸跡へは大門跡から坂下門跡などを経て直進するコースと、二の丸跡から不明門跡などを経て、
本丸跡を取り囲む帯郭跡伝いに迂回しながら登るコースがある。
|
⑦大門跡 |
|
| 苗木城で一番大きな大門は、二階建てで、三の丸と二の丸とを仕切っていた。 門の幅は二間半、二階部分は物置に利用されていた。 領主の江戸参勤出立時などの大きな行事イガは開けず、普段は左側(東側)にある潜り戸を通行していた。 |
|
大門跡を過ぎてすぐ左手にあるのが御朱印蔵跡。
 |
御朱印蔵跡 「切石」で整然と積まれた石垣の上に建てられていた御朱印蔵には、将軍家から与えられた朱印状など重要な文書や刀剣類が納められていた。 |
大門跡から登って行くと綿蔵門跡がある。
 |
⑫綿蔵門跡 本丸へ上る道をさえぎる形で建っていた門で、七ツ時(午後4時)以降は扉が閉められ、本丸には進めなかった。年貢として納められた真綿が門の二階に保管されていたことからこの名がある。 |
本丸跡までは屈折した坂道が続く。綿蔵門跡から登ると坂下門跡で礎石が残る。
|
⑬坂下門跡 |
|
|
さらに登ると菱櫓門跡があり、
|
⑭菱櫓門跡 |
|
|
ここを登りきると巨石を利用した本丸跡の石垣と天守台が見えてくる。
本丸跡への登城道には本丸口門跡があり、その手前に千石井戸が残っている。
|
千石井戸 あまり深くはないが、どんな日照りの時でも水が枯れたことがなく、千人の用を達したという。 |
|
本丸跡 |
|
 |
|
|
苗木城天守建物 |
|
 |
| 二つの巨岩 本丸跡の一角には2つの巨岩からなる天守台が残っているが、このような天守台も珍しい。往時には三層の天守が築かれていたが、今では巨岩の上に柱と梁組みで天守三階部分の床面が部分的に復元され、展望所となっている。 |
 |
 |
別名「霞(かすみ)城」の由来 山頂の本丸跡からの眺望は素晴らしく、眼下に流れる木曽川からの比高差は約170m。 中津川市街と木曽川、さらに恵那山や木曽山系の山並みが一望でき、標高の高さとともに、苗木城がいかに要衝の地に築かれていた山城であったかが実感できる。 苗木城に危機が迫ると木曽川から霧が一面に立ちあがり、城を隠してしまうという伝説があることから「霞城」とも呼ばれている。 |
 |
 |
|
| 馬 洗 岩 天守台跡の南下に大岩があり、馬洗岩と呼ばれている。 絵図には「この石廻り二十三間弐尺」とあり、周囲約45mの花崗岩質の自然石である。 馬洗岩の名の由来は、かつて苗木城が敵に攻められ、敵に水の手を切られた時、この岩の上に馬を乗せ、米にて馬を洗い、水が豊富であるかのように敵を欺いたことから付けられたといわれている。 (説明板から) |
天主台の標高は433m
苗木城は標高433mの高森山に築かれた山城で、山全体は巨岩に覆われ、南麓に流れる木曽川を天然の堀としていた。 |
大門跡の西側が城主の居館や勘定所などがあった二の丸跡で、礎石が一面に広がっている。
 |
| 二の丸跡 二の丸跡の一角に長方形をした的場跡があり、高さ1mほどの的の土塁が残る。 |
二の丸跡から帯郭跡を登って行くと不明門跡がある。
 |
⑨不明門跡 二階建ての門が建てられていたが、普段は締め切られ、忍びの門であったといわれている。 |
さらに登ると清水口門跡へ行く。
|
⑩清水口門跡 |
清水口門跡を過ぎると物見矢倉跡がある。
|
物見矢倉跡 |
物見矢倉跡から登って行くと仕切門跡。
|
⑪仕切門跡 |
仕切門跡から的場跡を経て⑮本丸口門跡まで登城道が続く。
本丸口門跡を過ぎると笠置矢倉跡がある。
|
|
矢倉跡 本丸西側の巨岩の上に建てられていた矢倉跡で、笠置山が正面に見えることからこの名がつく。 |
天守台南下の馬洗岩と呼ばれる大岩が目を惹く。
|
|
馬洗岩 周囲約45mの花崗岩で、苗木城が敵に攻められて水の手を切られた時、この岩の上に馬を乗せて、米で馬を洗い、水が豊富なように敵を欺いたということからこの名がある。 |
馬洗岩の脇は切通しになっており、
|
|
ここを抜けると本丸跡へ上る急な石段があるが、 |
苗木城の歴史 5-慶長5年から明冶の廃城まで続く
慶長5年、西軍に与した河尻直次は改易となり、関ヶ原の戦功により遠山友政が旧領を回復して10,521石を領して入城する。
以後代々遠山氏がこの地を領し、幕末には12代友禄が幕府の若年寄に就任している。
GPS位置情報は目標物の測定位置が建物や遺構の中心でなく道路から辿るのに分かりやすく、
駐車場、鳥居、玄関などの場合もあります。その他の情報も2002年頃に現地で確認したものですので、
その後、道路拡幅などによる移転や行政合併特例法による市町村合併で市町村名の変更があるので
その後の情報でご確認ください。
シルバーの城郭城跡の散歩道「苗木城址またの名、赤壁城」