|
2012.08.13 |
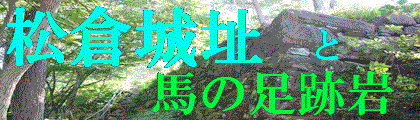 |
岐阜県高山市上岡本町1丁目 |
シルバーの城郭城跡の散歩道「松倉城址と馬の足跡岩」
松倉城址への道は「飛騨の里」から車で山道を1,5km登り峠の広場から徒歩で700mほどの場所にあります
|
飛騨松倉城址 岐阜県高山市上岡本町1丁目590 |
所在地:岐阜県高山市西之一色町松倉山 遺 構:曲輪、石垣 形 式:山城 築城者:三木自綱 築城年代:天正7年 |
高山市「飛騨の里」のテディベア駐車場手前から「松倉城址遊歩道」の石段登口に「史跡・松倉城」説明板があります。
| 史跡松倉城 三木良頼、自綱によって永禄年間(1558)から天正年間中頃(1573)にかけて築かれた。 三木良頼は永禄元年(1558)長子良頼(自綱)を将として天神山城(後の高山城)の高山外記と畑佐城(新宮町)の山田紀伊守を討った。 三木自綱は天正5年(1577)山中城(下岡本町)の岡本豊前守を討ち、白川郷を除く一円を支配し、桜洞(益田郡荻原町)を冬城に松倉城を夏城とした。 松倉城は山城ながら山上の本丸に矢倉、城門を置き標高856.7m、比高360mの松倉山上に巨石を使って、堅固な石垣を築き上げる、戦国末期の山城から一歩前進した雄大な縄張りを持つ城である。 このころ自綱は、越中の佐々成政二通じて秀吉に従わなかったので、天正13年(1585)秀吉は家臣金森長近二命じて是を撃たせた。 自綱は高堂城に迎えて戦ったが破れ、秀綱は松倉城で死守した。 しかし、勇将畑安高が山蔵宗次に討たれ、また藤瀬新蔵が裏切って金森氏に通じ、闇夜に火を放ったので白は落ち、三木氏ここに滅び、以後廃城となった。 『現地説明板より』 |
高山市「飛騨の里」説明板からから車で1kmほど上がると「松倉シンボル公園」があります。
城址へは画面左の石段を登ります。(車でこられた方はここに駐車できます)
|
峠の広場 |
 |
|
登り口に小さな祠がお祀りしてあります。 |
|
数分登ります。 |
石垣の本格的な城郭建築
本丸を中心に土塁でなく、石垣で大手門、二の丸、三の丸を作った本格的な城郭建築であったそうです。
|
道は一本道ですので迷うことはありません。 |
|
堀 切(空堀)
|
500mほど登ると城址の痕跡が現れます |
|
本丸手前から砦跡の石垣が現れます。 |
いくつもの石垣を過ぎると本丸に近づきます。

搦手(からめて)門跡
南石門の跡
本丸跡の広場が見えてきました
|
本丸跡の石垣 |
本丸跡の広場へ出ました。
|
本丸跡には説明版があり見晴らしがよく、城の位置としては絶好の場所と思われます。 |
|
|
|
現地の図面も風雨でかすれてハッキリ見えません |
|
本丸跡(松倉山山頂 標高856m) |
|
史跡「松倉城址」 |
|
城址から北方を |
下りは本丸の奥の階段から回って、登ってきた道へ戻りくだります。
「南石門の跡」の立看板を確かめて下ります。
道路脇駐車場へ惑ってきました。
次に松倉地区にある「馬の足跡岩」をご案内します。
松倉城落城秘話の「馬の足跡岩」は松倉山の反対側のアソシアホテルから「リスの森」へ向かう道中にあります。
|
「馬の足跡岩」と 岐阜県高山市千鳥町1111 |
アソシアホテルから「リスの森」へ向かう道中約1.5kmほどの左側にあります。
|
道路の左側に案内板が見えてきます。 |
| 松倉落城の秘話「馬の足跡(岩)」 振り返り見上げる松林の峰が、飛騨国司姉小路(あねがこうじ)中納言三木左京太夫自綱(よりつな)の居城「松倉城址」である。 天正十三(1585)年旧暦八月、豊臣秀吉の命を受けた金森長近・可重父子は、合崎山を本陣と定め松倉攻めにかかったが、自綱の息子秀綱が籠る城の守りは固く、攻めあぐねていた。 そこへ、三木の家臣、藤瀬新蔵の裏切りによる放火があり、秀綱以下が慌てふためくところ、「頃やよし」と金森勢は、鬨の声をあげ攻めた。 城方は散々の体にて落城となり、猛火の中、城を最後まで見届けた総大将秀綱も「もはや、これまで」と、愛馬にまたがり一気に飛び降りた。 それが、この岩上であると伝えられている。 その後秀綱は、平湯から安房(あぼう)を越え、信州福島興禅寺の伯父、桂山和尚を頼って身を寄せようとするが、途中郷民の手にかかって、あえなく落命した。 馬の足跡が残るこの巨岩は、四百余年を経た今も、山仕事や松倉観音参詣に行き来する人々に、秀綱を哀れむ松倉落城の秘話として語り継がれ、更に、この足跡を踏み締めれば足腰が強く、丈夫になると言い伝えられてきた。 昭和六十三年夏、折りしも大規模林道開設により、この足跡岩が埋め捨てられることを知った里人は、ことは重大であると高山市に陳情したところ、市の好意により、この地に飾り据えることとなったものである。 |
|
|
|
岩の上に特に「馬の足跡」は確認できませんでした。 |
「馬の足跡」(岩)から先ほどの「松倉城址」のある山が見えます。
|
松倉山(856m) |
シルバーの城郭城跡の散歩道「松倉城址と馬の足跡岩」