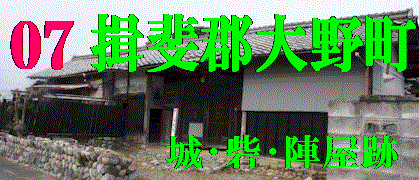
|
�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_����ӂ̏隬�V�v�i�K��S��쒬�j�̏隬�����^���܂����B
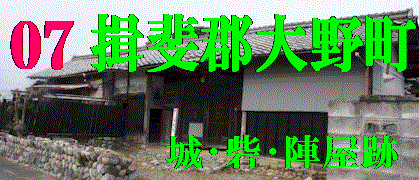
|
�@
|
�K��S��쒬 �������P�P�ӏ��̏隬���Љ�܂��B |
|
��쒬 |
79.��m�����i��쒬��쎚�Ï�j�A80.���i�����m�����i��쒬���j�A 81.���V�������i��쒬���V���j�A82.���H�����i��쒬���H�����ʁj�A 83.�������ܔV�����i��쒬�ܔV���j�A84.���i���ܔV�����i��쒬�ܔV���j�A 84-1.�~�����i��쒬�ܔV���j�A 85.���^��(��쒬����)�A86.����i���)������(��쒬����)�A 86-1.���{�ƏZ��(��쒬����)�A86-2.�Ԉ���₷����{�_��(��쒬����)�A 87.�쑺�˓@���i��쒬��j�A87.-1�ڒz�쑺�w�������i��쒬��j�A 87-2.�����~�Õ��i��쒬��j�A87-3.�����_���i��쒬��j�A 88.�D�c�͓���@���i�i��쒬��j�A88-1.��Õ��Q�i��쒬��j�A 88-2.�q���ƏZ���i��쒬��j�A89.�����w�����i��쒬�����j�A 89-1.�����w���ڒz���i��쒬��x�j�A |
|
|
�@
|
79.���m���� ���K��S��쒬��쎚�Ï� |
|
79.��m�隬 |
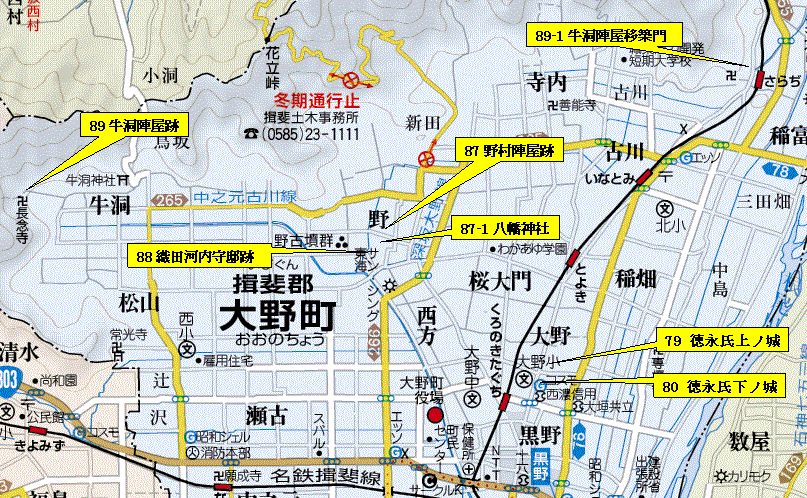 |
|
79.��m�隬 |
|
|
|
��쒬�Ï� |
�@
|
80.���i�����m���� ���K��S��쒬���@�@�C���@�R�R�� |
|
|
���i�����m�隬�i���ۈ牀�j |
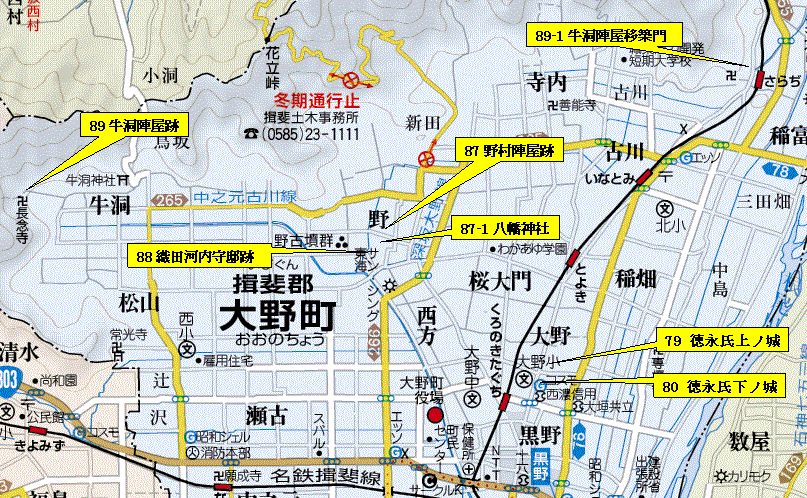 |
|
���i�����m�隬 |
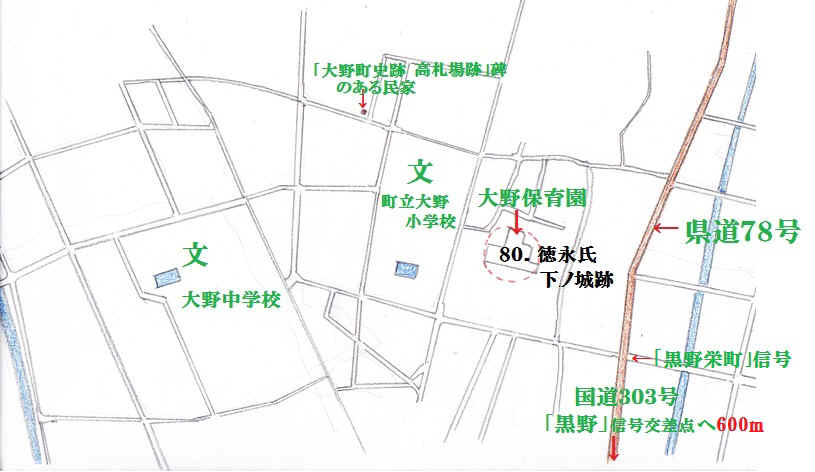 |
|
|
|
�Z��n�}���炩���Ă̍��Ղ炵�����̂��Č� |
|
�ۈ牀�̎��͂����Z��n�}�Ɍ���ĂȂ����H�������܂����B |
���i�����m��
�����Ɋւ��Ėw�Ǔ���o���Ȃ���̈�ł��B
��쒬���ŏ隬�炵���ӏ���T���܂����A
�@��쏬�w�Z�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�A�V���Z��n�łȂ����̋������Z��n�A
�B���E�����{�݁E�����_
�@�@�@�@�@�@�@�@
�Ȃǂƒn���̋��Ƃ̖K�˂Ă܂������u����ȏ�
���������Ɩ����v�u�m��Ȃ��v�ł����B
|
�B��A���~���Ɂu��쒬�j�� ���D��v�̕W���̂���Ƃ����܂����B |
|
�L�����~�ɗ��h�Ȗ� |
�@
|
81.���V���隬 ���K��S��쒬���V���X�X�V�|�S�@ |
|
|
|
|
���V���隬 |
 |
|
���ю����u���V���隬�v�ƌ����Ă��܂����隬�����������܂���B |
|
��̈�\�炵�����̂͌�������܂���B |
�@
|
82.���H�隬 ���K��S��쒬���H�����ʁ@�@�C���@�Q�R�� |
|
|
���H�隬 |
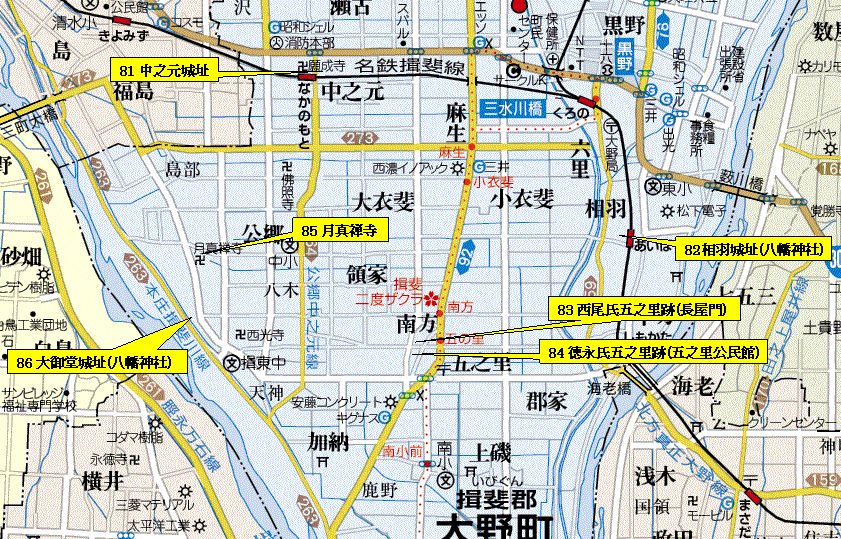 |
|
�隬�͔����_�� |
 |
|
���H�隬 |
|
�����_�Ђ��隬�ƌ����Ă��܂��B |
|
|
|
�u��쒬�j�ց@���H�隬�v�肪����݂̂ň�\�炵�����̂͌����܂���B |
|
���H��̗��j |
�@
|
83.�������ܔV���� ���K��S��쒬�ܔV���@�@�C���@�P�V�� |
|
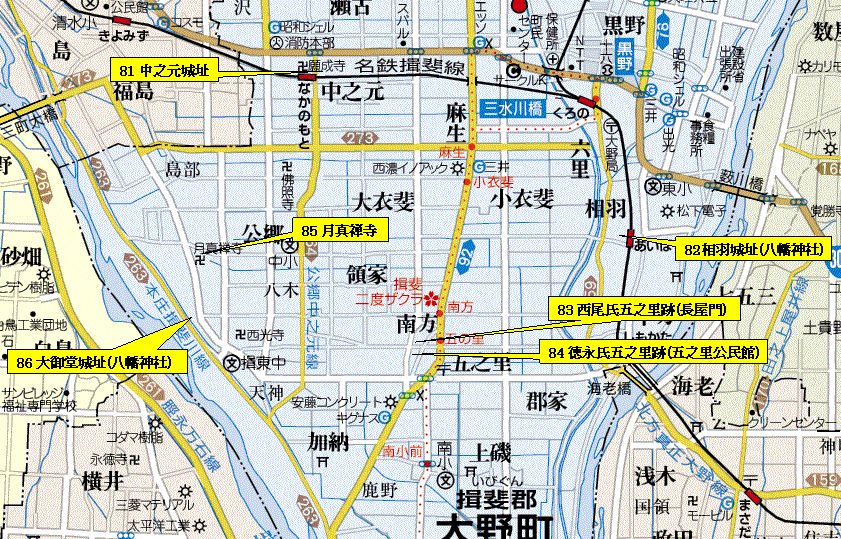 |
|
�������ܔV�����ƒ����� |
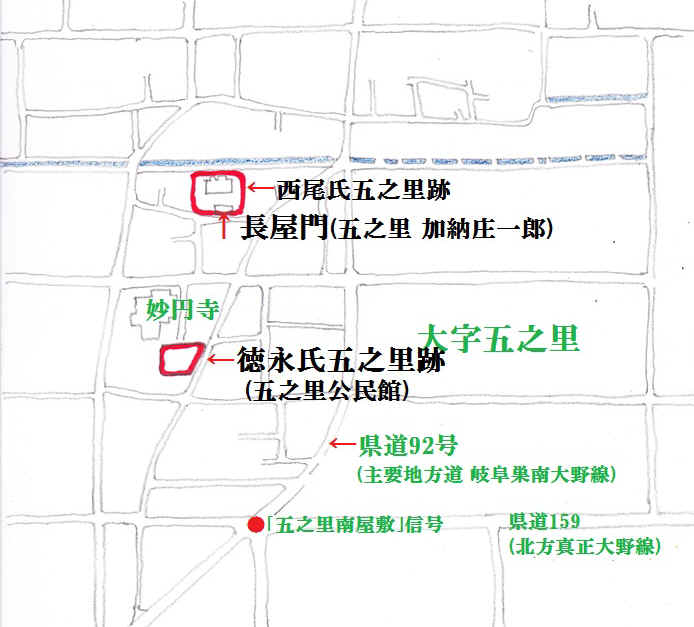 |
|
�T���� |
| �����傪����u�������ܔV���v |
| �u������v ���ʂɂ́u�܃m���@���[����Y�v ��쒬����ψ���u������v �����͔g�����A���͈ꕔ���������A ��̗��ɂ��u���������ɂ��܂��傤�v�̕����������Ă��܂��B |
�@
|
84.���i���ܔV���� ���K��S��쒬�ܔV���@�@�C���@�Q�O�� |
|
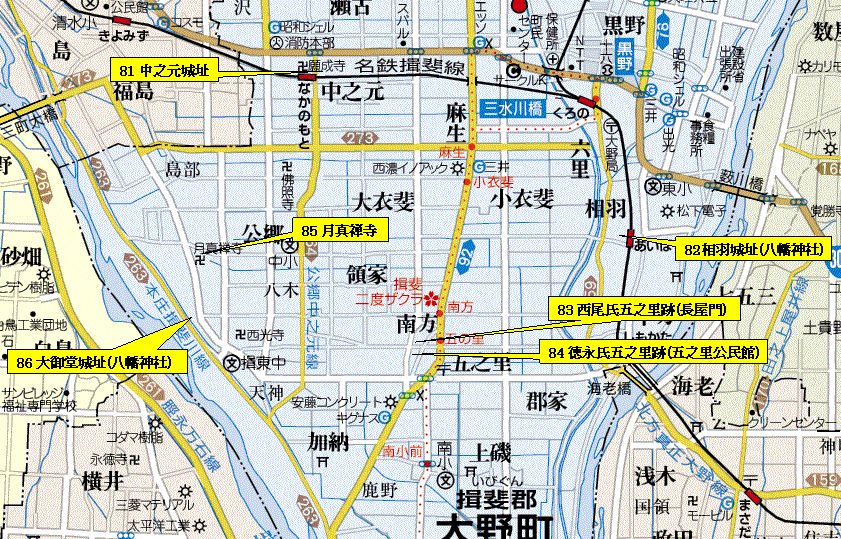 |
|
���i���ܔV���� |
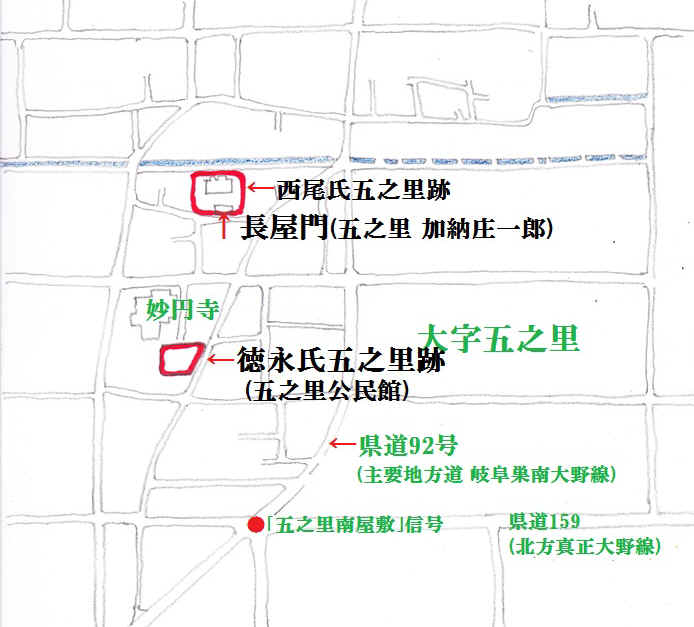 |
|
�T���� |
|
�u���i���ܔV�����v |
�@
|
84-1.�@���~�� |
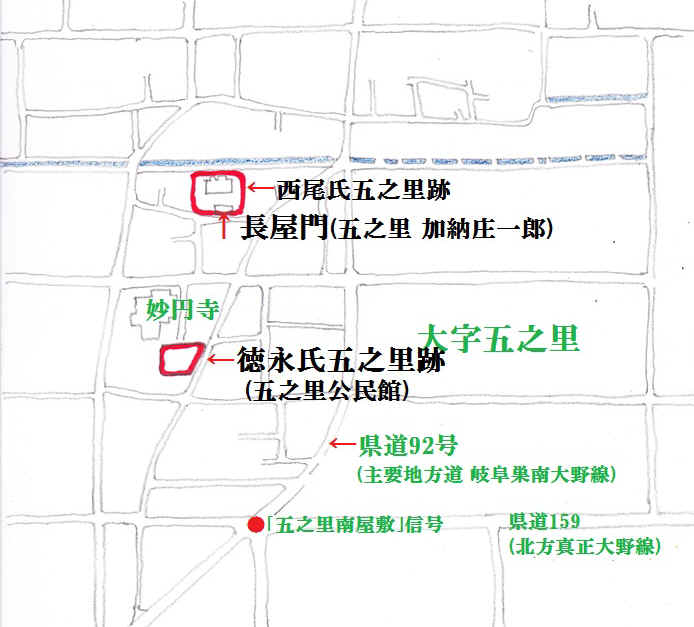 |
|
�T���� |
|
�ؑ�Z�E |
��䓰��̋K�͂͑傫���u���^���v�̐������u�����_�Ёv�܂ł�
�L���n����߂Ă����悤�ł��̂ŗ��n���u��䓰�隬�v�Ƃ��܂����B
|
85.���^�T�� ���K��S��쒬���� |
|
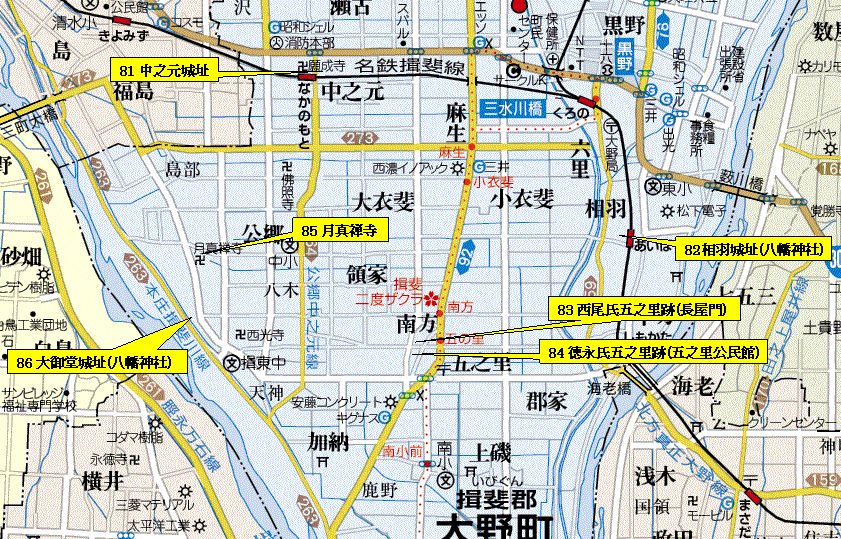 |
|
����^�T������u��䓰�隬�v�̏ꏊ |
 |
|
��䓰��͒|�������q���a�̏� �u�|�������q�̕�v |
|
�����������瑡��ꂽ��͉������j�ꍡ�ɂ��|�ꂻ���ł��B |
|
���ɂ����ꂻ���ʼn���������̂����X�|���I |
���^���̐��ʂ̎R��͔��肸�炢�����ɂ���,
�u�����v�͕�����₷���L�������e�ɂ��蓹�H�����ɕ�Ɩ{����������B
�i��쒬�����w�Z�쑤�̓��𐼂��X�O�O���قǂ̌����H���s�p�ɓ��200m�قǏꏊ�ł��B�j
| �@ |
|
�r�n�r���O |
|
�u�|���d���̕�v���u���������i�Z�V��w���������w���̎�j�̕�v |
|
�u���j�Ձv�̒|���d���i�G�g�̌R�t�|�������q�̕��j�� |
�@
|
86.��䓰�隬 ���K��S��쒬�����@�@�C���@�Q�X�� |
|
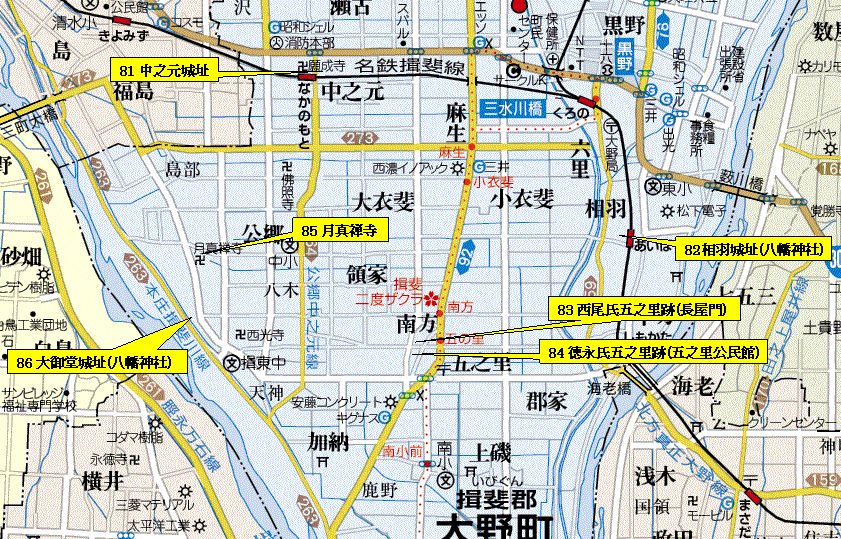 |
|
����^�T������u��䓰�隬�v�̏ꏊ |
 |
|
�|�������q���a�̒n �u�|�������q�̕�v |
|
�����_�Ў��͈�т��u��䓰�隬�v�ł��� |
|
�_�Иe�ɂ͐ΐ��́u��䓰��v�}�v�Ɓu�|�������q�d�������a�V�n�v�肪����܂��B �@��䓰��́A�z��N���z��҂ɂ��Ă͒肩�łȂ����A�퍑����ɒ|���d�������邵���B |
|
�u�|�������q�d�����̗R���v |
|
���̔����_�Ђ͑���@�����Ƌ��ɏo���ɍ݂����Ǝv���܂��B |
|
|
|
���̔����_�Ћ����͏�̏o���ɂ���܂����B |
�@
|
86-1.�Ԉ���₷����{�_�� ���K��S��쒬���� |
|
�����_�Ђ̍ŋߊJ�����ꂽ�Z��n�̔��Α��ɂ���A |
�@
|
86-2.���{�ƏZ�� ���K��S��쒬�����@�@�C���@�R�X�� |
|
|
�剮���̓g�^���Ńy���L�h��A��̗��ɂ� |
|
���͓����X���ǔ͔��������A�����͔g������ςȏ�Ԃł��B |
�@
|
87.�쑺�˓@�� ���K��S��쒬��@�@�@�C���@�R�Q�� |
|
|
�쑺�˓@�� |
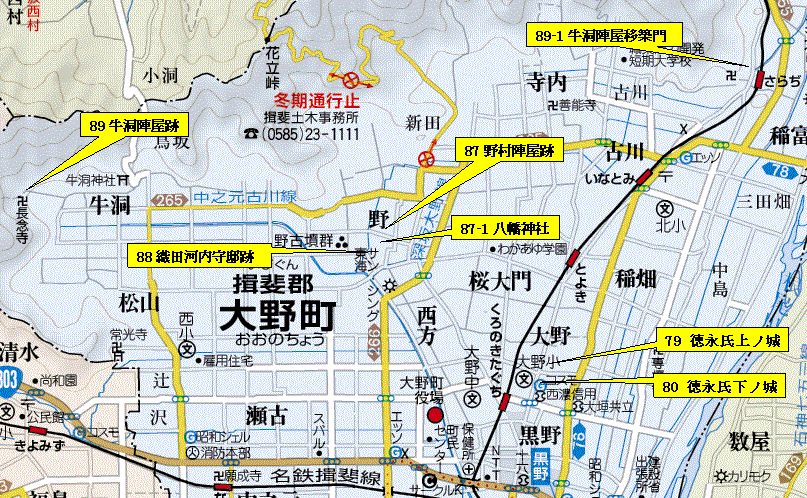 |
|
�@�쑺�˓@�Ղ͔����_�Ђ̗� |
 |
|
��쒬�j���u�쑺�˓@�Ձv |
|
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�쑺�˂̗��j �@�c���T�N�A�փ����̐���ɂ��A�D�c���F�����̒n�ɂP����^�����A�w����z�����B �@���i���N�i�P�U�R�P�j�A�Q�㒷���͎k�q�Ȃ��v���A�쑺�D�c���͒f��ƂȂ��� �@����N�i�P�U�T�T�j�A��_���˓c���S�̎��j���o���V�c�S�C�O�O�O�m����A���̂ƍ��킹�U�C�Q�O�O��̂����B�@ �@���\���N�i�P�U�W�W�j�A�R�㎁�����{�Ƃ��V�c�̕��m�Ȃǂ�����A�\���P����̂�����ɗ��B�i��_�V�c�ˁj�@ �@�c���l�N�i�P�W�U�W�j�A�X�㎁�ǂ̎��{�Ƃ����S�쑺��^�����A�쑺�˂��̂����������ɔp�˒u���ƂȂ����B |
|
|
|
��쒬�j���@�쑺�˓@��(���a�T�R�N�w��) |
|
�@ |
|
�����_�Ђ̗����� |
|
87-1.�����_�� ���K��S��쒬��@�@�@�C���@�R�Q�� |
|
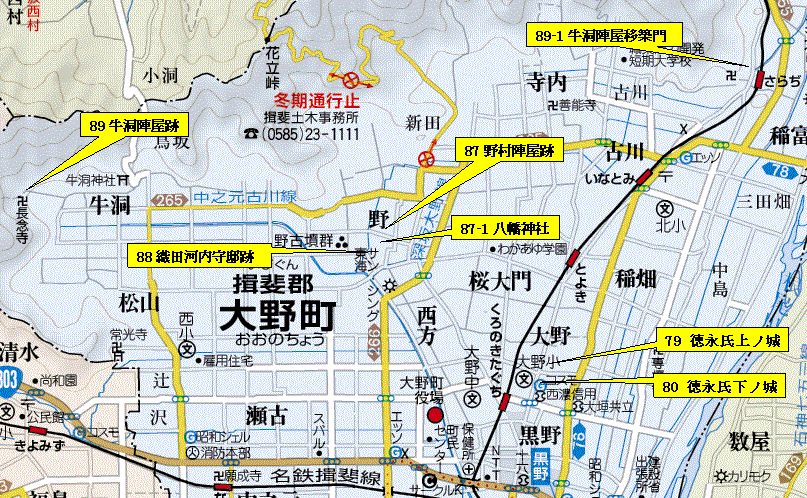 |
|
�����_�Е\�Q�������ɂ� |
|
�����_�� |
 |
|
�����_�Ђ̕\�Q���ɂ����铹�̐����ɂ� |
|
87-2.�쑺�˓@���� ���K��S��쒬��@�@�@�C���@�R�Q�� |
|
 |
|
�����_�БO�̓����ւP�{�ڂ̐��ł��B |
|
�����_�Ђ��琼���P�{�ڂ��Ȃ�����u�쑺�˓@����v������܂��B |
|
|
���̒҂̉��ɂ͌Õ�������Õ��̏�Ɂu���Ɓv�������Ă��āA�Õ����́u���R�Õ��v�ƌĂ�Ă��܂��B
87-3.��Õ��Q�u�����~�Õ��v ���K��S��쒬��@�@�@�C���@�R�Q�� |
|
�҂̓˂����肪�Õ��ł��̏�ɉƂ������Ă��܂��B |
�����_�БO�̓��̂T�{�ڂ𐼂Ȃ���Ɓu�D�c�͓���@�Ձv�֍s���܂��B
|
88.�D�c�͓���@�� ���K��S��쒬��@�@�@�@�C���@�P�X�� |
|
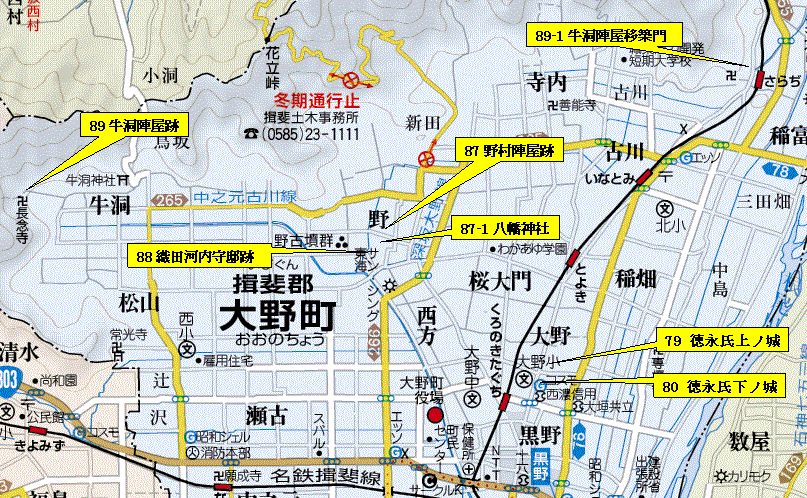 |
|
�D�c�͓���@�� |
 |
|
�n���ł��u�D�c�͓���@���v����u�쑺���~�W�v�̕����L�� |
|
�����_�БO�̓��̐����̒Ҍܖ{�ڂ𐼂ɋȂ��薯�Ƃ̊Ԃ𐼂i�ނƓˑR�L����ԁi���j�ɏo�܂��B |
|
�u�D�c�͓���@�Ձv |
|
�n���̐l�ɂ́u�쑺�g�t�v�����L�� |
�u�D�c�͓���@�Ձv�̐����ɂ́u��Õ��Q�v���L����܂�
88-1.�u��v�Õ��Q ���K��S��쒬��@ |
|
�u��v�Õ��Q���D�c�͓���@�� |
 |
|
�u��v���Q |
|
|
|
|
|
�u脰(���Ȃ�)�����Õ��v��u���Õ��Q�v |
|
�u�����Q�v |
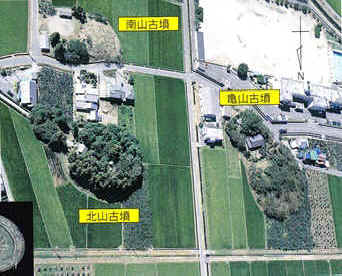 |
|
���쒬���̓쏬�w�Z�k���p�ł��B |
�@
88-2.�q���ƏZ�� ���K��S��쒬��@ |
| �@ |
| �@ |
|
�ԕ�Q�m�̓�������̑O�N�̌��z�Ɠ`�����A |
|
��쒬�d�v�������ɂ͂��́u��v��u�b�h�v��^�����E�v���w�肳��Ă��܂��B |
|
���̏d���Ɏw�肳��Ă銄�ɂ͉������j���ȂǍr��Ă��܂��B |
���́u��Õ��Q�v���琼�k�̎R�̒�����
�uE-90�����w���v�Ɩڈ�ɂȂ��u���N���v������܂��B
�R�̒����Ɂu���O���v�������܂��B�w���͂��̉E���ł��B
�w���͍�������オ��������ɂ���܂��B
|
89.�����w���� ���K��S��쒬�����Q�U�i���N�����j |
|
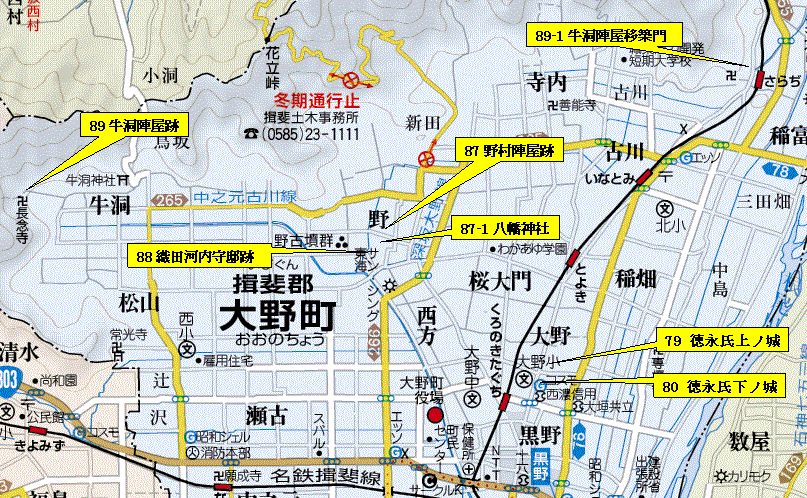 |
|
�����w���� |
 |
|
�u��쒬�������@�����w�����v�� |
| �@ |
|
�@�@�@�@�@�����w���͒��O���̓����� �@�����w���́A�����n��̐��[�ɂ��钷�O���ɕ���Œz����Ă��܂��B |
|
�]�ˎ��ケ�̒n�����߂����{
�˓c���͎�̐w�����ƕ��Ɖ��~�̐Ί_���c����Ă��܂��B |
|
�@�@�����w���̗��j |
|
�w�������͂��Ȃ�O�Ɉ�ʂ̉ƂɌ��đւ���ꂽ�����ł��B |
|
�u�����˓c�w�����D��Ձv�͐w���̑O�ɂ���܂��B |
|
���o�R���O�� |
|
�ڈ�ɂȂ�u���o�R���O���v�͋����w���̉��ɂ���܂��B |
|
���h�Ȓ��O�����O��ł� |
|
�w������̌����炵�͐�D�̏ꏊ�ɂ���܂��B |
���̋����w���̖傪�����ȍ~�Ɉ�x�n��Ɉڐ݂���Ă��܂��B
|
89-1.�����w���ڐݖ� ���K��S��쒬��x�T�V�W�i��[�@�j |
|
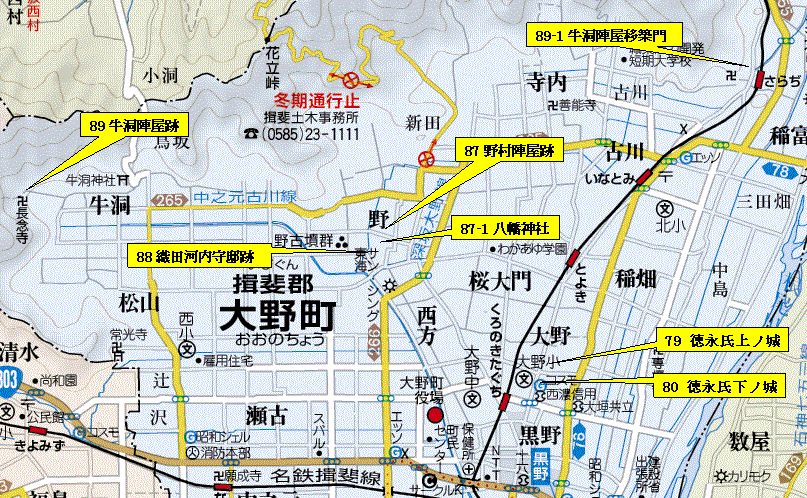 |
|
�����w���ڒz�� |
|
|
|
�����w���ڒz�� |
 |
|
�ڒz���ꂽ���~�͍L���A���ɖ傪����萳��͍����ɂ���A |
|
�����̕����傫�����h�ł� |
|
��O�i�E���j�̕����u��쒬�d�v�������@�����w����v�ł��B |
���̕ӂ�͓����悤�ȗ��h�Ȗ���\�����Ƃ���������܂��B
�ԈႢ�₷���Ƃ̖����f�ڂ��Ă����܂��̂ŎQ�l�ɂ��Ă��������B
|
���h�ȃA�v���[�`�̉��ɂ���\�D�����܂����ꏊ�ɂ���̂� |
|
�{���͐������ꂽ�Ƃ̖�ł����B |
|
���ɂ��Ί_�����h�ō\���̑傫�ȉƂ���R����̂łт����肵�܂��B |
�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_����ӂ̏隬�V�v�i�K��S��쒬�j