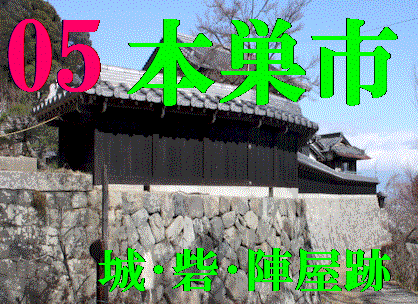
|
�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_����ӂ̏隬�O�T�v�i�{���s�j�̏隬�����^���܂����B
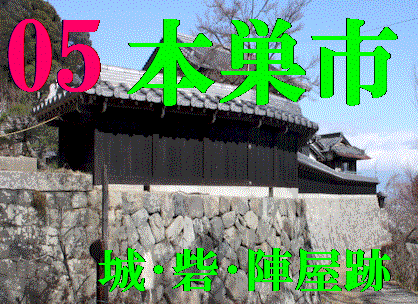
|
�@
|
�{���s �s�����Q�R�ӏ��̏隬���Љ�܂��B |
|
D.�{���s |
48.���`����i�{���s���`�j�A 49.�y�C�i�����)�����(�{���s�y�C���k���~640�j�A 50.�Ԗ�(���ڂ�)����i�{���s���O�F���ߥ�ŏ掛�j�A 51.�����i�₢)����(�{���s����j�A 52.���̏���i�{���s����j�A53.����w�����i�{���s����j�A 54.�R����勏�ٚ��i�{���s���R���j�A 55.�R����Ձi�{���s�R���E����̐X����) 56.�@�ю���� �i�{���s����E�R����̐�j�A 57.�S���R����i�{���s���@�ю���̉�)�A 58.�|����� �i�{���s����E�S���R��̐�̔����j�A 59.������i�{���s�O�R�͓��j�A 60.�h�����l�̏�Ձi�O�R�����j(���{���S�{����)�A 61.�����隬(�Ԑ�)�i�{���s�����j 61-1.����������f�w-1�i�{���s���������V�z�j 61-2�V�储�Ƃ�-1��~�����i�{���s�����j 62.����(�ЂȂ�)�㊯�����i�{���s�����j 62-1�V�储�Ƃ�-2������i�{���s�����j 63.�F�Îu�����i�{���s�����Ï�j�A 63.��(�����ǂ���)�����i�{���s�������j�A 64.��������i�{���s���������j�A 64-1.�����J�f�w�i�{���s���������j�A 64-2.���n�̍��i�{���s�����������j�A 65.���������i�{���s�����s��j�A 66.�_��(�����ǂ���)�����i�{���s�����_��(�����ǂ���) 67���̓a�l���~���i�{���s�������=�o���K���[���j �A 67-1.��W�l�̐��i�{���s�������j 67-2.����������f�w-�Q�i�{���s�������j 68.���̓a�l���~���i�{���s������=�����_�Ёj�A 69.��������i�{���s��������=�fᵖ�(�����̂�)�_�Ёj�A 69-1�V�储�Ƃ�-3��O�m�i�i�{���s�������j 69-2�������d���i�{���s��������j 70.�\���a�l���~���i�{���s�����\���㌴�j 70-1.�\�����R�_���i�{�������\���@���R�_�Ёj |
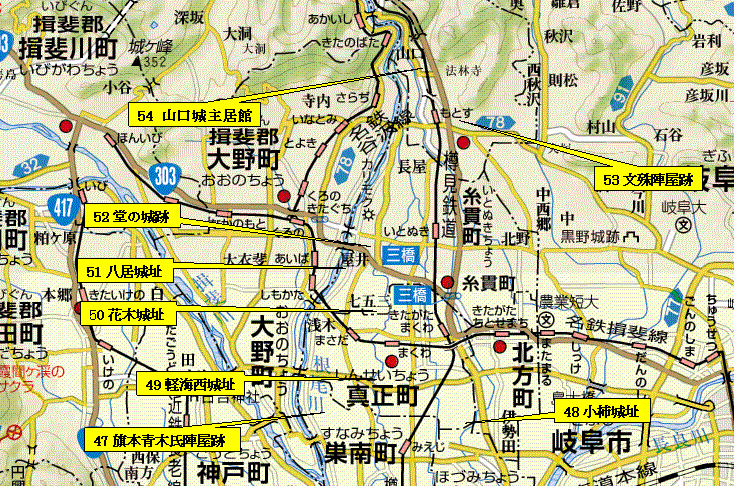 |
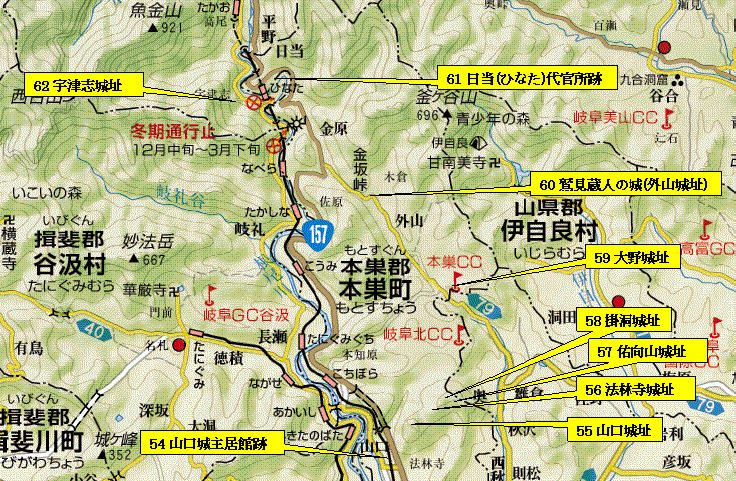 |
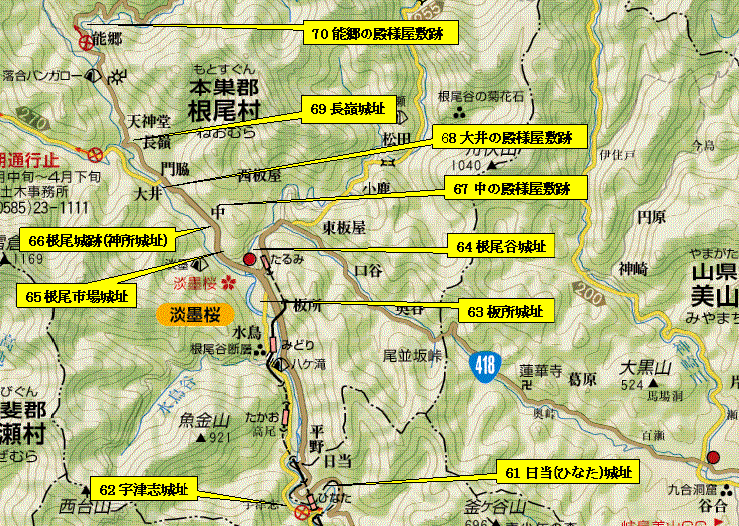 |
�@
|
48.���`�隬 �{���s���`�@�@�C���@�Q�O�� |
|
|
�u���`�隬�v |
|
|
|
���`�隬 |
 |
|
���`�隬 |
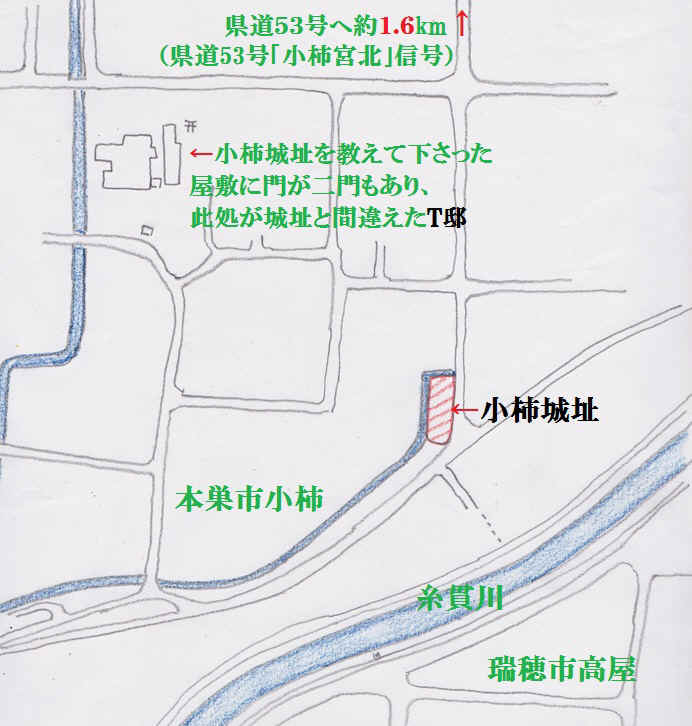 |
|
�W�������猩���u���`�隬�v���u���ѐ��h�v |
|
�u���ѐ��h�v�ォ�猩���u���`�隬�v |
�����Ⴂ�Łu�Z�\�����v
|
��Ղł͂Ȃ����Ɗ��Ⴂ���ĖK�� |
|
����ɂ��傪����u��\���v�̉Ƃł����B |
|
�u�V���o�[�̎U�����v������ȖK������Ă��u����J���܂ł��v�ƁB |
�@
|
49.�y�C���隬 ���{���s�y�C �~�����@�@�C���@�W�� |
|
|
�隬�肠�� |
|
|
|
�y�C���隬 |
 |
|
�y�C���隬(�~����) |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w��j�Ձ@�y�C���隬 �@�y�C����͌ËL�^�ɂ��Ή����������ق̒n�Ƃ����邪�n���̎���͖��炩�łȂ��B �@�y�̎���Ɏ����Ĉ�t�����A���㋏�Z�����̌�A��������Y�i�̂��̐ē����O�j�����Z�����Ɠ`������B �@�i�\�N�Ԓr�c�����̉Ɛb�Ћ˔��E�q�傪�v�Q������ďZ�Ƃ������i�\�l�N�i�P�T�U�P�j�y�C����̐܂�d�v�Ȗ������ʂ������̂Ɛ��肳���B �@�V���\���N�i�P�T�W�T�j����ɓ��璼�����Z���Η̂��A���̒n���x�z�����B �@�����͖L�b���ɏ]�����c������ɉ�����Ĉɓ��R���ɂĐ펀�����B �@�̂�����i�̂������j�������Č��Ă��̂��~�����ł���Ƃ�����B �@���̎�����y�C�隬�Ɛ��肵�A���a�\�l�N�l���\�ܓ� ���̎j�ՂƂ��Ďw�肳�ꂽ�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�{���s����ψ���j |
|
|
|
�������͂ލ��Ղ��킸���ɖʉe���c���Ă��܂��B |
�@
|
50.�Ԗ��i���ڂ��j�隬 �{���s���O�i���߁j�@�ŏ掛�@�@�C���@�@�P�S�� |
|
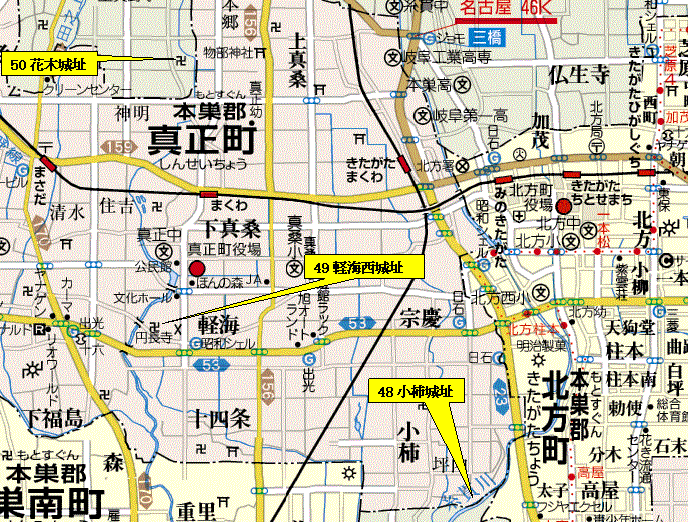 |
|
�Z�E����̘b�̂�(�����m�F�Ȃ�) |
| �@ |
|
�Z�E�̘b |
�@
|
51.����(�₢)�隬 �{���s���� �C���@�@�P�V�� |
|
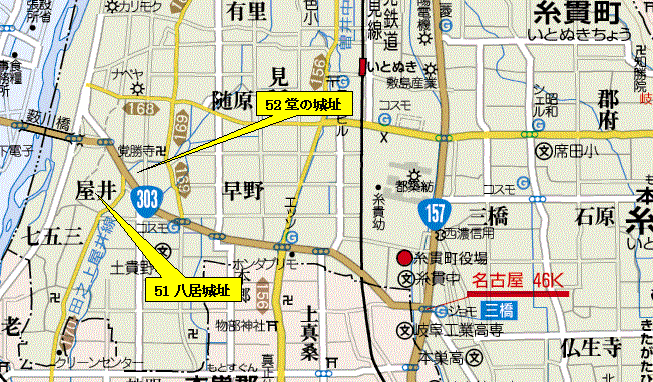 |
|
������� |
 |
|
�����隬 |
|
|
|
���ɖ傪�����Ă��܂����B |
|
�C���^�[�l�b�g���u����̂Ƃт�v���ɂ���u�������@�v���Q�l�� |
|
�[���̖Z���������ɂ�����炸���l���Ή����Ă������� |
|
��̗����ɂ͖x�̐Ղ�����܂��B |
�@
|
52.���̏隬 �{���s���� |
|
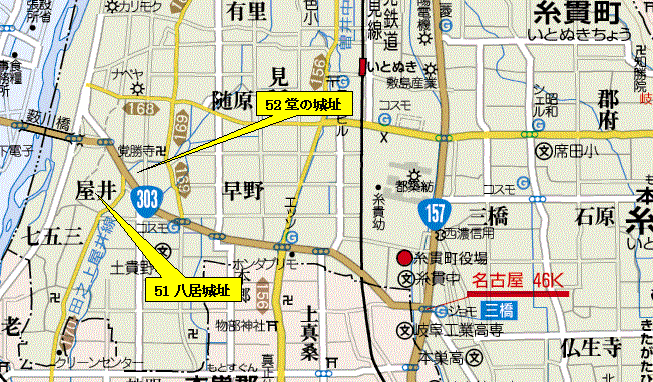 |
|
��Տꏊ�s�m�F (�����s�m�F) |
 |
|
�n���̐l�ɕ����ĉ������10�l10�F�̉ł����B |
|
��h�e�̊`������� |
|
����l�͍����R�O�R�̐M���u����v�̒҂͈ȑO���u���̏�v�ƌĂ�ł����B |
|
�ŋ߂܂ł������������I |
�@
|
53.����w���� ���{���s����@�@�C���@�S�S�� |
|
|
�@ |
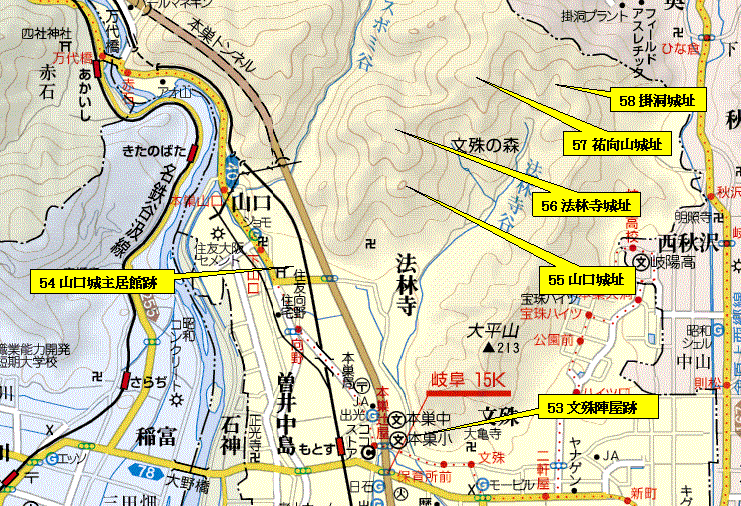 |
|
�T�Q�u����w������v |
|
|
|
�����P�T�V�́u�{�����w�Z���v�̐M���𓌂֓���V�O���قǂ̓쑤�̌��������e�Ɂu����w���Ք�v�������܂��B |
|
|
�@
|
54.�R����勏�ِ� ���{���s���R���@�@�@�C���@�@�T�R�� |
|
|
�m�F�肠�� |
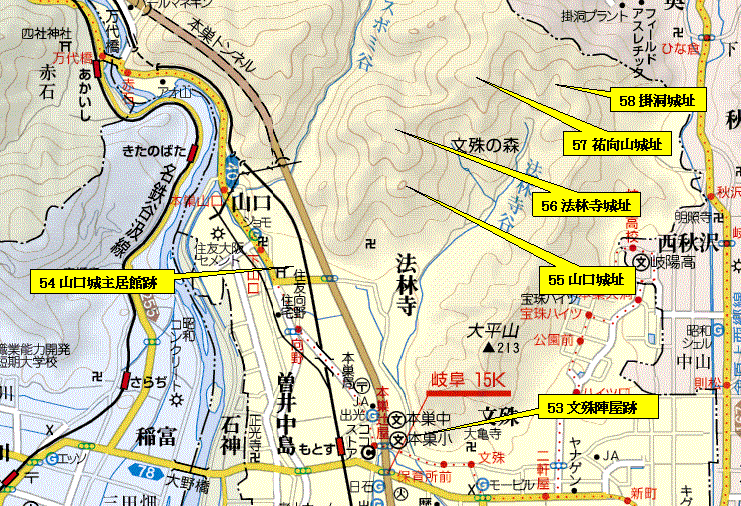 |
|
�R����勏�ق͐D���w�̐��� |
|
|
|
�M���S���u�D���w�v�v���b�g�z�[�����ɂ���܂� |
���~�̎�����X�ɉ��܂���
|
�����|�M�̒��Ԃ̉��ɖ傪�����܂� |
|
�Ăђ|�M�̎��͂ɉ����Đ��̕��֕����ƒ|�M����Ė��邢���֏o�܂����B |
|
�j���@���g�����t�Z���Ձ@���Z���R���� |
|
|
�@
|
���̏�Ձ@�o�R ���{���s�R������i����̐X�����j |
|
|
���n���K�� |
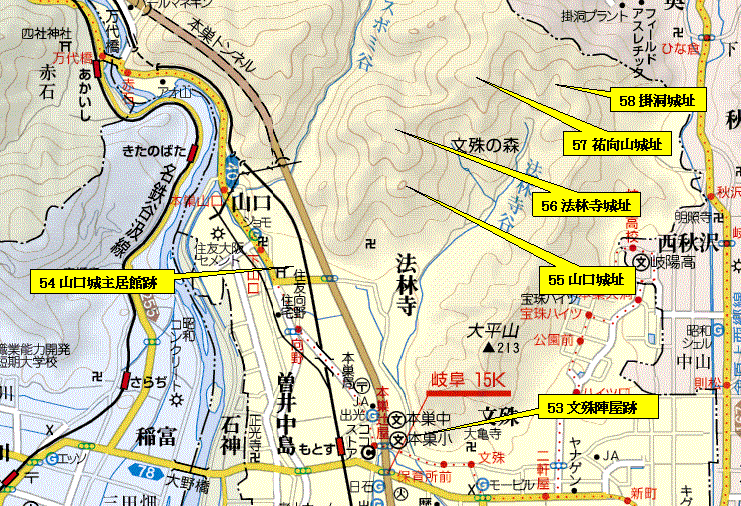 |
|
�R���隬�E�@�ю��隬�E�S���R�� |
|
�摜������ |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
�u����̐X�v�o����ɒ��ԏ�i�����j������Ԃ͂����ɒu���ēk���œo��܂��B |
|
�Óc�D���̈ꐶ |
|
�@ |
�@
|
56�@�ю��隬 �{���s����i�R����̐�j |
|
���n���K�� |
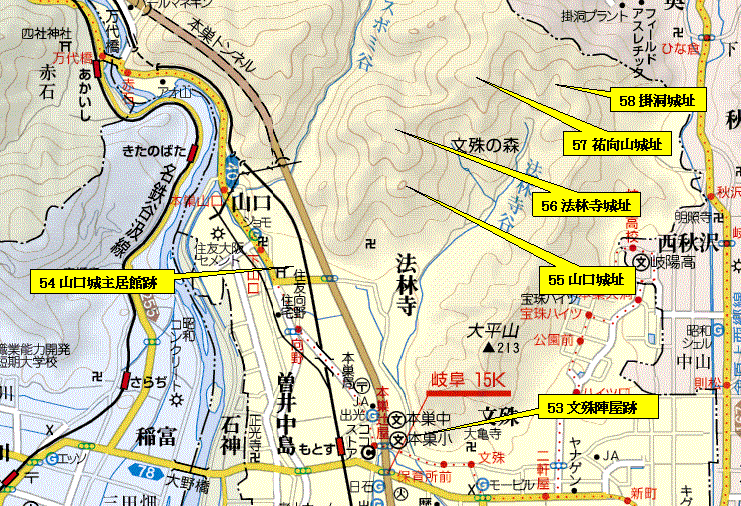
|
57�S���R�隬 .�{���s����(�@�ю���̉�)�A |
|
���n���K�� |
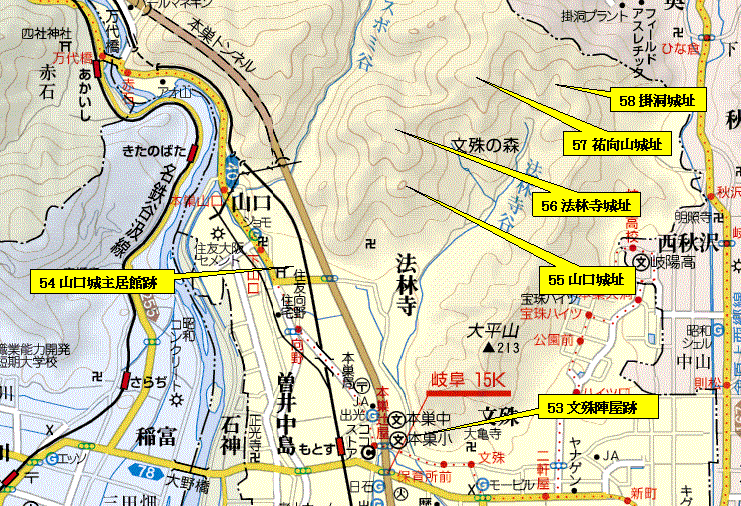
|
58�@�|���隬 �{���s����(�S���R��̔���) |
|
���n���K�� |
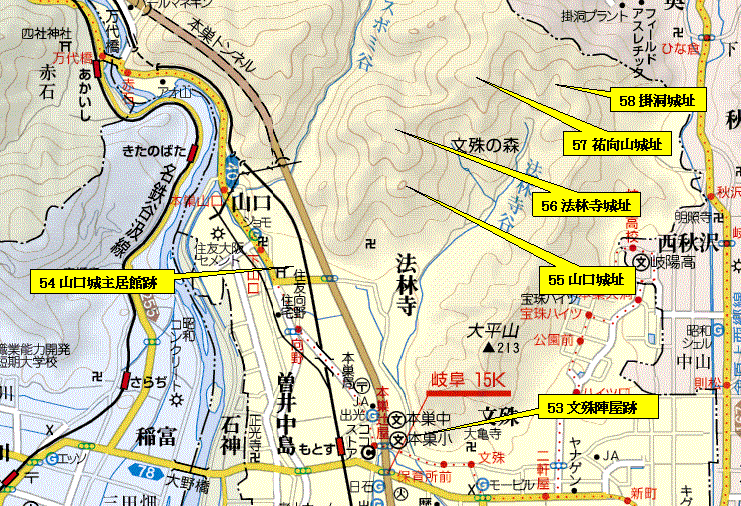
�|���隬���S���R���̔������ɂ���悤�ł��B
|
59.���隬 ���{���s�O�R�͓��@�@�C���@�P�R�S�� |
|
|
��m�F�摜���� |
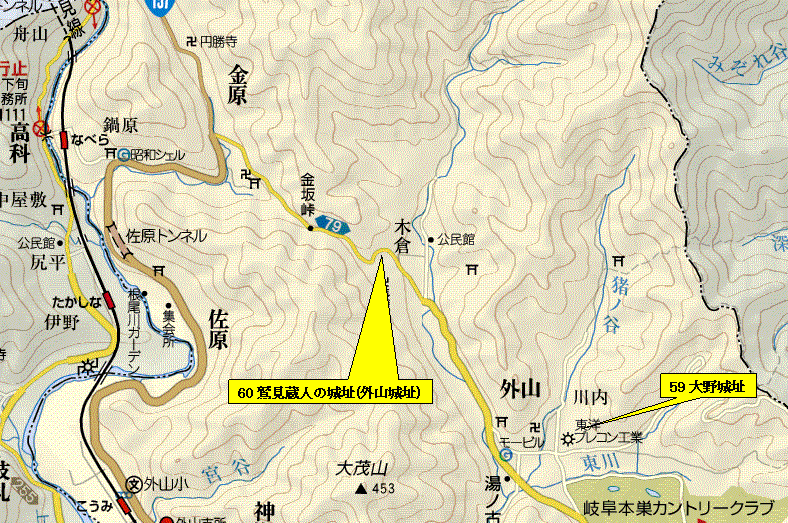 |
|
����͖{���J���g���[�k |
 |
| �@ |
|
���隬�� |
|
�n���̐l�Ɍ��킹��Ɓu�n���ω������邾������v�Ƃ̂��Ƃł��B |
|
|
|
���隬��̗��ɂ� |
|
������̈ʒu���T���Ȃ�������A���̏W���ɗB��̂��X�u���G�v��T���Ă��������B |
|
���隬�̍� |
�@
�@
|
60.�h�����l�̏隬 �i�{���s�O�R(���{���S�{����) |
|
�j�֊O�R�隬�肠�� |
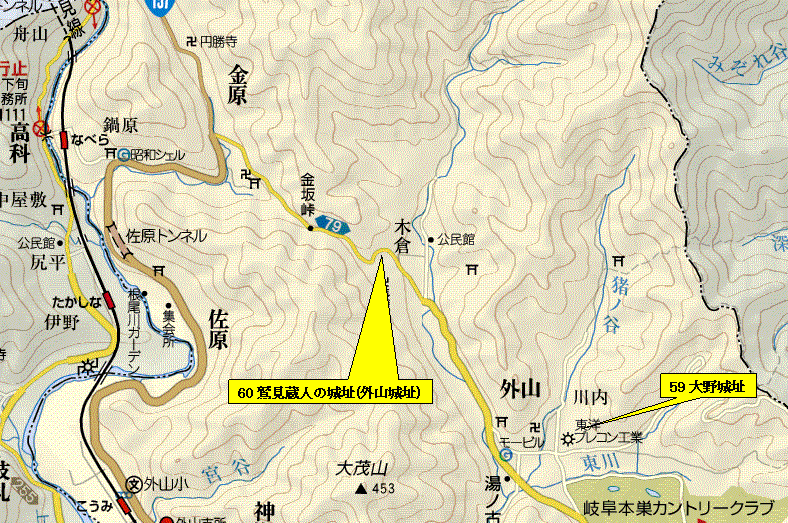 |
|
�h�����l�̏�Ձi�O�R�隬�j |
 |
|
�����V�X�������⓻�̓���Q�O�O���̓��H�������u�O�R��j�v�̐���������B |
|
�O�R��j�P�i�z��܂ł̌o�܁j |
|
�O�R��j�Q�i�z���̌o�܁j |
|
���K�ꂽ���͋C�t���܂���ł������A��Ղ̉��̃J�[�u�̏��ɢ�隬��v������܂����B |
|
|
�@
|
61-1.���������ꊈ�f�w ���{���s���������V�z�@�@�C���@�P�S�V�� |
|
|
�s�w��L�O��(�V�R�L�O�� |
 |
|
�u���������ꊈ�f�w�v |
|
�����n���ɂ� |
�@
|
6�P-2.�V�嗎�Ƃ� ���{���s�����@�@�C���@�P�R�V�� |
|
 |
|
�����P�T�V���������ɓ���Ɓu�P�����v�̈ē����ڗ��̂łP�T�V���̘e���i���P�T�V���j�ł������ɕ�����܂��B |
|
|
|
�P���@�t�R���n�� |
|
|
�@
|
61������(��)�� ���{���s���� |
|
|
�u�֒r�v |
|
|
|
�u�֒r�v�̓�(����157��)���Α��ɂ���K�i��o�� |
|
�����o�������Ɂu��v���K���������̂ŃV���^�Ǝv�������u�R�̐_�v�����Ղ肵���K�ł����B |
|
���炵�����̂�H���ēo��Ə��X�ɐԂ��Y�����߂Ă���̂ł���ɉ����ēo�邱�Ƃɂ����B |
|
�����隬���H |
�@
|
6�Q.�����i�ЂȂ��j�㊯���� ���{���s���� |
|
|
���̓����Q�T�O���قǐi�ނƃR�~���j�e�B�o�X�u���������فv�̃|�[�������� |
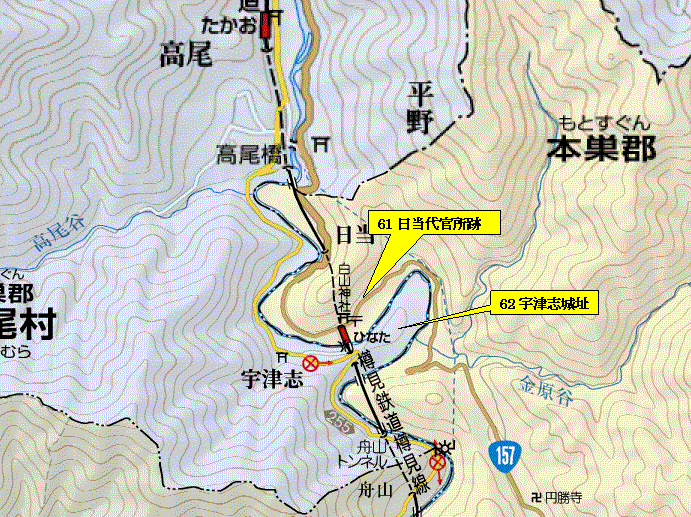 |
|
�����㊯���� |
|
|
|
�u�j��
�����㊯���Ձv���̗��ɂ� |
|
���Ɍ�����̂��w�ɂł��B |
�{�ʂ�̍�̏�ɂ͒M���S���u�����w�v������܂�
|
�M���S���u�����w�v�̏�̓��H��k�֓˂����蓌���u���R�_�Ёv�����܂��B |
|
�u�����w�v�̊Ŕ̉E�ɂ������ɃK�[�h���[���������܂��� |
�@
|
6�Q-1.�V�嗎�Ƃ� ���{���s�����@�@�C���@�P�S�V�� |
|
|
�M���̖{�莛�U�߂̔g�y |
 |
|
�ڈ�́u�����w�v�k�̋�����쉈���ɖk�ւ̂ڂ�A |
|
�u�V�嗎���v�ւ̉���� |
|
�~�����P���@�t�R���n�i�V�嗎���j |
|
|
|
�K�i������āu�M���S���v���H�����i�ނƔ肪�����Ă��܂��B |
|
�u�����~�����R���n�v�肪����܂��B |
�P���@�t�R���n�� |
�����n��̂W�隬
|
63�D�F�Îu�隬 ���{���S�����F�Îu�Ï�@�@�C���@�P�T�P�� |
|
|
�F�Îu�隬 |
|
|
|
�u�F�Îu�隬�v |
 |
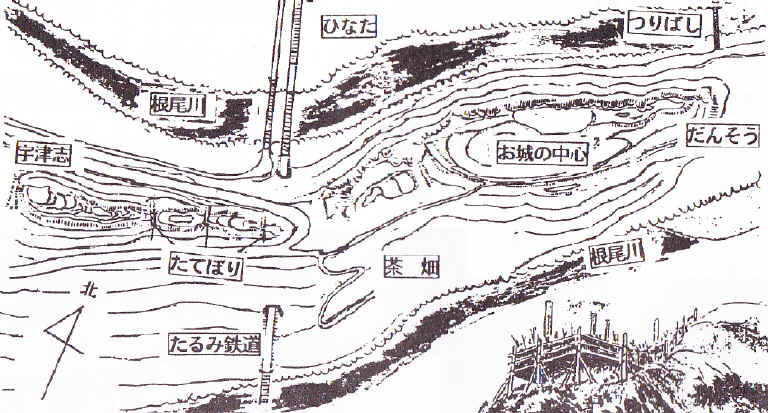 |
|
�F�Îu�̂��� |
|
�ڈ�ƂȂ�n���̉Α��� |
|
�~�G�͌����Q�T�T���͒ʍs�~�߂ł��B |
|
�x�����������N�ԁi�P�R�R�S�`�P�R�R�W�j�Ɍ��Ă��Ɠ`������B |
|
�Α��ꂩ���R�O�O���قnj����Q�T�T����i�ނƃw�A�s���J�[�u����Ղł��B |
|
|
|
����͐�������隬�܂ōs���Ă݂悤�Ɠo��n�߂܂����� |
�@
|
64.�����隬 ���{���s���������@�@�C���@�P�X�V�� |
|
|
|
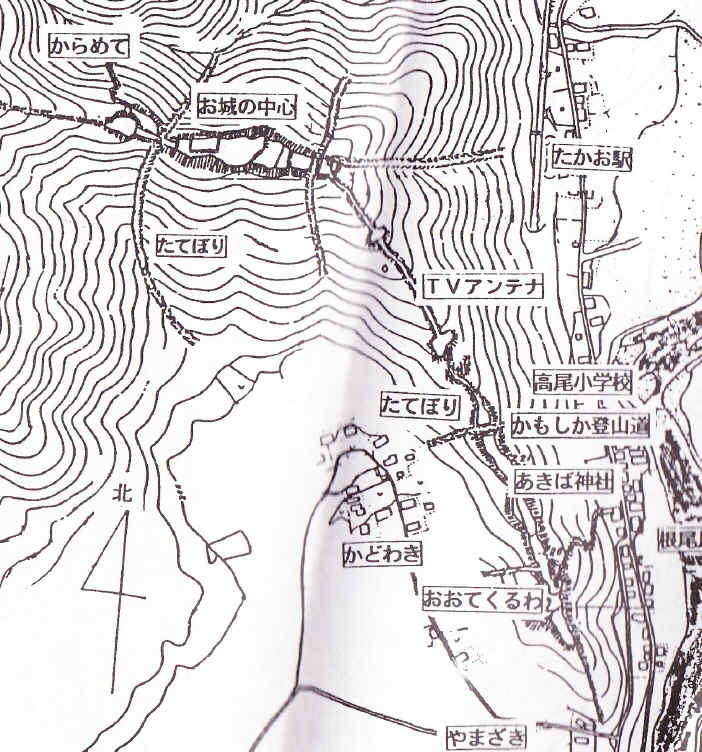 |
|
������̗��j |
|
�����隬 |
|
��e�n�� |
|
�R��n�� |
�@
|
64-1.�����J�n�k�f�w ���{���s������������(�݂ǂ�)�@�@�C���P�T�U�� |
|
|
�����̒f�w�ʐ^�� |
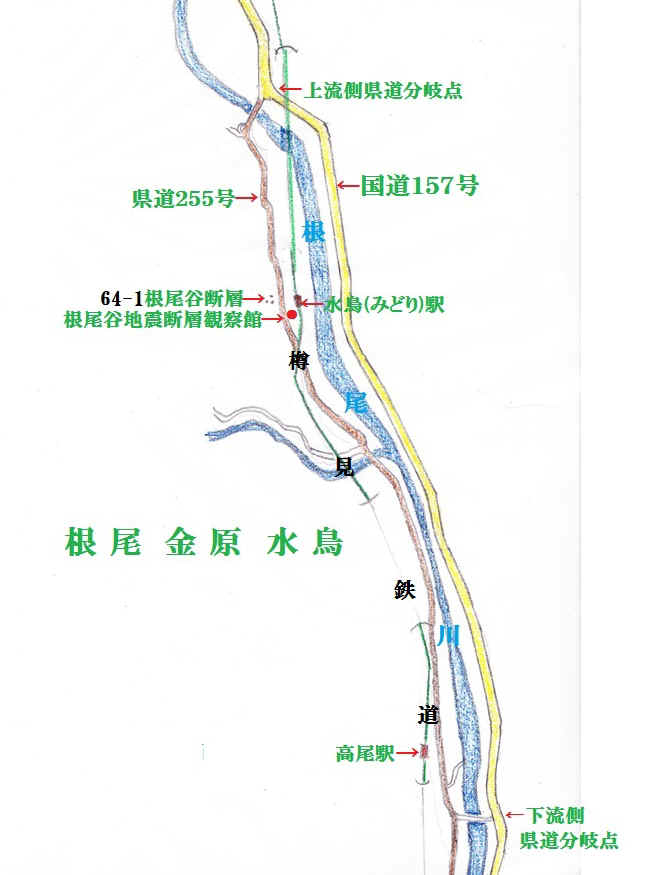 |
|
�����J�n�k�f�w�͍����P�T�V���̑Ί݂ɂ���̂� |
|
�u�V�R�L�O�������J�f�w�v�� |
|
|
|
���w����ʓV�R�L�O���u�����J�f�w�v |
|
|
|
�����n���ɂ� |
�@
|
�U4-2.���n���� ���{���s���������� |
|
|
|
|
�V�[�Y�����͒��ԗ����T�O�O�~������܂��B |
�@
|
�U5.�����隬 ���{���s�����M�� |
|
|
�u�M���v�̗R�� |
 |
|
������ |
|
|
|
�R�̒���(��̋ȗ�) |
|
|
|
�u�O�̋ȗցv���u���ȗցv�܂ł��炢�o��Ȃ����Ɓu����_�Ёv�܂œo�蓹��T���܂������ʖڂł����B |
|
|
�@
|
6�U.�_���隬 ���{���s�����_���@�@�C���@�P�X�X�� |
|
|
�_���ƌĂ��킯 |
 |
|
�u�ɂ��ɂ������q�v�i����������ψ���s�j��� |
|
�u�_���隬�v�����߂����Ȃ��|�C���g |
|
�s�w��L�O��(�j��)�_���隬 |
|
�}�Ȍ��z�̐Βi |
|
�㕔��s�͈ӊO�ɍL�����݂́u�z�K�_�Ёv���J���Ă��܂� |
|
����͍ō��ɋC��t���ĉ���ĉ������B |
���́u���̓a�l���~�Ձv�ł��B
�����P�T�V���֖߂�A�k�サ�܂��B�Q�O�O���قǂŁu�������w�Z�v�e���čX�ɂQ�O�O���قǐi�ނ�
�O���H�֗��܂��B
�O���H�ɂ͐M���@���W��������܂���B
�u�L�����v��o���K���[���}�������v�̏����ȕW�����ڈ�ł��B
|
�O���H�̖ڈ�́u�L�����v��o���K���[�����v�̊Ŕł��B |
���炭�i�ނƍ������J��ɉ˂���u��勴�v��n���
���̍������u���̓a�l���~�v�肪�ڂɓ���܂�
|
67.���̓a�l���~�� ���{���s�������@�@�C���@�P�W�P�� |
|
|
|
|
�s�w��L�O���i�j�ցj�@���̓a���~ |
|
�o���K���[���͓y�ۂɈ͂܂�Ă��܂��B |
�Ăэ����P�T�V���֖߂�X�ɖk�i�݂܂��B
|
67-1.��W�l�̐� ���{���s�������@�@�C���@�P�X�U�� |
|
|
�����P�T�V�����u�������w�Z�v�����T�O�O�����̍���(����)�ɔ肪����܂��B |
|
|
|
�����u���W�l�̐��v�̓`�� |
�@
|
67-2.�����J�f�w ���{���s�������@�@�C���@�P�X�O�� |
|
|
���w����ʓV�R�L�O��(�����P�X�N�Q��) |
 |
|
�F�̑т��f�w�� |
|
���̏��L����ʘH��������\�l�N(�P�W�X�P)10��28���A�ߑO�U���R�V���A�}�O�j�`���[�h�W�D�O�� |
|
�����n���ɂ� |
�@
|
68.���̓a�l���~ ���{���s�������@�@�C���@�Q�O�V�� |
|
|
�u���v�͈ȑO�u�����v�ł����B |
|
|
|
�����_�Љ������u���̓a�l���~�Ձv�ł��B |
|
|
|
�������n��̓����߂��̐��g�^�������̉Ƃ̎�O�𓌂֓���܂��B |
|
�u���~�Ձv�͐��g�^�������̉��̈�i��������ȏꏊ |
����隬�͍����P�T�V�����X�ɖk�ւP�D�T�����قǐi�݂r���J�[�u�ō��o����
�E���̓������֓������u�f���j�_�Ёv�̉����隬�ł��B(����������Ȃ�)
|
69.�����隬(�f��_��) ���{���s��������@�@�C���@�Q�T�W�� |
|
|
�ڈ�͍��������n��́u�f���j(�����̂�)�_�Ђł��B |
|
|
|
�����P�T�V������u�fᵖ�(�����̂�)�_�Ёv�֓���܂� |
|
|
|
�u�fᵖ�(�����̂�)�_�Ёv�Ɠǂ݂܂� |
|
���̐_�Ђ̏�ɏ隬������܂����A���ݓ��̐����Ȃǒn���ōl���Ă���B |
�u�V�嗎�Ƃ��|�R�v�͍�����Ί݂̌����Q�V�O���e�ł��B
�u�f���j�_�Ёv����r���J�[�u��߂��č�����Ί݂֓n��A�����Q�V�O���̍����_�t�߂�
�R���O�V�i�R�ňē������H�e�ɂ���܂��B
|
69-1.�V�嗎�Ƃ��i�R�j ���{���s��������@�@�C���@�P�R�V�� |
|
|
�P���@�t���B������u�O�m�i�R�v |
 |
|
�@ |
|
�P���@�t�R���n�i�O�m�i�j�i�P���@�t���B��������j �P���@�t�R���n�� |
�����P�T�V�����X�ɖk���Q�������̓����ɍ������d���������܂��B
|
69-�Q.�������d�� ���{���s��������@�@�C���@�P�R�V�� |
|
�����J�ɕ����̖�����������̌���
|
�M������ɓd�C���������\�� |
|
|
�@�������d�����߂����P�D�T�������Łu�\��(�̂���)�v�̓���
�{���s�c�o�X�u���Ì��v�o�X�₪����܂��B
|
70.�\���a�l���~�� ���{���s�����\���㌴�@�@�C���@�Q�X�W�� |
|
|
�\���a�l���~�� |
|
|
|
�\���̓��� |
|
�����֓��蓹�Ȃ�ɐi�ނƏ��ΐ�������O���H�֏o�܂��B |
|
�����̈�ԉ����u�����\���㌴�v |
|
��l�̂��N���̎p���������̂œo���čs�����ɂ��܂����B |
|
�u�a�l���~�v�͂��̏�̖̖����ꏊ�ɂ���Ƃ̎� |
|
�����������炸�E���E�����Ă�Ɓu���̉E�̗т̒��I�v�Ɖ����琺��������̂ŗт̒��ցB |
|
�\���̓a�l���~�� |
�ߏ��ɂ��a�l���~�ƊԈႦ�����ȉƉ�������܂��B
|
�C�m�V�V�����l�Ƃ̒����삯�����Ă��邻���ł��B |
���̓��̏I�_���m���߂܂����B
|
���������Ȃ��Ԃ����Ă݂����Ɛi�݂܂������A���ɂ͗����t�A�͗t�Ŗ��߂�� ���̒n�_�Łu�����\���v�T�K�͏I���I |
�\���̒��S���֖߂�r���ɓ`�����`�������́u�\�����y�v�̔��R�_�Ђ�����܂��B
|
70-1.�\�����R�_�� ���{���s�����\���㌴�@�@�C���@�� |
|
�@
|
���R�_�� |
��قǂ̎O���H���E�i�ނ��T�Om�قǂŃQ�[�g���܂��Ă��܂����B
�ȑO�͂��̉��ɂ������̏W���������Ė؍ނȂǂ̎Y�ƂŐ������Ă��܂������A
�O������̈����ȍޖ�Ƃ̌��ĕ�(�Q�~�S�����̗��s)�A
�q���̒ʊw��~�}��Â̐������ނ̖��ō��͏Z��ł��܂���̂œ~�̓Q�[�g����Ă��܂��B
�����P�T�V���͓~�G�͂����ŏI�_
|
�����P�T�V�����͑��̓�����k�Ȃ���~�G�̓Q�[�g�������Ă��܂��B |
���̓����̃o�X��I�_�u���Ì��v�ɂ͂P�����{�͗���悤�ł�
|
�{���s�c�o�X�������͂W�{����悤�ł��B |
�����M���̐l�ł��u�\���͐Ⴊ�[���v�ƌh������\����
���܂�ď��߂ė��܂����B�u�\���̓a�l���~�v��T�����߂ɂR�x���ԂŔ���ė��āA
����Ɠa�l���~�������܂����B
�Ⴊ���������ǂ��Ȃ�Ɠ~�������̌F�⒖(����)���o�ĕ|���ł��B
�����n�ʂ��@���ĐH�ו��������������Ղ���������܂����B
�n���̊F����e�Ȑl����ł����B
���肪�Ƃ��������܂����B
�s��ō����I��鍠�A���̓_���̒�̓��R�W���́u���R���~�v�u���R�隬�v�֏o�����悤�Ǝv���Ă��܂��B
����t�A�����ԈႢ�Ȃ��ړI�n�ɍs����悤���ē����ł���u�V���o�[�̎U�����v������������\��ł��B
���́u�n�����������O�U�v���̗K��J�ցI
�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_����ӂ̏隬�O�T�v�i�{���s�j